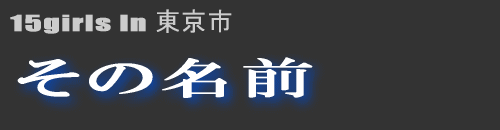
|
ガシャン!!!! 食堂のキッチンの方で響いたその音に、食堂にいた面々は一斉にそちらを注視していた。 キッチンの方では、真田さんと悠祈さんが顔を見合わせて怪訝そうな表情を浮かべている。 「ッ、痛。……なんでいきなり皿が割れるのよ」 「命さん、大丈夫ですか?私も……触ってない、んです、けど」 食堂にいる面々は、おそらく真田さんか悠祈さんが割ってしまったものだと思っていることだろう。 だけど、二人の言葉が真実であることを解っていた。私―――妙花愛惟―――だけは。 真田さんは「ちょっと切っただけだから」と言いつつ、指を唇に当てていた。 ――また、流血させてしまった。 些細な怪我で済んだ安堵感もあるけれど、それ以上に、怪我人が出たことに対する負い目を感じていた。 そう。あのお皿が割れたのは、キッチンから離れた席にいる私の所為。 私に取り憑いている悪霊の所為で、私の周りにいる人達が不幸になっていくんだ。 直接手を下すわけでもない。ただ、私が存在しているだけで、奇怪な事件が起こりすぎる。 以前に働いていた職場でもそうだった。食器や機器が破損するのは日常茶飯事。更には誰もいないはずの場所で突き飛ばされてベランダから落ちそうになった人もいるし、機械に巻き込まれて大怪我を負った人すらいる。そしてそんな事故は決まって、私が出勤している時に限っていた。 いつしか私は周りから忌み嫌われ、最終的には職を追われた。 家族もおらず、たった一人で取り残された私。 一人ぼっちだった私に、唯一手を差し伸べてくれたのが鈴様だった。 だけど最近は除霊も滞っているし、逢坂さんに付きっきりみたいだし。 鈴様すらも離れていくような気がして――じわじわと蝕むような恐怖に苛まれる。 今、私の心は孤独に包まれていた。 誰かに関われば、きっとその人を不幸にする。 だから私は一人ぼっち。 鈴様にまで見放されたら、一体どうなるんだろう。 悪霊に支配されて、悪の化身になってしまうかもしれない。 神様にすら見放されて、私という存在は、終わるのだろうか。 コクン、と冷たくなった珈琲を嚥下した。 振り向いては他に人もいなくなった食堂を見渡して、ふっと小さく安堵ともつかぬ吐息を零す。 誰もいない方が良い。誰かがいれば、その人を不幸にしてしまわないかと不安感に襲われる。 早いうちに部屋に戻ってしまおうか。幸い、相部屋の銀美憂さんはいつも制御室で何かの作業をしているみたいで、部屋に戻って来ることは少ない。 誰もいない部屋で一人で過ごす。それが一番、安全な選択肢。 この珈琲を飲み終えたら部屋に戻ろうと、そう決意した、時だった。 「どーん!!」 「わぅ……!?」 背後で大声がしたと同時に、突然後ろから背中を押されて小さく声を上げていた。 手にしていた珈琲カップを落としてしまいそうなほど、驚いた。 振り向けば、今まで殆ど言葉を交わしたことのない人物の姿。 事情聴取の時に相席はした。けれどあの時は新境地に驚き混じりだった所為か、名前が思い出せない。 青味がかった色素の薄い髪に、幾つものピアス。切れ長な瞳が、私を見下ろしていた。 「愛惟とか言ったな、確か。一人で何しょぼくれてんだ」 「え、えっと……」 「てめぇ、気合が足りねぇぜ。あぁ?」 因縁をつけられているようで身を竦める私に、人物は薄い笑みを浮かべた後でドンッと一つ私の背を叩く。 「事情聴取の時に、アタシの名前聞いたろ?まさか覚えてない、なんてことはねーよな?」 「……う」 口篭る私に、少しの間を置いた後、ポカッと拳が私の脳天を直撃する。 そうして一つ殴った後、人物は私の向かいの席にどっかりと腰を下ろした。 「ハギワラ・レン。また忘れたら、今度は殴るだけじゃ済まねぇぞ」 「ご、ごめんなさい。萩原さん……」 「憐でいいよ。しっかしなぁ、お前見てっと、陰気臭くて堪んねぇ」 「え、あ、ごめんなさい……」 憐さんはテーブルに足をかけて、まじまじと私を見つめる。 突然絡まれてオロオロしている私を尻目に、憐さんは私の飲みかけの珈琲に口をつけては「冷てぇ」と文句を漏らした。 私が押し黙っていると、憐さんは珈琲をグイグイと一気に飲み干した後、ドンッと叩きつけるようにテーブルにカップを置く。そうして私に目を戻しては、くっと眉を寄せて告げた。 「お前はゴメンナサイしか言えないのか?そうやって謝ってばっかりだから、余計に陰気臭いんだ」 「……うぅ」 そう言われても、こういう場面で出て来るのはやっぱり「ごめんなさい」なのだ。 それすらも制限されると、私は何も言えなくなってしまう。 「ほら、ゴメンナサイ以外に何か言ってみろよ。日本語ぐらい喋れるんだろ?」 「そ、それはもちろん、喋れますけど。……どうして、私に関わってくれるんです?」 素朴な疑問とばかりに、恐る恐る問い掛けた。 関わってくれているというよりも、やっぱり絡まれているという印象の方が強いのだが。 憐さんは腕を組んで私を見遣ったまま、軽く片眉を上げて答えた。 「んなもん、退屈しのぎに決まってんだろ。この施設、することねぇからなぁ」 「……それなら、別の方にした方が良いと思います」 少し視線を落として返す。絡まれているから嫌とかではない。 私なんかを退屈しのぎの相手にして、痛いしっぺ返しに見舞われるのは憐さんだ。 「折角お前を選んでやったのに、何だその言い分は」 「ごめんなさい。でも私には悪霊が取り憑いていて、関わった人は皆不幸になってしまうんです」 真摯にそう告げた。 けれど憐さんは暫し真顔で私を見つめた後、プッと小さく吹き出していた。 「なんだそりゃ?ガキじゃあるまいし、んなもん信じられるかよ」 「本当なんです。鈴様も、私に強い霊気を感じると仰いますし、それに実際私の周りの人達が――」 「バッカやろう!」 言葉途中で大声に遮られ、私は目を丸めていた。 一喝の後、憐さんはふっと鼻で笑って言葉を続ける。 「もし霊とやらが実在したとしてもな。アタシは霊なんかに怖気づくタマじゃねぇよ。アタシに怯えて霊の方がどっか行っちまうさ」 笑い飛ばすように豪快に言う憐さんに、不安感が少しと、心強さが少し。 こんなふうに、霊を肯定しても尚私に怯えない人なんて、鈴様以外にいなかったから。 「……優しいんですね、憐さんは」 弱く笑んでそう言うと、憐さんは「何が?」と肩を竦めて見せた。 私は空になったカップを手に取って、席を立つ。 憐さんの優しさは嬉しい。だけどこれ以上、関わるべきではないと思った。 彼女を不幸にするわけにはいかない。 「ちょ、待てよ。霊だかなんだか知らねぇけど、このアタシをシカトするなんて許さねぇぞ?」 「……でも、憐さんを思ってのことなんです。本当に、ごめんなさい」 謝罪を繰り返しながら、早足にキッチンの方へと向かう。 だけど憐さんは、そんな私を追いかけて来た。 どうして、私をそんなに構ってくれるんだろう。身に危険が及ぶのは憐さんだと警告しているのに。 キッチンの食器洗い機にカップを収め、小さく唇を噛む。 優しくされると余計に怖くなる。私は一人でいるべきなんだ。 孤独に耐えなければ。そのためにも、人の優しさを避けなければ。 「愛惟、お前ムカつ――ッ?!」 背中に放たれた声が不意に途切れて、ふっと振り向く。 その瞬間、私は小さく目を見開いていた。 ドンッと鈍い音を立てて、憐さんの腕の辺りにぶつかった物体は、キッチンの棚の上にあった固いまな板。 ――こんなに安定の良いものが、突然落下するなんてこと、ありえない。 憐さんは左の二の腕を押さえて、眉を寄せ、シンクに凭れかかっていた。 「れ、憐さんッ……大丈夫ですか!?」 「ちくしょ……あんなところから物が落ちてくるとは思わなかった」 憐さんの青い服に、じわりと黒にも近い赤色の染みが出来ているのが見えた。 それもまた普通に考えればおかしいこと。まな板が置いてあった棚は然程高い位置にあるわけではない。 いくら固いまな板と言っても、出血するほどに強烈な打撃を与えるほどの力はないはずだ。 別の力――そう、例えば悪霊が、その力を貸したりしない限りは。 「私の……私のせいです!ごめんなさい、憐さんッ!」 「戯言ほざいてんじゃねぇ。てめぇは何も悪くないだろ……」 「……私に悪霊が憑いているから」 これが事実に他ならない。憐さんに怪我を負わせたのも、何もかも。 後悔してもしきれぬ思いに歯噛みした。 けれど、憐さんはキッと鋭い眼差しで私を見遣り、「黙れ!」と一喝する。 「てめぇに憑いてる悪霊のせいだとしても。……やっぱり愛惟は何も悪くない」 「え……?」 「愛惟の意思でやってるわけじゃないんなら、お前だって立派な被害者だ……」 憐さんは言い捨てるようにポツリと残し、腕を庇いながら歩き出す。 私は今まで考えもしなかった憐さんの言葉を頭の中で反芻した後、はっと我に返って憐さんの後を追った。 「い、医務室に!」 「行くに決まってんだろ」 少し混乱している私とは相反して、憐さんは冷静に返す。 食堂を出たところで、「待て」と憐さんは声を上げた。それは私にではなく、偶然廊下を歩いていた人物に対してだった。 「おい、アキト。可愛川鈴を呼んで来い。医務室にだ」 「アキトじゃなくてアキハだってば。アキ君の時代は終わっ……て、憐ちゃん、どしたの?!」 最初は明るく返していたその人物、秋巴さんは、憐さんの二の腕に出来た赤い染みを見て目を丸めた。 「棚から物が落ちてきてな。安定が悪かったんだろうよ。んなことより、可愛川呼んで来い」 「そうかぁ、お大事にね。はい、パシリ行ってきまぁす」 ラジャー、と秋巴さんは敬礼を一つ決めてから、とててて、と廊下を駆けて行く。 それを見送りながら、私達は医務室へと向かった。 「ったく、ムカつくんだよ、こういうの。何が悪霊だっつーの。姿現して、拳と拳の勝負しやがれってんだ」 ぼやくアタシ―――萩原憐―――を前に、落ち込んだ様子を見せる愛惟と、小さくかぶりを振る可愛川。 医務室のベッドに腰掛けて、そばにあった丸椅子をガスッと蹴倒しては、口を開く可愛川に目を遣る。 「それが出来ぬ存在故に、私のように除霊が出来る人物が古代から続いておるのだ」 「なーにが除霊だ」 「……。しかし、今回はすまなかった。私が目を離している隙を狙われてしまったな」 普段はビシバシと物事を言ってくる可愛川も、今回ばかりは自分の否を認めているようだった。 寧ろアタシからしてみりゃ、可愛川なんて出て来る幕でもないんだけどな。 ただ一応可愛川の了見も聞いておこうと思って、呼びつけたわけだ。 案の定、可愛川は霊の存在を肯定し、監督不行き届きってヤツを謝った。 「可愛川しか倒せねぇってのが気に食わねーんだ。タイマン張って負けたことのないこのアタシが、ちっとも歯が立たねぇなんて。……ありえない!!」 「有り得ると言っておろうが。お前がむきになってどうなる問題でもない。妙花の言うよう、関わらぬ方が賢明だ」 そんなことをのうのうと告げる可愛川に、少し苛立って軽く睨み遣る。 何が除霊だ。何が関わらぬ方が賢明、だ。 コイツに、んなこと言われる筋合いがあんのか? 愛惟が手当てをして、包帯を巻いた二の腕を見遣る。 こんなにあっさり攻撃を食らうなんて、やはりありえない。 物が落ちてくれば、普通その気配があって当然だ。その気配を察知して回避する。 戦いにおいて当然のことが、出来なかった。 それは、あのまな板が落ちてくる気配が全くなかったことだ。 気づいたのは視界にその四角い物質が入った瞬間。避けることも出来ずに、もろに攻撃をくらってしまった。 悪霊とやらが存在するのは、確かかもしれない。 それは気配を消して攻撃を仕掛けてくる暗殺者にも似た存在だ。 だけどッ。敵がいる以上、アタシはそいつを撃破したいんだ。 ――それから。 アタシが苛立っているのは、その正体を見せぬ敵に対してだけではない。 陰陽師とか、除霊とか、そんな偉そうなこと言いながら、何も出来ない女に対しても憤りを覚えていた。 「可愛川は本当に、愛惟のことを考えてやってんのか?」 「当然だ。逢坂のことも気掛かりではあるが、妙花のことかて気に掛けている。妙花の悪霊は、逢坂の霊よりも厄介なものだということも解っておる。今は策を探している最中だ」 「んなこと聞いてんじゃねぇよ。冷たいヤツだな、お前は」 可愛川にそう言い放った後で、ちらりと愛惟に目を遣った。 相変わらず、自分に全ての責任があるような顔をして俯いている愛惟の姿に、小さく溜息が漏れる。 何のファッションか知らねぇけど、ダサいグラサン掛けて、その目を濁らせて。 まるで、周りを隔離する壁みたいだ。 「コイツの後ろ姿、見たことがあるか?」 ぽつりと問いを掛けると、可愛川は怪訝そうな顔をして「どういう意味だ」と聞き返す。 可愛川は何も見えていない。見えているとしたら、その目に映ってんのは敵である悪霊だけだ。 確かに可愛川の任務は、その敵を撃破することなのかもしれないけどさ。 もっと、それ以前に気にすべきことってのが、あるんじゃないのか。 「……思わず、殴りたくなるような後ろ姿だよ」 そんなアタシの言葉に、尚も怪訝そうな可愛川。 けれど妙花*は、その意図を汲み取ったように顔を上げて瞬いた。 本人の前で、言いたくなんかなかったけど。 そういう憚りよりも、やっぱ可愛川に対する皮肉の方が勝っていた。 「愛惟には友達なんか出来ねぇよ。自分から閉ざしてやがるんだから」 「……」 愛惟は図星といった様子で閉口する。 そんな姿を横目に、トンッとベッドから降り立って、可愛川に一つ睨みを利かせた。 「愛惟が唯一信頼出来る人間が、お前だったんじゃないのか?可愛川」 「私が、唯一?」 「お前だった、って言ってんだろ。わかるか?だったは過去形だ」 「……何が言いたい?」 ぐいっと愛惟の手を取って、強引に引き寄せた。 「後は自分で考えろ、バカ」 履き捨てるように言って、愛惟の手を引いて歩いていく。 可愛川のことを気に掛けるように、躊躇いがちに振り向きながら歩く愛惟に、 「行くぞ、愛惟」 と一つ促し、強引に愛惟を攫っていく。 善人ぶった行動のようにも思えるけれど、これがアタシの意思のままの行動だ。 無性に、可愛川の横にコイツを置いておくのがムカつくだけなんだ。 それにアタシは善人じゃない。ただ愛惟の世話を焼いているだけじゃない。 自分の本能の赴くままに行動するさ。それで愛惟がついて来ようが来まいが、それは愛惟の自由ってやつ。 「どこ、行くんですか?」 医務室を後にして、食堂の前の廊下を通過して、ホールの入り口まで差し掛かったところでようやく愛惟は口を開く。その問いを少し保留して歩いた先にある扉。以前に都を騙す時にも使った、逢引には恰好の部屋。 「ここ」 それだけ言って、扉を開く。相変わらず薄暗い部屋は、それとなく淫佚な雰囲気が漂っている。 アタシが勝手にそう思ってるだけであって、本来は備品室という立派な役割を持った部屋なわけだけど。 愛惟を備品室に連れ込んで、扉を閉める。非常灯だけがぼんやりと部屋を照らす。このぐらいが丁度いい。 「備品室……?ここに、何が?」 おずおずと問い掛ける愛惟に、ふっと小さく笑みが漏れた。 善人にとっては、備品を調達するための部屋。だけどな、悪人にとって見れば、施錠も出来て人の出入りも少ないこの部屋は、別の用途に使われるんだ。 「愛惟は、アタシのことを何者だと思ってるんだ?」 「え……?」 「新しいオトモダチになってくれるヤツか?ちょっと乱暴なオネエサンか?」 「……憐さんは、私に優しくしてくれる人、です」 ぽつりと答えた愛惟に、「バーカ」と小さく呟いた。 甘っちょろいヤツ。世の中そんなに善人ばっかってワケじゃないんだぜ。 まぁこの施設は比較的、イイヒトが多い場所みたいだけどな。 けど、アタシは違う。 「優しくしてるわけじゃない。丁度いい退屈しのぎなだけだ」 「……でも、憐さんは」 と、何か反論してくる愛惟を、ドンッと壁に突き飛ばした。 不意を突かれたように、壁に背を打ってそのまま崩れ落ちる愛惟を、見下ろすように一視。 「こんなコトされても、優しい人だなんて言えんのか?」 「れ、憐さん……?」 壁際で尻をついた愛惟に歩み寄り、すぐそばにしゃがみ込む。 グラサンの奥で揺れる瞳がアタシを捉えていた。 このグラサンはセンスないけど、顔はまぁまぁ可愛い方だ。 身体の凹凸は少なく、まだどこか未熟な雰囲気が残る。 別に好みのタイプってわけでもないけど、こういう自虐的なやつを見ると、余計に虐めたくなるもんだ。 「嫌なら抗え。その方が楽しめる」 短く言って、愛惟の肩に手を置き、壁に押し付けた。 ビクッと小さく震える身体。僅かに身を引いたけれど、これ以上逃れることもままならない。 もう片方の手で愛惟の顎を掴んで顔をクッと上げさせると、どこか怯えたような瞳がアタシを見ていた。 そう。この目が見たかった。狩られる野兎のような、怯えた目が。 そしてアタシは、狩る者だ。 「こんな、こ、と……」 震える声で搾り出す愛惟は、その目を逸らしながら形ばかりにその手をアタシの腕に添え、押し退けるような仕草を見せた。それも強引に振りほどけば、いとも簡単に滑り落ちた。 顔を近づけて、乱暴に唇を奪った。 「ンッ……」 覚悟はしていたように、それでもやはり僅かに抵抗を見せて捩る身体を手で押さえつけ、舌を滑り込ませる。 生ぬるい人間の温度。アタシは、これが好き。 粘着質で、湿っていて、どこか甘ったるいこの味。 人に寄ってその湿度も味も違うけど、自ら身体を合わせたいと思えたヤツの体内ってのは、やけに扇情的だ。 仕事で身体を売っていたアタシは、不味いキスだって幾度となく経験した。 気持ち良くない行為だって、何度も。でもそれは食い扶ちのための行為。 今、この施設でベッドも食事も衣服すらも与えられて、それでも尚行為を求める。 本能的なものでもあり、快楽を追求するためでもある。 それをシたいと思えた相手が、なかなか見つからなかったわけだけど。 秋巴が男で、しかも少年ならばアイツに相手になってもらうところだった。 しかし秋巴はああ見えて二十六の女。話にならねぇ。 そうして蟠っていた情欲を吐き出せる相手が、やっと見つかった。 「これからお前を犯す。拒否権はない」 「わ……私でいいんですか?」 見当違いな言葉を返す愛惟が少し可笑しくて、コツンと額を小突きながら言った。 「嫌いなヤツを襲うと思うか?」 「う……優しくして下さい……」 「バーカ。優しいレイプなんかあるかっつーの」 思ったよりも早く覚悟を決めた様子の愛惟に、少しだけ拍子抜けする。 もうちっと抵抗してくれても楽しいのにな、なんて思いつつ。 まぁなんだかんだで、愛惟も人肌に飢えてたんだろう。 服の下へと手を滑り込ませて直接素肌に触れると、愛惟は不安げに顔を伏せながらも、縋るようにその手でアタシの腕を握っていた。 「憐さん……?私とこんな、深い関係を持ってしまったら、どうなるか……」 「もういい。悪霊云々は二度と口にするんじゃねぇ。アタシが不幸になろうと、愛惟の所為じゃないからな」 「……私の、気持ちの問題は?」 「ン?」 首筋に舌を這わせようと顔を近づけていたところで、不意に問われた言葉に動きを止めた。 舌を出したまま愛惟を見上げれば、一瞬目が合う。 途端、恥ずかしげに顔を赤らめて視線を逸らす愛惟に、ふっと小さく笑みを漏らした。 「アタシを好きになってもいいんだぜ?……苦しい片想いになるだろーけどな」 冗談めかして告げてから、舌先で愛惟の肌をなぞっていく。 滑らせる度にビクリと震える身体が面白くて、アタシは愛惟のウィークポイントを探るように行為を繰り返す。 コイツ、可愛い。 「あぅ……憐、さん……恥ずかし、ですよぉ……」 「それがいいんだって。今からもっと恥ずかしい目に遭わせてやるからな?」 「うー……」 堪えるような喘ぎ声に不覚にもクラックラしながら、アタシは更に深く深く、愛惟の身体を探っていく。 震える度、溢す度、湿度を増すコイツがもっと知りたくて。 抱くはずもなかった独占欲が、心ん中で膨れ上がって行くのを感じていた。 可愛川なんかに渡さねぇ。今は、コイツはアタシだけのモノ。 ――がちゃ、ぱたん。 自室に戻って扉を閉じると、部屋の奥で人の動く気配がした。 おそらく寝台に身を横たえていたのだろう、逢坂は上体を起こして小さく笑みを見せていた。 私―――可愛川鈴―――の帰りを待っていたかのような、その所作。 「おかえりなさい、可愛川さん」 「うむ。……まだ調子が優れぬか?」 気丈な笑みこそ見せれど、毛布を被って身を横たえていたらしい逢坂にそう問い掛ける。 逢坂は少しの思案の間を置いてから、曖昧な語り口で返す。 「調子が良いとは、言えませんけど……でも可愛川さんがいてくれれば、幾分楽になるような気がします」 「そうか。暫しは、逢坂のそばに付いておくことを心がけよう」 逢坂と向かい合わせになるよう、自身の寝台に腰を下ろしながら告げれば、逢坂はどこか安堵したような表情を見せて頷いた。 逢坂も、最初の頃から考えれば随分素直になった。私に心を許していると捉えても良いのだろうか。 「私のことよりも……憐さんと愛惟さん、何かあったんです?突然呼び出しだなんて」 「あぁ。妙花の悪霊の件はお前にも話したな。その悪霊が、また暴れた。萩原に怪我をさせたのだ」 「それで緊急呼び出し、ですか。ふぅん。憐さんの怪我は大したことなかったんです?」 「幸いにもな。軽い出血程度で済んだ」 そう答えると、逢坂はどこか不思議そうな表情で私を見つめる。 「何だ?」と小さく問い掛けると、逢坂はぱちりと幾つか瞬いた後、言った。 「愛惟さんの悪霊のことはよく解りませんけど。……可愛川さん、愛惟さんのそばに付いてなくても大丈夫なんですか?今まで愛惟さんに付きっきりだったでしょう?なのに突然、私のことで騒がせてしまったから。愛惟さんのこと、最近構ってないんじゃないですか?」 「……確かに、その通りだ」 逢坂の言葉に、先程萩原から言い放たれた言葉が思い出される。 『愛惟が唯一信頼出来る人間が、お前だったんじゃないのか?可愛川』 と、その言葉は余りにも当然過ぎて。 妙花のそばに居ても良いのは私だけだった、はずだった。 私こそが唯一、妙花の悪霊に抵抗する術を持つ者。妙花に関わっても不幸が降りかからない者だ。 それなのに、そんな定説を打ち破るように、萩原は続けた。 『お前だった、って言ってんだろ。わかるか?だったは過去形だ』 妙花に対する考え方を全て否定されるような一言。 私だけが妙花のそばにいるべき存在。他に妙花のそばにいようとする人間など存在しないと思いこんでいた。 だけど。――妙花は、萩原に攫われた。 「それじゃ、愛惟さん寂しがってるんじゃないですか?私が可愛川さんのこと、独占しちゃっているから」 「……否。問題はないと、思う。妙花には萩原がいる」 「憐さんですか?……もしかして、三角関係?」 逢坂はくすっと小さな笑みを伴って、どこか楽しげに小首を傾げた。 まるで私達の問題を、客観的に見ては楽しんでいるかのように。 そんな逢坂に、嘆息を一つ漏らして首を横に振る。 「勝手に色恋沙汰にするでない。私と妙花は悪霊という接点で繋がっているだけだ。妙花と萩原の関係までは私が関知するところではない。……ただ、萩原に霊の悪行が降りかからぬかが心配なだけであって」 「じゃあ可愛川さんは、愛惟さんと憐さんが恋人になっても、構わないんですね?」 「……突飛な話だな。まぁそれは、妙花の悪霊さえ除霊出来れば、その後は一向に構わぬぞ」 私の中で用意された答えのように、そう告げた。 けれど、告げながら何らかの違和感に捉われて、少し視線を落とす。 妙花の除霊が完了したら、私と妙花の接点はなくなる。それが当然のことであるはずなのに。 一体何が、気掛かりなのだろうか。 「でもね、可愛川さん。愛惟さんって、可愛川さんのこと好きなんじゃないでしょうか」 「……な?何を言い出すか。そのようなことは」 「私、愛惟さんの気持ちが解るような気がします」 私の微かな狼狽に気付いては、それを楽しんでいるかのように続ける逢坂。 逢坂の表情に笑みが点っている、そのことだけを考えれば喜ばしい。 しかし、逢坂の笑みは私をからかって楽しんでいるものではないか。 「最初は可愛川さんのこと、別に何とも思ってなかったんですよ?私。……だけど、可愛川さんは真剣に私のことを想って、戒斗の件に取り組んでくれている。そんな姿を見ていると、心、揺れちゃうんです」 「……心が、揺れる?」 「はい。きっと愛惟さんも同じだろうし、可愛川さんと一緒に過ごしている時間が長い分、私以上の気持ちを抱いてるんじゃないかなって。だから愛惟さん、可愛川さんのことが好きなんですよ」 結論付けるように言っては、「多分」と笑みで付け加える逢坂。 その考え方が暫し理解出来ず、頭の中で逢坂の言葉を反芻する。 妙花が私のことを想っている?恋愛感情を抱いているというのか? 私は妙花に対して、悪霊を秘めている人物であり、除霊を行なうべき対象としか見ていないはずだ。 それが私の役割。必要以上に、妙花に関わることはない。 「憐さんが愛惟さんにモーションをかけているとして。愛惟さんは可愛川さんのことが好きなはずなのに、憐さんにも心が揺れてしまっている。可愛川さんはまだ自分の気持ちに気付いていない。複雑な三角関係ですね」 「……逢坂の憶測通りならば、な」 どうせ外れているだろうと、軽く返した。萩原\の真意は解らないが、妙花は私に対して特別な感情を抱いているとは思えない。それは私も同様である。 「私はその複雑な関係を更に複雑にすることが出来る」 と、逢坂が不意に口にした言葉に、思わず怪訝な表情を浮かべていた。 逢坂は楽しげに口の端を上げながら、こう続けた。 「私が可愛川さんを奪う、なんて展開も有りじゃないですか?さぁ私に可愛川さんを取られた愛惟さんは一体どうするのでしょう。乞う、ご期待」 「……」 やはり逢坂は、私をからかっている。 逢坂が並べ立てる言葉の全ては、いずれも推測に過ぎない。 そしてその推測が当たっているとも、思えない。 「私が好き勝手言ってる、って思ってるんでしょう?」 「え?……いや、まぁ」 心中を見抜かれて、思わず言葉を濁していた。 逢坂はにっこりと笑みを深め、毛布を剥ぎ取って寝台から降り立つ。 そして私の寝台に移動して、私の隣に腰を下ろした。会話をするには少し近すぎるほどの間近な距離。 「確かに私の言っている全てが、正しいとは限らない。だけど一つだけ確かなことがある」 「それは?」 前を真っ直ぐに見据えて告げた逢坂に言葉を促せば、逢坂はふっと私を見上げ、悪戯な笑みを見せた。 「私は可愛川さんのこと、好きですよ。……恋愛感情なのか否かまでは、まだ解りませんけどね」 「……逢坂?」 「ふふ。可愛川さんって色んなことを知っていそうだけど、恋愛に関しては疎いんでしょう?」 確信めいた口調で告げられた内容に、返す言葉を失った。 そんな私の困惑を深めるように、逢坂はその身体を私に凭れかけ、緩く腕を抱いた。 密着した逢坂に、一つため息を漏らしてから、私は言った。 「確かにお前の言う通り、恋愛云々はよく解らぬ」 「恋愛なんて簡単ですよ。抱きたいって思えれば、いいんですから」 「……随分難しいことのように思うが?」 怪訝に返せば、逢坂は相変わらず楽しげな笑みを湛えたままで、するりと私の手を絡め取る。 逢坂の小さな手が、私の手に絡んで、握る。 手を握られたというよりも、捕われたように感じるのは気の所為か。 「いつかそう感じるときが来ると思います。相手は多分、愛惟さんか……私か」 「お前には戒斗がいるのではなかったか?」 「戒斗は戒斗。可愛川さんは可愛川さん。第一、可愛川さんが言ったんですよ、現世の人間を幸せにするんだって。戒斗と私の関係に否定的なら、可愛川さんが責任を取ってくれないと」 「……責任を取るとまでは言ってないはずだが」 「じゃあやっぱり私は戒斗と一緒に逝きますからッ!」 不貞腐れたように言う逢坂に、内心ため息を零しつつ、首を横に振った。 「それは駄目だ。私の所為でお前を死なせるようなことになったら、私がどんなに後悔するか解るか?」 「解りますよ。だーかーらー、責任取って下さいねッ」 一転してにこりと表情を綻ばせる逢坂に、は、と吐息が零れた。 演技なのか何なのか解らぬが、逢坂には振り回されるばかりだ。 どこまでが逢坂の本音なのかも解らぬが。 現時点で、逢坂に対してどのような気持ちを抱いているかと問われれば、それは恋愛感情以外であることは確かである。私にとっては、逢坂も妙花も除霊の対象でしか、ないはずなのだが。 「愛惟さんは可愛川さんと憐さんの間で揺れてる、かぁ。……じゃ私も、憐さんに揺れてみようかな」 「何を言っている?話が余計にややこしくなるではないか」 「私、好きなんですよ。ドロドロの人間模様。複雑な方が楽しいと思いません?」 「思わん」 一言でばっさりと言い切って、肩を落とした。 逢坂の話には、本当についていけない。 ただ、逢坂の一言だけが頭の中に残って離れようとしなかった。 『愛惟さんは可愛川さんと憐さんの間で揺れてる、かぁ』 あくまでも逢坂の推測だ。それも、限りなく当てずっぽうな。 しかし万が一。この逢坂の推測が当たっていたら、一体どうなるのだろうか。 或いは片側だけが当たっていたら――妙花が、萩原に対して恋愛感情を抱いている、としたら。 「逢坂、一つ問いたい。お前の得意な推測で構わぬが、萩原は妙花に対してどのような感情を抱いている?」 そう問うと、逢坂は小首を傾げて考えた後、軽い笑みを浮かべて返す。 「憐さんは遊んでる感じの人ですからね。愛惟さんも遊びでしかないんじゃないです?」 「妙花が遊ばれている、と?」 「ええ。愛惟さんって純粋そうな人でしょう?悪い言い方をすれば、騙されやすいんだろうなぁと」 「……」 もし、そうだとしたら。 だったら。――だったら、何だというのだ? 自身の感情が上手く整理出来ずに戸惑っている。 妙花に対しての、感情が。 解らぬものは仕方がない。ならば私はどうしたら良いのか。 そう考えて、一つの行動が思い浮かぶ。 解ることから、明確にして行けば良いのではないか、と。 「遊びに決まってんだろ?愛惟が寂しそうにしてっから、構ってやっただけだ」 咥え煙草のまま、発音の悪い響きで言葉を返した。 飯を食い終えて廊下を歩いていた時、不意にアタシ―――萩原憐―――を呼び止めたのは可愛川だった。 いっつも以上にクソ真面目な顔をして、可愛川は問うた。 「萩原。お前は妙花に対して、どのような感情を抱いて接しておるのか」……だとさ。 アタシは当然の答えを返す。今言えるのはそれ以上でもそれ以下でもない。 愛惟は都合の良い遊び道具。アタシだけの、玩具。 「お前はそのような甘い考えて妙花に関わっておったのか?」 「んだよ、悪ぃかよ」 「ならば今一度警告する。妙花には近づくな」 きっぱりと告げる可愛川に返す言葉を、少し考えた。 煙草を吸い込んで、吐き出す。 沈黙の中で浮かび上がる感情は、「ムカつく」の一言。 可愛川のヤロウ、今でも愛惟を自分のもんだと思ってんのか? 今日の昼間に言ってやったはずだ。『お前だった、って言ってんだろ。わかるか?だったは過去形だ』 その言葉は事実になった。愛惟はアタシに身体を許して、暫しの時間、行為に興じた。 愛惟が軽い女とは思えない。アイツはアタシに心も許して、信頼を寄せている。 だからこそ身体を許したんだ。行為こそが立派な証拠。 「関わって不幸になろうが、そいつはアタシの自己責任ってやつだ。それとも、他に理由があるのか?」 「理由だと?」 「愛惟をアタシに奪われたくない理由だよ」 「……否。私はただ、お前の身を案じているだけだ」 否定する直前の一瞬の間に、可愛川の心理を垣間見た。 ふっ、と薄く笑みを浮かべ、煙草の紫煙を吐き出しながら可愛川を見遣る。 「解った。お前、愛惟に気があるんだろ。もしかして可愛川さんともあろうお方が、嫉妬してるんですかー?」 からかうように言ってやれば、可愛川は案の定カチンと来た様子でかぶりを振った。 「馬鹿なことを。私はそのようなつもりで妙花をそばに置いたわけではない」 「じゃあ、別に構わないよな?アタシが愛惟の心も身体も、全部掻っ攫ってもさ」 「それは、妙花の決めることでもある。……妙花はお前のような軽い女に心を許すはずがない」 蔑むような言葉も、アタシにとっては優越感に浸れる一言だった。 馬鹿なのはお前だ、可愛川。 「既に愛惟はアタシのモンだ。……医務室を後にしてから、アタシと愛惟が何をしてたと思う?」 「……」 可愛川は怪訝そうな表情で、口を閉ざす。 想像もつかないだろう。解るはずがない。愛惟の心情も察してやれない、こんな冷たい女には。 「愛惟は既にアタシに身体を許した後だ。――可愛かったぜ?」 「な、……なんだと?妙花がお前に、身体を、許ッ……」 あからさまに動揺する可愛川の姿ってのは、レアかもしれない。 普段の真面目くさったポーカーフェイスからは、想像も出来ない姿。 コイツも一応人間なんだな。そこに感心するぜ。 ――可愛川は、愛惟のことが好きなんだな? 「もう遅い。愛惟はてめぇより、アタシの方が好きなんだ。あんな純情そうなヤツだ、一度身体を許した相手を簡単に忘れるわけがないだろ?」 「……今一度問う。お前は妙花に対して、どのような感情を抱いているのだ」 「何度も言わせんな。遊びだっつって――ッ」 ドンッ、と廊下の壁に押し付けられて、言葉が途切れる。 アタシの喉元に当てられた手は微かに震えて、その怒りを露わにしていた。 「妙花を弄ぶような真似は許さぬぞ!」 「何すんだッ……アタシがどう思ってようと勝手だ。問題は愛惟の気持ちじゃねぇのか」 「黙れ。妙花が真摯にお前を想うならば、それは許し難いことだ。お前は妙花の気持ちを受け容れることなど出来ぬのであろう!?」 グッと、喉元を掴む手に力が篭る。 感情的にアタシを責める可愛川に対して、半分は冷静に、そして半分は感情的に。 小さくもがいた後、ガンッ、と腕を振るった。 可愛川の頬を捉えた拳で、アタシはようやく自由になる。 可愛川は打たれた頬に手を当てて数歩後退しながらも、キッと鋭い眼差しをアタシに向けた。 「お前は妙花を幸せにすることなど出来ぬ。お前に、妙花のそばにいる資格などない!」 「何を偉そうにのたまってやがる。可愛川、てめぇ人のこと言えんのか?」 「なんだと?」 「愛惟の気持ちなんか考えたこともない癖に、保護者ぶるんじゃねぇっつってんだよ。本当に愛惟のことを想ってんなら、アイツの気持ち察してやれよ。言っただろ?お前だけが唯一、愛惟が信頼に値する人間だったんだ」 「……」 柄にもなく真剣に告げれば、可愛川は言葉を失い、僅かに視線を落とした。 今更気付きやがって。もう遅い。――と、言いたいところだけど。 まだゲームオーバーじゃない。 一度愛惟がアタシに身体を許したからと言って、それで愛惟の気持ちが確定したわけじゃない。 アタシが本気で愛惟に惚れてんなら、アタシだってまだ頑張るさ。 だけど、アタシは本気じゃない。愛惟のことは遊びでしかない。 可愛川の言う通り、アタシが愛惟のことを幸せにしてやることは、多分出来ない。 それ以前に、アタシは愛惟の幸せなんて、そこまで興味のあることじゃないんだ。 「悔しいなら取り返してみせろ。愛惟はお前のことを見捨てたわけじゃないだろうからな」 「私は……妙花に対して恋愛感情を抱いているわけでは、ないのだ。ただ、これ以上妙花を不幸な目に遭わせたくない一心で、妙花に関わっていた。……妙花を傷つけたくない」 「そうか。ならそれを実践してみればいいんじゃねぇのか?まずはアタシからアイツを引き離すところからだな」 「妙花をお前のそばに置いていれば、妙花は傷つくか」 「多分な。アタシはそれが楽しいと思う、残酷無慈悲な人間だからな」 自分でもしっかり自覚している。それをストレートに告げれば、可愛川は思案の間を置いてから、ふっとアタシへ目を戻した。 「責めてすまなかった。萩原は妙花を気にかけてくれたのだな。……面倒をかけた」 可愛川はそれだけ言って、アタシに背を向けて歩き出す。 「別に」 短く告げて、壁に背を寄せながらぼんやりと可愛川の後ろ姿を見送った。 アタシは一体、何を言ってんだろうな。何のために、誰のために、こんな言葉を紡いだんだろうな。 愛惟とのことは遊びだった。惚れてなんかいない。これは確かだ。 だけど、心のどっかで独占欲を抱いていた。愛惟を可愛川なんかに渡してやるか、ってな。 愛惟はアタシにとって、都合の良い玩具だった。 アイツの中にいる悪霊とやらも、興味深かった。強い敵には立ち向かいたいからな。 ただ、それだけ。何度も言っているように、丁度良い退屈しのぎ。 「愛惟、か……」 一人になった廊下で、ぽつりとその名を呟く。 アイ、っていう名前。一文字の愛ではなくて、愛を惟るって書いて、アイ。 “惟る”。それって、どういう意味があるんだろうか。 別に、どうでもいいこと、だけどな。 「どうでもいい。……どうでもいいよ」 ふっと零れる嘆息と、苦笑い。 残念なのは、折角の遊び道具を可愛川に奪われちまったからだろうか。 まぁいいさ。フリーの女はまだ何人もいるんだし。 その中から、新しい玩具を見繕ってやろうぜ。 コンコン。 響いたノックの音に瞬いて、私―――妙花愛惟―――はベッドから立ち上がる。 銀さんと相部屋のこの部屋だけど、銀さんは朝早くから夜遅くまで戻って来ることはない。 今は夜の九時過ぎ、銀さんが戻って来るまではまだ随分時間があるだろう。 それに銀さんはノックをしないし。とすれば、誰かが訪ねて来たのだろう。 早足に出入り口に向かって扉を開けると、そこにいたのは―― 「妙花、突然すまぬ。少し話がしたい」 真っ直ぐに私を見つめる瞳。ドキッとして、一瞬声が出なかった。 「……り、鈴様?どうなさったんですか?」 彼女を部屋へ招きいれながら、問い掛ける。 よく考えれば、突然というわけでもないのかもしれない。鈴様は除霊のために頻繁に私のところへ来て下さっていた。だけど、最近は逢坂さんの件でお忙しいみたいだったし、お昼間にあんなことがあったばかりだし。 それに、今回は除霊のために訪れたわけではないようだった。 「お前とはゆっくり話す機会もなかったな。申し訳無いと思っている」 「そんな……私のことは良いんです。逢坂さんの方が、今は調子が良くないんですよね?」 愁傷な様子の鈴様に首を振りながら、部屋の奥のテーブルセットへ促した。 丸テーブルを囲んで向かい合わせに腰を下ろすと、改めて鈴様の真摯な表情が見て取れた。 それと同時に、彼女の頬に青痣が出来ていることに気付く。 「……可愛川さん、頬、どうしたんですか?」 「これか?……いや、何でもない」 「殴、られたように、見えますけど……」 「聞くな。自業自得だ」 可愛川さんはきっぱりと言い切って、私が言葉を返すより早く、話題を変えていた。 「逢坂は逢坂で、良くも悪くもといったところだが。……それよりも、お前のことが気にかかってな、妙花」 「私は……どう、なんでしょうね。今日も憐さんに怪我をさせてしまったけれど……」 自覚できない悪霊の所業に、躊躇っていた。悪霊は姿を隠したかと思えば、突如悪行を起こす。 調子が良いとは言えないと思うけれど、私は…… 「悪霊のことは、今回は保留とさせてもらう」 「……え?」 鈴様が告げた言葉が、理解出来なくて小さく問い返した。 だって鈴様は私の悪霊を払うために、私のところに来てくれている。そう思い込んでいたから。 「昼間の件。萩原の言葉が気にかかって、仕方なかった」 憐さんの名前が出て来ると、内心ドキッとする。 まさかあの後、あんなことがあったなんて。 鈴様にバレたら、恥ずかしすぎるし、それにばつが悪い。 「つい先程、萩原に話を聞いて来た。……全てのことを」 「え……、え!?」 ぽつりと告げた鈴様の言葉に、頭がスパークしていた。 全て?全てってまさか、私と憐さんが身体を重ねたことも、全部……!? 「私は、妙花と萩原と仲に口出し出来る立場ではないのかもしれん。妙花が自ら望んで、萩原に身を委ねたのであろう」 「ちょ、ちょっと待って下さい、その、それは、あのッ……」 顔にどんどん血液が集まってくるのを感じながら、熱くなった額に手の甲を当てる。 益々混乱してくる頭。どうして鈴様が、私と憐さんのことを!? ……憐さんが、話したってこと?どうして、鈴様にそんなことを話してしまうの? 「大丈夫か?」 と、心配そうにかけられた声で、ようやく私は鈴様に目を戻した。 だけどやっぱり真っ直ぐに彼女を見ることが出来なくて、視線を落とす。 何を言ったら良いのかも解らずに押し黙っていると、鈴様はどこか不思議そうに問い掛けた。 「萩原との関係……私には、知られたくなかったのか?」 「……それは勿論です。だって」 ――だって。 知られたく、ないに決まっている。 どうしてって、理由は、わからないけど。 鈴様にだけは、知られたくなかった。 「妙花。私も余り、知りたくなかった。……だけど知ったことで、気づいたことがある」 訥々と語られた言葉に、ゆっくりと鈴様に視線を戻した。 鈴様は少しだけ言い躊躇うような間を置いた後で、真っ直ぐに私を見つめて告げた。 「私は、お前を萩原のそばに置いておきたくない」 「……え?」 「萩原が自分で言っている通り、お前との行為は萩原にとって遊びに他ならない。そんなやつに、妙花を任せるわけにはいかない。……萩原では、お前を幸せにすることなど出来ぬのだ」 「れ、憐さんは優しい人ですよ……?」 おずおずと言い返せば、鈴様はゆっくりと首を横に振った。 「確かに、萩原かて残酷な人間でないことは解っておる。しかし、……何というか」 と、鈴様は言葉が見つからない様子で口篭る。 鈴様はいつもきっぱりと物を仰る方。だから、こんなお姿に少し驚いていた。 鈴様は少しの沈黙を置いた後、緩く視線を落としたままで、言った。 「私は妙花を他の者に委ねたくないと、そう思う。……自分でも理由が解らぬのだ。けれど、私は、私以外の人間に妙花を……渡したく、ないと」 「……り、鈴様。それって」 心音が早鐘のように速度を増していた。 あの鈴様が、こんなにも言い躊躇って、それでも精一杯私に何かを伝えようとしている。 その、伝えようとしている内容は―― 「妙花」 「は、はいッ……」 真っ直ぐに、見詰め合う。 鈴様の綺麗な瞳が、私を見ている。 ゆっくりと開かれる唇。 ドクン、と心音が一つ鳴った時、鈴様は告げた。 「お前には悪霊が憑いておるのだ」 「…………は?」 「だから!いつも言っているように、他の者に関われば、その者を不幸にする。故に、私以外の人間とは関わるな。良いな」 「……」 拍子抜け、していた。 今までの雰囲気とは一転して、いつものビシバシした物言いの鈴様に、思わずふっと弱い笑みが零れる。 な、なぁんだ……期待して、損しちゃった……。 「ただ、私は一つ反省せねばならぬ」 鈴様はその表情を幾分和らげて、言葉を続けた。 「妙花に、私とだけの関係を強要することで、お前を孤独へと追い詰めていた。それに気付けなかったことを、謝罪する。すまなかった」 「鈴様……」 「今後は極力、お前との時間を割くこととしよう。それから、他の者と一切関わるなとは言わない。萩原かて悪い人間ではないはずだ。肉体関係はどうかと思うが、仲良くする分は構わぬぞ」 と、どこか柔らかい笑みを湛えて告げられた言葉に、なんだか温かい気持ちを抱いていた。 やっぱり鈴様は優しいお方だ。そんな方だから信頼して、除霊をお任せしている。 私にとって、やっぱり鈴様はかけがえのない人。 「――愛惟」 ぽつり、小さく紡がれた、名前。 私は彼女の口から発されたその響きに、少しだけ驚いて幾つか瞬いた。 鈴様は思案するような間を持って、それからふっと小さく笑みを漏らしていた。 「いつも思っていた。良い名前だと。私にはまだ愛の定義がよく解らぬがな、愛を惟るという名はとても深い」 「あ、ありがとうございます。亡くなった両親が、名づけてくれたんです」 「そうであったか。愛惟、……私にはその必要がありそうだ」 「必要?」 小さく問うと、鈴様は椅子を立って、私のそばに近づいた。 ぽむ、と頭に乗せられた手。ふわりと柔らかく、髪を撫ぜてくれた。 「惟るという言葉は、思いを巡らせるという意味であろう?――愛について惟る」 柔らかな口調で告げてから、すっと鈴様の手の感触が離れていく。 それがどこか寂しくもあって、鈴様を見上げれば、優しい表情で私を見つめる鈴様と目が合った。 「愛について、理解が出来たら。その時には真っ先にお前に伝えよう」 そう言って、ふっと笑みを深める鈴様。 言葉に含まれた意図が、上手く汲み取れなくて少しもどかしかったけれど。 だけど、それはきっと、私にとって嬉しいことなのだろう。 「はい。その時を――待って、ます」 こくんと小さく頷けば、鈴様は満足げに一つ頷き返し、静かに私から視線を逸らした。 「それでは、失礼する。人恋しい時は一人で抱え込まず、私のところへ来るように」 「はいッ。……おやすみなさい」 鈴様の優しさが嬉しくて即答した私に、鈴様は少しだけその肩を揺らしたように見えた。 そうして、部屋を去っていく鈴様の姿を見送った。 パタン、と扉が閉じて、また部屋に一人きり。 だけど今までのように、孤独を抱くことはない。 「……鈴様」 そっと胸元に手を当てると、いつもより少し速く音を立てる心臓の感覚。 寂しいときに、そばにいて下さって。 私に巣食う悪霊に対し、懸命に対処して下さって。 そして時折、ドキッとするような優しいお言葉をかけて下さるお方。 私は、きっと―――鈴様に、恋してる。 いつか教えてくれるだろうか。彼女にとっての愛の定義。 その時にはまた、私の名前を呼んで欲しい。 その愛しい声で、愛惟、と。 |