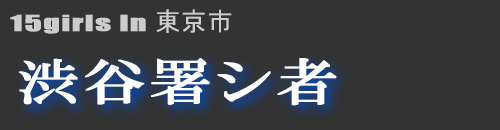
|
曇り空の下、ちょっぴり重たいビニール袋を手にして早足に署へ急ぐ。 入り口の両開きの扉を肩で押し開ければ、見慣れた長い廊下が真っ直ぐに伸びている。 以前は賑やかだった署内も、今は人の気配が無い寂れた空間だった。 だけどここには、私―――小向佳乃―――を待ってくれている人がいる。 廊下を少し進んだ先の『交通課』の札がかかった扉、また肩で押し開けてから、私は言った。 「蓮池先輩ッ、お昼ご飯買って来ましたよぉ」 私と千景が属している渋谷署の交通課。ここには今、蓮池先輩が一人で滞在している。 蓮池先輩は部屋の一番奥の『課長』というネームプレートが乗っかった大きなデスクに座していた。 「おかえりなさい、小向。五人分、調達出来た?」 蓮池先輩はいつもの優しい微笑で、私を迎えてくれた。以前はこうして私や千景がお昼ご飯を買いに行くのがいつものことだった。だけど、今は千景もいないし、たった二人の交通課。 でもこれで寂しいなんて言っていられない。私と千景が施設にいる間は、先輩はずっと一人きりだったんだから。だけど先輩は寂しさなんて微塵も感じさせない、大人さんだなぁって感心しちゃう。 「今日は五人分ありました……けど、地方からの輸送が難しくなってて、今後はどうかわからないってお店の人が話してました。もしかしたら近いうちに、お店を閉めて疎開するかもしれないって」 東京市は日を追うごとに過疎化が進んでいる。理由は第一に米軍の本拠点があるということ、そして第二に災害の被害が激しい地域であること。東京市は常に警戒を要する場所であり、国内でも極めて危険な区域に指定されている。だから東京市を離れ、地方に疎開する人々は数知れない。東京市に残っているのは、何か理由があって東京市を離れられない人々が殆どだ。帰る場所がない人、交通費すら捻出できない人、或いは私達のような、お仕事のために離れられない人。 「東京市を去るのは賢明な判断でしょうね。……だけど、そうすることが出来ない人も多い。私達は残された人々のために、最善を尽くしましょう」 真摯な言葉の後に、柔らかい微笑み。その姿に少しだけ見惚れてから、私は「はい!」と頷いた。 蓮池先輩はまだ二十八歳なのに、とてもそうは見えない落ち着きがある。老けてるとかじゃなくて、精神的に大人っていう意味で。切れ長ながら優しげな瞳も、後ろにアップにした髪も大人さんだし、いつもビシッと決まっている制服も彼女の性格を表しているみたい。 蓮池先輩は警官の鏡のような人物だ。人々のために正義を貫き、悪すらも罰するのではなく正そうとする。 自分の身すらも省みずに、日夜この渋谷署で警察の仕事を全うしている。 だけどそんな先輩の身体のことが、私は心配だったりするんだけどなぁ。 「どうしたの?そんな複雑そうな顔をして」 先輩は私を見つめてきょとんとし、すぐにふっと小さく笑む。 先輩は私が手にしたビニール袋を示して、「早く皆に届けてあげて」と優しく言った。 「蓮池先輩も、ちゃんとご飯食べてエネルギー蓄えて下さいね!」 ビニール袋からお弁当を一つ先輩の机に置いて、それからペコリと頭を下げる。 「ありがとう。小向もね。私は少し仕事が残っているからデスクを離れられないけれど、皆のこと宜しくね?」 「はい、任せて下さい!」 どどん、と胸を叩きながら言って笑んでから、「いってきまぁす」と意気込んで奥の部屋へと進んで行った。 署には先輩が一人で滞在してるって言ったけれど、実は今は他に三人の人物がいる。 それぞれの理由によって、警察に保護された三人の女性だ。家族もなく、帰る場所もなく、そして自活能力もないと見なされた女性達。 今回私が署に戻って来たのは、この三人を地下施設に連れて行くためだった。 今は書類上の問題で少し足止めを食っているけれど、今日の夜には施設に戻れる見込みになっている。 彼女達には奥の休憩室で待機してもらっていた。休憩室といっても古びた簡易ベッドが四つと、ソファが二つ、テーブルが一つあるだけの空間。待機するには退屈すぎる空間だろう。 コンコンッ。 ノックをしてからドアを引くと、古びた蝶番がギィィと軋む。 「お待たせしましたッ、お昼ご飯でーす」 笑みを持って告げるけれど、返されるリアクションは沈黙だった。 三人の視線が私に向けられては、ふっと逸らされる。……うぅ。 三人の女性達は、向かいあわせの二つのソファにそれぞれ座っていた。 向かって右側のソファには、逢坂七緒(オオサカ・ナオ)さんが一人で座っている。 七緒さんは落ち着いた雰囲気の綺麗な女の子だ。黒髪のボブヘアに、どこか鋭い瞳。十八歳なんだけど、パッと見は二十歳を越えているようにも見えるなぁ。 七緒さんは私と視線を合わせるでもなく「ありがとうございます」と小さく頭を下げた。基本的に言葉が素っ気なくて、ちょっと刺々しくて怖いけど、きっと根はいい子なんだよッ!伊純ちゃんみたいに! それから向かって左のソファの手前に座っているのは、優しげなお姉さん、三森優花(ミモリ・ユウカ)さん。 ふんわり柔らかそうな茶髪に、垂れ目がちな瞳。柔らかくて優しげ、この言葉が一番似合うなぁ。 「あ、ありがとうございます、佳乃さん……食事まで用意してもらえるなんて、なんだか申し訳ないです」 三人の中では一番心を開いてくれている感じのある人。色々と気を使ってもらえるし、二十四歳っていうことで私とは一個違いで親近感とか湧いちゃうし、三森さんの存在は密かに助かっている。 そして三森さんの隣に座っているのは、楠森深香(クスモリ・ミカ)さんだ。 肩よりちょっと長いぐらいの黒髪で、前髪は少し短め。眼鏡を掛けていて、その奥には少し大きめのくりくりっとした可愛い瞳が見える。笑えばきっと可愛い人なのだろう。……だけど彼女の表情は、まるで感情がないようにいつも冷たく、その顔には幾つもの痛々しい切り傷が見えていた。 楠森さんは決して目を合わそうとしない。言葉を交わそうともしない。私はまだ一度も彼女の声を聞いていない。二十六歳で、以前は公務員だったとのことだけど、何かの出来事で心を閉ざしてしまったのだろうか。私は先輩から詳しいことを聞いていないからわからないし、詮索すべきことでもないのかもしれない。 三人の前にお弁当を置いてから自分の分も確保して、私は七緒さんの隣に腰を下ろした。 三人の様子を眺めてみるけれど、やっぱこの三人、なんとなく重たい雰囲気がある。 そんな空気を追い払うように、私は努めて明るい声で言った。 「いただきまぁすッ!」 パンッ!と手を合わせてご挨拶。 そんな私に三森さんは弱く微笑んで、真似るように軽く手を合わせてくれた。 七緒さんは特に興味もないとばかりにお弁当を開けている。そして楠森さんに至っては私の声が聞こえてもいないかのように、目を逸らしたままで押し黙っていた。 「楠森さん、ちゃんと食べないと身体に毒ですよ」 そう呼びかけると、彼女はビクッと小さく身を竦ませ、益々顔を伏せてしまう。 昨日からずっとこんな調子で……彼女は、何も口にしていないんじゃないかな。 心配だけど、私はそれ以上掛ける言葉を持たなかった。楠森さんは干渉されることを拒んでいる。 楠森さんだけがお弁当に手をつけず、私達三人は黙々とお弁当を口にしていく。 こういう時千景がいたらなぁ。もうちょっと話題とか出してくれそうなのに。 いやいや、千景に頼ってばかりもいられないッ!私が頑張らなくちゃ! 「……あ、あの、えっと。今日の夜には地下施設に移動することになると思うんです」 そう切り出すと、三森さんは真っ直ぐに私の目を見て話を聞いてくれる。七緒さんは隣からちらりと横目を向けて、「了解しました」と素っ気なく言葉を返す。楠森さんはやっぱりノーリアクションだ。 「それでですね、えっとぉ……地下施設は賑やかで楽しいところなので、皆さんも気に入ってもらえると思います。今、十八人……かな。そのぐらいいるんですけど、女性ばっかりで本当に賑やかなのです。ほら、女三人で姦しいとか言いますしね!18÷3だから、姦しい×6?」 「……かしましい、かける、ろく」 私の言葉を復唱し、クスクスと小さく笑ってくれるのは三森さん。 七緒さん冷たいしッ、楠森さん反応してくれないから、やっぱり三森さん優しいよぅー。 こういう状況に立たされると、素っ気ない態度を取られてもめげずに事情聴取を頑張っていた千景が思い浮かぶ。千景も意外と苦労してたんだ……なのに私、役立たずだったかなぁ。 とにかく、千景を見習おう。千景みたいに、強気に、元気に…… 「あ、あのですね!」 思い切って声を放てば、私の正面に座っている三森さんがきょとんとして、「は、はい?」と小さく応える。 「あ、えと……施設にはたくさんの女性がいますし、皆さんと相性の良い人とかも見つかるかもしれないですッ。友達とかもそうだし、それから……なんていうか、その」 「恋愛沙汰ですか」 続く言葉に迷っていた私に、ぽつりと続けたのは七緒さんだった。 七緒さんはちらりと私に目を向け、ふっと溜息を吐く。 「……そういう人が見つかるのも、良いこと、じゃないかな?」 恐る恐るそう言うと、七緒さんは「そうですね」と冷たく返した後、お箸を動かす手を止めて視線を上げた。 「でも私、理想が高いんです」 「理想……?例えば?」 「身長は155センチ以下。体重45キロ以下。髪は癖のないストレートで、無駄な肉のついていない華奢な身体。全体的な色素は薄く、瞳は二重で長い睫毛、――そして美しいオーラ」 「……。た、確かに理想、高いかもしれないね」 七緒さんが淡々と告げた条件、全てを満たすことが出来る人など思い当たらなかった。 強いて言えば遼ちゃん辺りが一番近いかもしれないけど、でも美しいオーラっていうのがなぁ。 ――あ。 施設の人じゃないけれど、私は一人だけその条件に当て嵌まりそうな人を思い出していた。 髪は綺麗なストレート、身体も華奢で、くっきり二重の瞳に長い睫毛。難題と言える美しいオーラっていうのと、そして何より全体的な色素が薄いって言う条件を見事に満たしている少女。……だけど、身長は155センチ以上ぐらいあるかもしれないなぁ。 その条件に近そうな少女とは、私の従姉妹である柚里ちゃんっていう女の子だ。不意に思い出された少女の姿に、ほんわりと懐かしい気持ちに浸る。 「とにかく、そういうことは期待してませんから」 私の考えを遮ってきっぱりと告げられた七緒さんの言葉に、「そっかぁ」と残念ながらも相槌を打つ。 そんな私達の会話を聞いていた三森さんと目が合い、私は彼女に向けて言った。 「三森さんも、そういう人、見つかったら嬉しいよね?」 けれど三森さんはふっと困ったような表情を見せ、首を横に振る。 「ごめんなさい。折角なのですが、私……もう、フィアンセがいるんです」 弱い笑みと共に、彼女は左手を差し出していた。薬指には、細い銀色の指輪。 「フィア、ンセ……って、婚約者!?」 初耳だったその言葉に驚きながら聞き返すと、三森さんは表情を和らげて小さく頷く。 そして薬指に嵌められた婚約指輪を愛しげに見つめ、目を細めた。 彼女の様子につられて嬉しくなりながら、 「そうだったんですか。おめでとうございます」 と言葉を掛け、羨ましいなぁなんて思いつつお弁当をぱくつく。 だけどふっと訪れた沈黙の中、私は一つの疑問に捉われた。 ―――どうして婚約者がいるのに、保護する必要があったんだろう。 帰る場所も、自活能力もないと見なされたから三森さんは警察に保護された。 婚約者さんがいるならば、それは明らかに不自然だ。 「……三森さん。その婚約者さんって、今は……どうしているんですか?」 そう問いかけながらも、彼女の反応が少し怖かった。 聞いてはいけないことかもしれない。だけど、聞かずにはいられなかった。 三森さんは私の問いにゆっくりと視線を上げると、ふわりと優しげな笑みを浮かべて言った。 「彼は私のそばにいます。……いつも、そばに」 「……そう、ですか」 満足の行く回答には程遠かった。だけどこれ以上は聞いてはいけない、そんな気がして頷いた。 幸せそうな笑みを弱めて、またお弁当に取り掛かる三森さん。 楠森さんは黙り込んだままじっとして、お弁当にも一切手をつけようとしない。 七緒さんはどこか冷たい表情のまま、黙々と食事を続けている。 「……」 私はこれ以上、彼女達に投げ掛ける話題が見つからず、歯痒い思いをしながらお弁当を食べ進めた。 漂うのは沈黙。重たい空気の中、少しだけ息が詰まって咳き込んだ。 コツン。 大きな窓ガラスを指で小突いて、冷蔵庫のよう冷たい温度を微かに感じる。 夕方十八時。すっかり日も暮れて、外には闇が広がっていた。 交通課や皆に待機してもらっている部屋は一階。 私は署に入ってすぐの階段から二階へ上がり、大きな窓ガラスのそばでこうして闇を眺めている。 吹き抜けになったホールは、日当りの良い所に大きな窓が取り付けられ、天気の良い日は電気がなくても日光が明るく照らす気持ちの良い場所だった。しかしこの時間ともなれば、大きな窓は闇を映し、そして情けない私の顔をぼんやりと映している。 自分の無力さがふつふつと湧きあがる。いつも千景に頼ってばっかりだった私。 こうして一人にされてみれば、いかに私自身の力でここまで来ていないかが明らかになるようで。 もっと強くならなくちゃ。頑張らなくちゃ……。 コツン、コツン。 冷たい空気を震わせるように響いた靴音に振り向いた。 誰かが階段を上がって来る。てっきり蓮池先輩だと思ったけれど、違った。 「……佳乃さん」 館内を照らすのはほんの小さな明かりだけ。このホールの一帯は薄闇と言っても過言ではない。 その薄闇の中から姿を現した女性は、黒衣に身を包んでいた。 「七緒さん……?」 休憩室では気付かなかったけれど、彼女は黒のハイネックに黒の膝丈フレアスカートという黒尽くめの格好をしていた。闇に滲むような輪郭を持って階段を上がってくると、彼女はゆっくりと私に近づき、そして小さく溜息を漏らす。 「あの二人と一緒にいると、私まで変になりそうです」 愚痴るように漏らされた言葉に、思わず返す言葉を失った。 七緒さんは吹き抜けになっている天井を見上げながら、また溜息一つ。 そんな彼女に、少し迷ってから言葉を投げ掛ける。 「楠森さんは何か傷を抱えているみたいだし、移っちゃう感じも、わからなくはないけどね。……でも、三森さんは優しい人じゃない?」 「一見は彼女もまともです。でも、さっき言ってたでしょう?婚約者がいるんだって」 「あ……うん」 「……すぐそばに」 七緒さんがぽつりと漏らす言葉に、僅かな不安に捉われながら「そばに?」と小さく問い返す。 漠然と、三森さんが抱えている問題は見えているような気がしていた。 だけどそれを受け入れたくない部分も否めない。――だってそれは、とても悲しいこと。 「あの人の婚約者は多分、もういない。あの人は幻を見ているんです。語りかけることこそしない、けど、なにもない宙を愛おしげに見つめている。……立派な異常者ですよ」 「……」 七緒さんの推測は、私の推測とほぼ一致するものだった。 もういないはずの婚約者。……三森さんはいないはずの人物が、見えている、なんて。 認めたくない事実に、私は返す言葉も持たず、視線を落とすことしか出来ない。 そんなの、悲しすぎるよ……。 「佳乃さん、一応言っておきますけど、私は異常者ではありませんからね」 沈黙する私に、釘を差すように七緒さんは言う。 七緒さんが、二人に対してどこか差別を含んだ感情を抱いている。 そのこともなんだか悲しくて、やはり私は何も言葉を返せなかった。 七緒さんは構わずに、淡々と言葉を続けた。 「私は変な目で見られたくないんです。弁解ですけど。……私が保護されたのは、正しくは保護ではなく監視をする必要があったから」 「……監視?」 「私は少年院上がりですからね。……他にも理由はあるんでしょう、けど」 あっさりと告げられた言葉に、今までとは別の意味で言葉を失った。 少年院?七緒さんは、犯罪者だったってこと? とてもそうは見えなかった。 冷たい感じはあるけれど、十八歳にしては言葉も態度も落ち着いていてしっかりした女の子だ。 これ以上聞いていいのか、悪いのか。……気にはなるけど。 この沈黙をどうしたら良いかと、逡巡していた時だった。 ドゥン!!! 突然眩しい閃光が窓から差したかと思うと、激しい爆発音が署を揺らした。 一度だけ鳴り響いた轟音に、私と七緒さんは顔を見合わせる。 「今の、何ですか?」 「ば、爆音……かな」 そう言葉にしてから、のんびりしている場合じゃないと気づいて七緒さんの手を取った。 階段を降りようと思った、けれど――ッ ダン、ダンッ!! 吹き抜けの階上から見える署の入り口が激しく叩かれる。 あれはノックとかそんなんじゃない。何者かが、扉を壊してこの署に入ろうとしているんだ。 署の扉はそう頑丈なものじゃない。今から階段を降りていては、扉を壊して押し入った何者かと鉢合わせる可能性が高かった。こんな物騒なことをするんだから、当然見逃してくれるはずもない。 「七緒さん、こっち!」 署の裏に非常階段がある。表の階段は諦めて廊下を行きかけた、その時。 ガシャァァン!! ガラスが割れる派手な音はすぐそばで鳴り響いた。 大きな窓ガラスを割って、投げ込まれた何か―― 「危なぁい!」 言いながら七緒さんの身体を庇うように押し倒したと同時に、カッと目を焼くような鋭い光が館内を照らす。 刹那、ドォォン!!とフロアを揺さぶる轟音に、思わず目を伏せた。 ――少しの静寂、私は小さく息を吸い込み、慌てて身を起こす。 振り返れば、ついさっきまで私達がいた場所が煙に包まれ、パチパチと炎が上がっている様子を見て取れた。そのすぐ後、バァンッ!と大きな音が階下から聞こえた。おそらく正面の扉が突破された音だ。 「急ぎましょう」 七緒さんもすぐに身を起こし、私達は奥へと続く廊下を急ぐ。 まずい。ものすごぉくまずいッ。もし、押し入ってきた敵と遭遇したら、今の私には武器がない。 拳銃は下の階に置いてきてしまっていた。当然七緒さんも武器なんか持ってないだろうしッ…… 「あ、ッ……」 不意に体勢を崩した七緒さんは、顔を顰めて壁に手を付く。 「ど、どうしたの!?」 「ごめんなさい、足にガラスの破片がッ……でも、大丈夫です!」 虚勢を張るように言い放つ七緒さん。見れば点々と血液が落ち、浅い傷ではないことは察する。 だけど今はどうしようもなかった。手当てをしている余裕はない。 「七緒さん、頑張って!」 励ますように告げて、彼女の手を握りまた先を急ぐ。 長い廊下を抜ければ、一つのドアにぶつかった。このドアを開ければ螺旋状の非常階段だ。 扉を開け放った時、ゾワッと嫌な感覚が背筋に走る。 冷たい外の空気が吹きつける中、暗くてよく見えないけれど――敵の数、多いかもしれない。 でも今更引き返すわけにもいかず、七緒さんの手を取ったままで螺旋階段を駆け下りる。 二階から一階に下るだけの短い距離だが、螺旋状になっている階段からは視界が悪い。 間もなく地上、というところまで来て――私達は足を止めざるを得なくなった。 「ッ……」 階段の下には銃を手にした米軍兵士の姿。 ジャキンッと音がして、兵士が私達を殺そうとしている殺気のようなものが伝わってくる。 慌てて引き返そうとした、その時、真上――階段の上からも足音が近づいてくることに気付く。 「囲まれましたね」 七緒さんの言葉に、思わず泣きたくなるのを堪えて唇を噛む。 絶体絶命だ。このままじゃ、私達……死んじゃうよ!! 恐怖と微かな絶望感を感じながら、七緒さんの手を握りしめ、私はきゅっと目を閉じた。 「トウッ!!」 不意に聞こえたのは、女の子の声、だった。 階段の下で構えていた兵士――の、上から、 女の子が降って来た。 ――え!? 女の子は両足で兵士の顔に着地し、兵士を気絶させたところで私達を見上げて言った。 「佳乃ちゃん、お久しぶり」 「……ゆ、柚里ちゃん!?」 その人物に心底驚きながらも、助かった、という現状に安堵感が込み上げる。 思わぬ所から現れた救世主は、私の従姉妹、保科柚里(ホシナ・ユリ)ちゃんだった。 三年ぶりに会う柚里ちゃんは、変わっているような変わっていないような。 美しい白い髪に白い肌、端正な顔立ちに、どこかテンポのずれた語り口。 “アルビノ”というメラニン色素の欠如で、先天的に色素の薄い柚里ちゃんは、その白さも相俟ってか昔から不思議なオーラを持つ女の子だった。だけど三年前に会った時は、もっとお嬢様然とした女の子で…… 今のようにタオルをバンダナ代わりにして頭に巻きつけるようなワイルドな女の子でもなかったし、私のピンチの時に上から降ってくるような女の子でもなかった。 第一、柚里ちゃんは東京市から遠く離れた宮城市に住んでいるはずで、東京市にいること自体が驚くべきことなのだ。 「……今はお久しぶり、の場合じゃなく、……急いで」 淡々と告げるのも柚里ちゃんなりの急かし方。私と七緒さんは頷いて、手を取ったまま階段を駆け下りる。そして気絶した兵士を飛び越して、先を急いだ。 柚里ちゃんは駆けながら短く紡ぐ。 「蓮池課長さんが、パトカーで待ってる……他の二人も、無事」 そんな柚里ちゃんの言葉に安堵したのも束の間、隣を駆けていた七緒さんが少しだけペースを落とす。 七緒さんは足に怪我を負っているのに、それでも無理して走っている。 今が危険な状況ということに変わりはない。 「頑張ろう、あとちょっとだよ!」 「は、いッ……」 七緒さんは苦しげに眉を顰めながらも頷き、私の手を一際強く握り直した。 程なくして、前方にカッと明るい光が点ったかと思えば、光がエンジン音と共に私達に近づいて来る。 すぐに、それが米軍のものではなく、蓮池先輩が運転するパトカーだと察した。 しかし周りから別のエンジン音が聞こえたかと思えば、パァンッ!と空気を割くような銃声が響く。 「佳乃さん!七緒さんッ!」 パトカーの後部座席のドアが開き、三森さんが私達に呼びかける。 助手席に座った楠森さんも、今までとはどこか違う心配そうな表情でこちらを見ていた。 「七緒さん、乗ってッ!」 柚里ちゃんに続いて七緒さんもパトカーに押し込み、そして私もギュウギュウの狭い後部座席に乗り込んだ。バンッ、とドアを閉めた直後、銃声と共にキィンッと鋭い音が響く。おそらく弾丸がパトカーを掠めた音だ。 「皆、シートベルトを締めなさい!」 蓮池先輩はそう言いながら、ギュゥン!とエンジンを唸らせてアクセルを踏み込む。 交通課だから言っているのではなく、シートベルトをしないと危険な運転をするという予告だろう。 後ろの四人は二人で一つのシートベルトを締め、互いに身を寄せ合った。 急加速で発進したパトカーは、署から離れて荒れたコンクリートの道を驀進する。 今まで馴染んだ署を後にし、後ろ髪を引かれるように振り向いた。 その時、カッと照らす幾つものランプに気付いて私は慌てて声を上げる。 「先輩!後ろから追手が……!」 「そう来ると思ったわ。飛ばすわよ」 蓮池先輩は心得たとばかりに短く言って、更にグンッと加速してパトカーを走らせる。 先ほど署を襲ったのは米軍と見て間違いないだろう。とすれば追ってくるのも米軍の車ということだ。 刹那、キィンッと先ほどと同じ金属が掠れるような音がして、僅かに車体が揺らめいた。 「しつこいわねぇッ」 先輩は焦れたように言って、突如グイッと急ハンドルを切り、横道に入り込む。 遠心力に押し付けられて揉みくちゃになりながらも、何とか耐えて後ろを見遣った。 背後からキィィッとブレーキ音が聞こえ、追手の何台かが追跡を諦めたようだ。 しかし後二台か三台、ライトを眩しく放ちながら追いかけてくる。 「皆、しっかり構えて。……跳ぶから」 不意に先輩は低い声でそんなことを言って、ふっと小さく息を吐いた。 と、飛ぶ?車って飛べたっけ? そんなことを思いながらも言われた通りに座席にしがみ付き、衝撃に備える。 パトカーはグンッとスピードを上げて一直線に進んでいく。 その時私はハッとして、慌てて先輩に呼びかけた。 「先輩!!この先は地盤沈下で道路が割れてッ……」 立ち入り禁止になっているはずだ。既に何台かがその場所で事故を起こし、死者を出したこともある。 しかし先輩は「だから行くのよ」と短く言って、更にアクセルを強く踏み込んでいた。 立ち入り禁止の札が立ち、車の進入を阻むために立てられた幾つものコーン。 ゴンッと鈍い音を立てて、コーンを弾き飛ばしながらパトカーは一直線に進んでいく。 速度メーターは私が見たこともないような数値を示していた。 「……しっかり構えなさい!」 先輩は念を押すように言い放つ。 前方に、大きく溝を開けた陥没箇所が見えてきた。 不意に先輩は小さくハンドルを切って、道路が山状に盛り上がった場所に向かって突き進む。 今から先輩が何をするつもりなのか、理解はしたけれど、それが成功するかなんて到底わからない。 恐怖が募ってぎゅっと目を閉じたと同時に、ふわりと身体が浮くような感覚を感じていた。 「ッ!!」 それはほんの一瞬の出来事だ。 だけどまるでスローモーションのように、長く宙に浮いていたような気がしていた。 ガンッッ!! 強い衝撃と共に、車は着地した。 大きな溝をギリギリで越えて――向こう側へと。 「先輩、すごいッ!」 「伊達に交通課の課長じゃないもの」 先輩はふっと安堵したような吐息を漏らした後、そんなふうに冗談めかす。 だけど先輩にとっても、今のはきっと大きな賭けだったはずだ。 彼女が滲ませる汗こそが、それを物語っている。 「小向!追手は?」 そう言われて慌てて振り向くと、先ほどまでしつこく付き纏っていた幾つものランプは見えなかった。 「……い、いません!」 「よし!撒いたわね」 先輩は明るく言って、それから大きく息を吐いた。 「それじゃあ地下施設まで急ぎましょう。……ここからは安全運転でね」 クスッと漏らす先輩の笑みに、私もつられて小さく笑み、「はい!」と一つ頷いた。 そうして、私は慣れ親しんだ渋谷署にも別れを告げた。 だけど悲しくはない。蓮池先輩も、柚里ちゃんも、皆も一緒。 それに、今は地下施設こそが、私の居場所なのだから。 施設についたらきっと私はこう言うのだろう。「ただいま」……と。 渋谷署からさほど距離のない709跡地の地下施設に到着した私―――蓮池式部―――達は小向に連れられて、六人という大所帯で地下施設の内部へと入っていった。 待ち構えていたのは私の可愛い部下である乾ちゃんと、話し相手だったのだろう、志水さんという女性。 この施設に滞在している人たちのデータは、乾ちゃんにまとめてもらった書類で粗方頭に入っている。志水さんの場合は「後頭にアフロ」の一行ですぐに一致したのだった。どんな方かと不思議だったのだけど、確かにあれは……。 乾ちゃんは小向を見てパァッと表情を晴れさせたのも束の間、私を目にした途端表情を強張らせた。 「久しぶりね、乾ちゃん」 「は、はい」 「……元気そうねぇ」 「……げ、元気ッス」 乾ちゃんはビシッと敬礼を決めたまま、僅かに上擦った声でそう答えた。 私は暫しじっと見つめた後、クスッと小さく笑みを漏らす。 「そんなに緊張しなくても大丈夫よ」 「うっす……」 んもぅ。乾ちゃんってば、本当に私のことが苦手なんだから。 「さて、まずは逢坂さんの足の怪我の手当てね。この施設、治療器具はあるのかしら」 そう言うと、乾ちゃんはコクリと頷いた。 「その廊下を進んでから左の廊下に入ったところに。私か伽世ちゃんが案内した方がいいと思います」 「保科柚里……応急処置、得意です」 と保科さんが挙手してくれたので、彼女ともう一人、手が空いていそうな人物を呼んだ。 「保科さんと志水さん、お願いしてもいい?」 言うと、二人は揃って頷き、 「志水伽世、応急処置はイマイチですが道案内なら!」 「保科柚里、保健担当……」 と、しっかり意気込んでくれた。 二人は逢坂さんの左右から肩を貸して、ゆっくりと廊下を歩き出す。逢坂さんはやはり傷が痛んでいるようだが、保健担当を自負する保科さんがいるから大丈夫だろう。 三人を見送り、改めて乾ちゃんに向き直った。 「さて、新しくこの施設で生活してもらう方々をご紹介するわね。足に怪我をしていた子が、逢坂七緒さん。そして、三森優花さんと楠森深香さんよ。」 「宜しくお願いします」 「……」 三森さんは微笑みを湛え小さく頭を下げた。楠森さんは顔を伏せたまま沈黙している。 乾ちゃんは「こちらこそ宜しくお願いしまーす」と軽く返してから、ちらりと廊下の方に目を向ける。 「さっきの、白い髪の子は?」 彼女は小向に紹介してもらった方が良いだろう。 小向を軽く突付くと、小向はようやく気付いた様子で「あ」と声を上げる。 「あの子はね、私の従姉妹の保科柚里ちゃん。今、二十一歳だったかな?あ、私も会うのは三年振りでね」 「へぇ?なんでまた佳乃の従姉妹が?」 「……え?」 乾ちゃんから返される問いに、ぱちくりと不思議そうに瞬く小向。 その後で「はて」と小首を傾げて考え込む。 「そいえば、なんで東京市に来たんだろう……いや、私は柚里ちゃんのこと、救世主としか……」 「は……?」 呆気に取られる千景ちゃんに小向は何か言いたげだったが、その肩に手を置いて言葉を制す。 積もる話はあるけれど、その前に三森さんと楠森さんを休ませなくちゃね。 「皆も疲れていると思うから、お部屋に案内して頂こうかしら」 場を改めるように言うと、千景ちゃんは一つ頷いて「それじゃあ案内します」と先立って歩き出す。 「ねぇ千景。もしかしてお部屋の数、足りないんじゃないの?」 「そのことなら、なんとかなったから。とりあえず空いてる部屋を使ってもらえばいいし」 小向と乾ちゃんはそんな言葉を交わしつつ、二人の女性を気遣いながら廊下の奥へ進んでいく。 この施設内の設備、食堂や備品室などの説明も終え、今夜はそれぞれ一人一部屋で休んでもらうこととなった。 そうして乾ちゃんと小向は、三森さんと楠森さんにそれぞれ一声を掛けてから扉を閉じた。 板についたその様子に内心安堵感を抱いていた。 施設の責任者という役職、乾ちゃんと小向に任せていたけれど…… この調子なら大丈夫そうね。二人は立派にお仕事をこなしてくれている。 その後ホールに戻り、隅のテーブルで私達は互いに起こったことを報告し合った。 署を米軍に攻め落とされたことを話せば、「そうっすか……」と沈痛な面持ちで頷く乾ちゃん。 だけどその表情はすぐ、強張った表情に変わることとなる。「そういうわけだから、私も暫くはこの施設にお世話になるわ」と私の言葉を聞いたからだった。そんなに邪険にしなくても良いのにねぇ。 乾ちゃんからの報告は、施設のアップグレードに関してと、新たに増えた面々に関してのことだった。 最初に調書を取ったという十四人から更に、米軍のMina=Demon-barrowさん、萩原憐さん、可愛川鈴さん、妙花愛惟さん。この四名に関しては小向からも報告を受けていた。そして小向の留守中に増えたのは怪盗FBを名乗る御園秋巴さんと、そしてこの施設の建造者の孫である銀美憂さん。アップグレードを行なったのも銀さんとのこと。 特に問題もないようで安堵した。一つだけ残念な報告だったのは、これも以前に乾ちゃんから報告を受けていたけれど、小向のお姉さんのことか。だけど小向も少しずつ消化しているようだし、今もう触れるべきことではないだろう。 「後は、今後のことね」 向かいに座った小向と乾ちゃんを交互に見ながら、私はそう言った。 なにやら考え込んでいた小向が、ぽむっ、と手を打って、 「部屋割り、改めて考えなくっちゃいけませんね!えへへ、腕が鳴るなぁ」 と楽しげに笑みを深めた。小向らしいというか、何というか。 和やかに部屋割りについて論議をしたいところだったが、私には数点気になることがあった。 「柚里ちゃんは誰と一緒がいいかなぁ」と乾ちゃんに相談している小向を横目に、私は少しの思案に耽る。 気になることとは以下の四点だ。 何故、米軍が警察署を襲ったのか。 銀さんが米国からこの施設までわざわざ届けたアップグレードディスクには、どんな意味があったのか。 そして、保科さんに関してのこと。 しかしこの三点に関しては、いずれも小向や乾ちゃんに話したところで明確な答えが出るとは思えない。 それぞれの問いは、その答えを知っているかもしれない三人に直接聞いた方が早いだろう。 小向と乾ちゃんに話しておくべき事柄と言えば、最後の一点。 私が連れてきた三人の女性――とりわけ、楠森さんのことだろう。 楠森さんは、本来ならばこの施設に連れてくること自体に抵抗があった。 しかし他に彼女を受け入れる場所などない。ならば、なんとかしなければならない問題だ。 「……ここに、楠森さんに関して記された書類があるわ」 私は署から持ち込んだ大きな鞄からファイルを取り出し、その中の一枚の書類を二人の前に置いた。 部屋割り談義を止めて、小向と乾ちゃんは揃ってぱちぱちと瞬く。 そして揃って書類を目で追って、先に怪訝そうに眉を顰めたのは乾ちゃんの方だった。 ワンテンポを遅れて、小向が小さく息を呑む。 二人とも理解しただろう。楠森さんがあんなにも、心を閉ざしている理由が。 「……これ、本当ですか」 乾ちゃんが短く問うた言葉に頷き返す。 ホールという場所柄、誰が聞いているかもわからない。だから敢えて口には出さないけれど。 書類には確かに、こう書いてあるのだ。 『楠森 深香(26) 港区立第一高校元教員 2101年01月10日・同校生徒数名に集団暴行を受ける』 そう、これこそが楠森さんが心を閉ざしている理由。 この出来事は現代の荒んだ教育現場に於いて、悲しいけれどそう珍しいこととは言えなかった。 彼女のような若い教員ならば尚更だ。 けれどやはり、レイプを受けた当人のショックは大きかったようだ。 口もきけなくなるほどに、楠森さんは心を閉ざしてしまった。 彼女の心を開くことが出来るかどうかはわからない。 しかし困ったことに、問題はもう一つ潜んでいる。 「港区立第一高校。二人とも聞いたことがあるはずよ。……つい最近ね」 そう示唆すると、乾ちゃんと小向は顔を見合わせた後、察した様子で小さく頷く。 「遼ちゃんの通ってた高校、ですね」 小向の言葉に「ええ」と頷いてから、少し黙り込む。 三宅遼さん。十七歳の現役高校生ではあるが、彼女は一月初旬から学校に通っていない。 同校に米軍の兵士が押し入った際、正当防衛という形で三宅さんが兵士を殺害した。その日以来、三宅さんは学校に一度も顔を出していないという。この地下施設に避難令が出た01月07日以降、ずっと施設に滞在していた三宅さんは事件の一部始終を知らないということになるだろう。 奇しくも被害を受けた楠森さんは、三宅さんのクラスの担任だった。 加害者である少年たちは三宅さんのクラスメイトだった。 ともなれば、三宅さんにとってもショックは大きいはずだ。 楠森さんにとっても、三宅さんという存在が事件を思い出させるきっかけにもなりかねない。 「……難しいですねぇ、これは」 小向の溜息交じりの言葉に何度目かの頷きを返した後、私は言った。 「二人を会わせないというわけにもいかないでしょう。だからまずは、それぞれに話すことが第一ね。楠森さんも話を聞けない状況というわけではないはずよ。冷静に聞けるかどうかは、わからないけれど」 「遼ちゃんには、私と千景から話しましょうか……」 「そうね。話す方も辛いでしょうけど、お願いするわ。楠森さんには私から話してみるから」 そう告げて、今一度テーブルに置いた書類を見つめた。 生徒達に犯されて、身体中に傷を負って。 彼女の顔に刻まれた幾つもの切り傷もまた、暴行の際につけられたものだろう。 まだ事件が起こってから日は浅い。その分身体や心に負った傷は深い。 だけど誰を責めることも出来ないような事件だった。 加害者である少年達もまた、ある意味では被害者だ。 荒んだ教育現場、人々の心の乱れと共に流行するのは乱れた風潮。 時代の被害者と言っても過言ではないかもしれない、少年達と、若き教員。 どこにも向けることの出来ぬ憤りに駆られても、私はそれを自制するしかないのだ。 受け止めて、消化して、人々が癒えるためにどうするかを考えよう。 警察は乱れた世間を正す職業。乱れた心を正す職業とも、言えるのだから。 「そうねぇ……あたしら兵士も、実を言うと目的は聞かされてないのよね!」 Room06、和葉ちゃんとMinaの部屋を訪ねた私―――乾千景―――と蓮池課長。 目的は蓮池課長の聞き込み調査であり、私はあくまでも付き添いだ。 佳乃は色々あって疲れただろうから先に休ませたわけだけど…… 蓮池課長と施設内デートなんて……ち、千景、頑張るもんッ。 課長はMinaと顔を合わせ、簡単な自己紹介の後で単刀直入に問い掛けた。「米軍の目的は何?」 しかしMinaはあっけらかんとした笑みで答え、蓮池課長もちょっぴり黙り込んでしまう。 「……やはり幹部が指揮する極秘計画ってことなのかしら」 「じゃないの?Um...まぁ一つ言えることは、米国は日本国が大好きってことかしら」 「どういう意味?」 「だってさ、これだけ膨大な数の兵士を日本国に送り込んでるのよ。他の国には一切目もくれずね。欧州にだってそれなりに財力とか残ってるはずなんだし、わざわざこんな弱小国に絞る必要はないと思わない?」 「ええ……それは確かに、米国最大の謎と言えるわね。この国を陥落したところで米軍にとって大きな利沢があるとは思えない。彼らの行動は奇怪すぎるのよ……無人同然の渋谷署に攻め込んだことに関してもね」 「確かにmysteriousよね。あたしもよくわかんないや。下っ端兵士は命令に従って動いてるだけだし、あたしも今じゃ反逆兵だし……」 やっぱりMinaは軍の中でも下っ端だったんだ。 まぁこの性格じゃ……秘密とか普通に漏らしてそうだし……。 蓮池課長は少し考え込んだ後、Minaに向けて一つ礼をし、 「ごめんなさいね、変なことをお聞きして。ともあれ、今後ともどうぞ宜しくお願いします。」 そう言ってにこりと微笑む。 蓮池課長って基本的に悪い人じゃないっていうか、きちんとした人なんだけど…… 私に対しては、どうもこう……いじめっこなのよね。だから苦手だ。 「No problem. こちらこそ、どーぞヨロシク。」 Minaの軽い挨拶を聞いて、「んじゃねぇ」と私も軽い挨拶を投げ掛け、Room06を後にした。 蓮池課長は廊下を歩きながら腕を組んで思案し、「不可解ね」と小さく漏らす。 確かに不可解ではあるけれど、不可解すぎてとても解決の糸口が見える問題とは思えない。 「米国の国家機密……私達が立ち入れる話じゃなさそうっすね。保留にしましょう、保留」 「それもそうね。詮索しすぎるのも良くないわ。……それより乾ちゃん」 「……は、はい」 「私に対してだけ妙に男気のある口調になるのは何故なの?」 「え、そうっすかね?いや、意識はしてないんすけど」 「ほら。“何々ッス”じゃなくて、“何々です”ってちゃんと言いなさい。女の子でしょう」 「う、……こ、心がけます」 蓮池課長、こういうところが厳しいんだよなぁ。 もういいじゃんー、昔から男気のある婦警でしたよぉーだッ。グスン。 そんなことを話しつつ、蓮池課長が次に向かったのは制御室だった。 銀さんの居場所を聞かれて、「制御室だと思います」と答えた。つまり銀さんに用事ということだろう。 制御室のインターフォンを押すと、ポーン、と小さく音がする。 只今呼び出し中。……のままで、二十秒、三十秒。 「いないのかな……?」 試しに制御室の開閉ボタンを押してみたが、やはりロックが掛かっている。 その時不意にザザ、と小さな雑音と共にインターフォンに備えられた画面に十六夜さんの姿が映った。 『……あら、初めましてかしら。……くしゅん』 ま、まだ風邪っぴきだわ十六夜さん。 蓮池課長はインターフォンに向けて会釈し、 「蓮池式部と申します。今日からこの施設にお世話になることになりました。どうぞ宜しくお願いします」 そう丁寧な挨拶をした。だから、蓮池課長は他の人に対する態度と私に対する態度が……もういいけど。 『あぁ……珠十六夜と申しますわ。こちらこそ宜しくお願い致します……』 十六夜さん、なんとなくやつれているような感じだった。 いつもお化粧とかビシッとしてる感じなんだけど、今日はノーメイクかも。なんか新鮮。 「銀美憂さんに用事があるのですが、今、いらっしゃいます?」 『ええ……一先ずお入り下さい』 十六夜さんは一つ頷いてからインターフォンを切り、すぐに制御室の扉がフゥゥン、と開く。 このハイテク感のある音、好きだなぁ。 私と蓮池課長は制御室に足を踏み入れる。 課長もさすがにこの部屋の機械尽くめには感嘆した様子で「凄いわね」と呟いている。 十六夜さんは「少々お待ち下さいね」と言い残して、それから制御室の奥の扉に向かって行った。 そう言えば、アップグレードで制御室の奥に機械室が増えたとか何とか言ってたっけ。 「銀博士、お客様です。蓮池さんと仰る方……」 「もう少し待って貰うように伝えてくれるか。今手が離せない」 そんなやりとりが奥から聞こえ、すぐにひょこりと顔を出す十六夜さんに「聞こえてたわよ」と言って二度手間を省く。 十六夜さんは私達の方に近づくと、ふっと小さく息を零しながら弱く笑んだ。 疲弊が滲んでいる様子だが、大丈夫だろうか。 「蓮池さんと仰いましたわね。警察の方でいらっしゃいますの?」 「ええ。乾と小向の上司に当たります。いつも二人がお世話になっております」 「いえ、お世話になっているのは私の方ですわ」 絵に描いたような見事な社交辞令を交わす二人を眺めながら、大人ってこういうもんかなぁ、とか思ったりなんかして。私も二十四歳なんだから立派な大人っちゃ大人だけど……。 「十六夜さん、無理……してない?なんか見るからにやつれてます、って感じだけど」 やはり心配になって問いかけると、十六夜さんは「大丈夫」と小さく言って、また弱い笑みを向ける。 「確かに少し根を詰めているから……でも、今は少しぐらい無理してでも、進めるべき研究があるの。この奥の機械室、我々科学者にとっては宝庫のようなものなのよ。やはり当時の文明は素晴らしいわ」 「へぇ……私達だけじゃ宝の持ち腐れになるところだったわね」 「銀博士のおじいさまが残して下さった遺産だもの。絶対に役に立てて見せるわ。……と言っても、私の知識では追いつけないものも多くって、銀博士がいらっしゃらないことには話にならなかったかもしれない」 「そうなんだ?銀さんって本当に凄い人なのね。……あ、でもさ、十六夜さんも銀さんも、無理して身体壊したら元も子もないからね」 「……ありがとう」 お。今日の十六夜さん、疲弊しているからかどうかわからないが、妙に素直だ。 弱い笑みで告げられたお礼の言葉に「ん」と頷き返して応える。 その時ようやく、奥から銀さんが姿を見せた。彼女の白衣はオイルやら何やらで汚れていて、顔にも黒っぽい汚れがついていたりして。なんだか意外な姿だけど、これが科学者ってやつか。 「すまん、待たせたな」 「銀美憂博士。もしかしたらと思っていたのですが、やはりあの銀博士でしたか。ご活躍、聞き及んでおります。わたくし、警察の蓮池と申します。施設の鍵を警察管理下から持ち出し、乾達に開錠を指揮しました」 「なるほど、乾達の上司だな。して、私に用事とは?」 蓮池課長の挨拶にも簡単な言葉で返し、銀さんは本題に入りたがっているようだ。 十六夜さんが言っていたように、科学者の宝庫に夢中といったところか。 蓮池課長も察した様子で、「では早速本題ですが」と前置きをして話し始めた。 「銀博士が持ち込んだというアップグレードディスクに関して。聞くところによると、米国の地からわざわざ足を運んで頂いたとのことでしたが……その、施設をアップグレードすることによって、それほどに大きな機能増幅が起こったのでしょうか」 「あぁなるほど、米国から長旅を経て行った手間を考えて、それに見合った成果が出たかという話だな。結論から言えばYESだ」 「詳しくお聞かせ願えますか」 「うむ。アップグレードで何よりも重要だったのは、この奥の機械室なのだ。その他の施設増加に関してはおまけのようなものであり、別段重要なものはない」 「なるほど。機械室には一体何が?」 「一言で言えば、今後の災害に備えるための設備だ。地震や火山噴火といった災害を事前に感知する他、この施設が建造された当時に打ち上げられた小型衛星から、世界各地の気象や地形の情報を捉えることも可能となった。他にも様々な研究機材があるが、これはまぁ重要ではないと言えるだろう」 「……なるほど。今までは衣食住を確保するための最低限の設備だと聞いていましたが、アップグレードによって災害対策施設になった、ということで宜しいですか」 「その通りだ。まだ分析していない機器も多い故、それが全てとは言えないが。何かまた明らかになったことがあれば報告しよう」 ……。 ちょっとだけややこしそうな話だったので、私は聞いている振りをしつつもあんまり聞いていなかった。 災害対策、施設?今までよりもちょっと災害に強くなりました、みたいな感じ? 蓮池課長は納得した様子で幾度か頷いて、改めて銀さんに一礼した。 「貴重なお時間を割いて頂いてありがとうございました。では、今後も宜しくお願い致します」 「こちらこそ。それでは失礼する」 銀さんも、こう、何、十九歳で蓮池課長にこんな態度取れるんだから凄いわよね。 やっぱそれだけの権力者なのかな。……ほんのり羨ましいぞ。 奥の機械室に戻っていった銀さん。 十六夜さんは時折小さくくしゃみを漏らしつつ、制御室の隅で煙草を吸っている。 蓮池課長は「なるほどね」と呟きながら制御室内を見回した後、「じゃあ行きましょうか」と私を促した。 「十六夜さん、無理は禁物よー。それじゃ」 「お邪魔しました。失礼します」 私の砕けた挨拶と蓮池課長の礼儀正しい挨拶に、十六夜さんは顔を上げて会釈した。 そうして私達は制御室を後にし、廊下に出たところで蓮池課長に問い掛ける。 「で、疑問は大体解決出来ました?」 「そうね。後は保科さんに……」 そう蓮池課長が言い掛けた時、廊下のT字路で話題の人物とばったり出くわした。 「呼ばれて、飛び出て……どどん」 保科さん……柚里ちゃんはぽつりとそんなことを言って、ぺこり、と頭を下げる。 さすがは佳乃の従姉妹だ。言っていることが意味不明すぎて実に佳乃の従姉妹っぽい。 柚里ちゃんは頭に巻いていたタオルを首に掛け、益々おやじくさ……いやいや、ワイルドな様相だった。 「あぁ、保科さん、丁度良いところに。……七緒さんの怪我の具合はどうだった?」 蓮池課長の問いに、柚里ちゃんは「ぐ」と言いながら拳を握り、こくりと頷く。 「保科柚里……頑張りました。ガラスの破片が皮膚に刺さっており、慎重な手術の末、取り除くことに成功です。幸い、縫うほどの大きな傷でもなかったので……今は消毒とお薬と、包帯で。人間の自然治癒力にお任せ中……です」 「そう。それは良かった……保科さんには来て早々お世話になってしまったわね」 「いやぁ……役に立てばと思って身につけた看護能力、活用できて、私も嬉しい」 柚里ちゃんはそう言って、またこくりと小さく頷く。 この子は笑顔というものを見せないけれど、なんだか一緒にいて和んでしまうタイプだ。 そういう意味でも佳乃と似てる。 「それとね、保科さん。もう一つ聞きたいことがあって。さっき小向も言っていたのだけど……元々は東京市の人じゃないのよね?なのに何故この危ない東京市にやってきたのかしら?」 「……はい。私は運命の導くままに、はるばる宮城市より見参した次第、です」 「運命……?」 蓮池課長の問いに返した答えもまた、不思議ちゃん発言だった。 柚里ちゃんは至って真面目な表情で、こう続ける。 「私はある人物を探している……多分その人は、この東京市のどこかに、いるはずなのです」 「心当たりはあるの?」 「いえ。東京市にいる、と感じただけですから……まだそれ以上のことはわからない」 「……そう。見つかるといいわね。その方」 蓮池課長は、柚里ちゃんの不思議な言葉にも真剣な様子でそう答えた。 柚里ちゃんの言葉があまりに真剣すぎるから、私も何も言えずにいた。 少しの沈黙の後、蓮池課長はどこか言い辛そうに切り出す。 「保科さん。……小向のご家族のことなのだけど」 「わかって、います。……雪乃ちゃんは亡くなった」 「知っていたの?」 「……はい」 無表情に頷く柚里ちゃんは、ふっと視線をどこかに向けた後、蓮池先輩に近づき、その腕をくい、と引いた。 そして耳元に口を寄せ、何事かを囁く。 私には聞こえないように。……私が聞いちゃいけないことか。 「どうして、それが」 「見えるんです。――でも、言わない」 内容の掴めぬ二人の会話を傍観し、なんだか少しアンニュイな気分になる。 あんまり良い話ではないのだろう。それは二人の表情からも見て取れた。 蓮池先輩はふっと小さく息を吐いた後、気を取り直すようにきっぱりとした口調で言う。 「わかったわ。それじゃあ、保科さんへの用事も終り」 「はい……それでは、おやすみなさい」 柚里ちゃんはぺこりと頭を下げて、てくてくと廊下を歩いていく。 その後ろ姿を眺め、「不思議な子ですね」と呟いた。 「……乾ちゃん」 ぽつりと名を呼ばれ「はい?」と蓮池課長を見れば、いつもより張り詰めたような、それでいて不思議そうな表情で廊下の向こうを眺めていた。ふっと私に目を向けると、課長は弱い笑みを見せる。 「脆いものね。人間も、地球も、とても脆いものだわ……」 「……?」 「だけど、生きていかなくちゃ」 そう言って笑みを深めると、「なんでもない」とごまかすような言葉を付け加え、課長は一足先に歩き出す。 私は頭の中で課長の言葉を反芻しながら、彼女を追いかけた。 「生きていかなくちゃ」 私はそのために、こうして仕事をして、命を繋いでるんじゃないかな。 なんて、そんな次元で物事を考えたことなんてなかったけれど。 死なんてほんの一瞬の出来事だ。生と死は紙一重だって、よくある言葉。 ――生きていかなくちゃ、得られないものがある。 不意にそんなことを突きつけられて、ふと自分の心臓に手を当てた。 ドクン、ドクン。響いている音こそが生きている証明だ。 うん。私はまだ生きていく。生きていかなくちゃ。 |