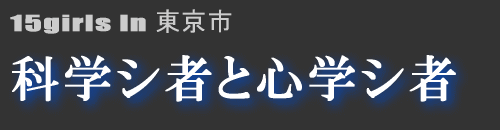
|
長い夢を見ていたような気がする。 意識が覚醒すると同時に、微かな頭痛と眩暈を覚え、一旦目を伏せる。 見慣れぬ天井は一体どこのものだったか。思い出そうとしたけれど、ある時を境に記憶がない。 渋谷の地下施設。目的地であったかの地へと辿り付き、そして……? あの時、精神的にも身体的にも限界を超えていた。おそらく施設に入ってから気を失ってしまったのだろう。 しかしここは施設の入り口でもなければ、廊下でもない――柔らかいベッドの中だ。 誰かが、助けてくれた?私―――銀美憂―――のことを? 「……」 響くような頭痛が幾分引いて、私は今一度目を開けた。 照明を落とした薄暗い屋内。 そして気付けば隣に、私が身を横たえたベッドに寄り添うように身を凭せ掛けている女の姿があった。 眼鏡を掛け、その身体には白衣を羽織っている。理知的な風貌の女はその双眸を伏せ、微かな吐息を漏らしているようだ。私を看取っているうちに眠ってしまったのだろうか。 上体を起こして室内を見渡せば、女とは反対の左側のベッドには誰かが眠っているようだった。 ベッドサイドの時計が示す時刻は、おそらく午前三時。自信がないのは、デジタルの文字が滲んでぼやけた輪郭しか見えないからだ。 私の眼鏡は一体どこに行ったのだろう。視界が悪く、眼鏡すら探せそうにない。 ふっと小さく息を吐いて、再度ベッドに寄りかかっている女へと目を戻す。 まだ頭痛が消えてはくれず、頭も回らない。 頬杖をつく形で眠っている女の姿、暫しぼんやりと見つめていた。 その時不意に、女が杖にしていた腕がカクンと崩れ、バランスを崩しながら女は目を開けた。 「……」 「……」 目が合うと、女はきょとんと瞬いて、そしてすぐに恥ずかしそうに目を逸らした。 「し、銀博士……いつからお目覚めに……?」 繕うように告げられる言葉、思わず少しだけ笑ってから、「ついさっきだ」と答える。 その後でふと疑問を抱き、私は改めて女を見つめた。 「私のことを知っているのか……?」 「勿論ですわ。申し遅れました、私は珠十六夜。科学者の端くれです」 「アカイシ、イザヨイ……そうか、科学者であったか」 女が私の名前を知っていたことに納得し、次はどのような問いを投げ掛ければ良いものかと思案する。 まずは―― 「私の眼鏡を知らぬか?あれがなくては何も出来んからな」 そう言うと、珠博士はまたきょとんとした様子で瞬いてから、ふっと弱い笑みで言った。 「かの銀博士も、私と同じ……眼鏡がないと話にならないなんて」 言って彼女が指し示した先は、私から一メートルの距離もないベッドサイドだった。 科学者と言えど所詮は人間。 当然のことに微笑む珠博士に、私は不思議な感情を抱きながら眼鏡を手に取った。 その後我々は個室を離れ、制御室に向かうことにした。 私の本来の目的を果すためであり、私の任務を終えるため。 「銀博士は何故この施設に?それに、パスワードは存じていらしたのですか?」 深夜の廊下を歩きながら、珠博士が投げ掛けた問い。 「……すぐにわかる。制御室はこの奥か」 はぐらかし、先を急いだ。まずは任務を終える。全てはそれからだ。 珠博士は不思議そうにしながらも「ええ」と頷いて歩を進める。 やがて重厚な扉が見え、ようやく時が来たのだと心のうちで喜びを感じる。そんな私の思いも知らずに、珠博士が先立って制御室へと入っていった。 後に続き室内に足を踏み入れて、ふっと感嘆の吐息を漏らしそうになる。 二十年前に作り上げられた文明。現代のそれに勝るとも劣らぬ素晴らしい設備である。 ……しかし私にはもう、関係のない存在だ。 「素晴らしいでしょう?きっと銀博士ならば、この施設の設備を最大限に引き出せると思いますわ」 「……そうだな。私はそのためにここへやってきた」 ぽつりと答えると、珠博士は不思議そうに私を見て、「そのために?」と問い返す。 肩に掛けた鞄から一枚のCD-ROMを取り出し、読み込み装置を探す。 「珠博士には話しておこう。私がこの施設にやってきた目的を」 CD-ROMのレコーディング装置を見つけ、そのそばへと歩み寄る。 私の後ろをついてきた珠博士は、何も言わずに私の言葉を待っていた。 全てを始めるため――そして全てを終えるために、私は話し始めた。 「私はこのアップグレードディスクを施設に運ぶために、アメリカからこの地へ赴いた。……半分は逃げるためでもあったが、な」 「アップグレード?……逃げるため、ですか?」 珠博士は幾つもの疑問を抱いて小さな声を返す。 私は一つ頷き、振り返って彼女に向き直った。 「米国は現在、日本国に対する敵意を膨れ上がらせている。国を挙げてだ。故に米国に在住している日本人の殆どが囚われ……抗った者は処刑される」 「そんな……」 「事実だ。我が銀家も同等の扱いを受けた。米国にあんなにも貢献したはずの科学者一家すら、国は特別扱いをしなかった。理由は簡単だ。我等は以前のように、国に貢献するだけの知力も開発力も失っていたから……つまり今ではもう必要のない存在だったから。」 「……それじゃあ、銀博士のご家族は」 「捕らえられた。私だけが唯一落ち延びたのだ。祖父の遺言に従うために、米軍の貨物船に密航し、この日本国へ訪れた」 「おじいさまの遺言、ですか……?」 珠博士は私の話す内容にからがらついて来ているといった様子で、眉を潜めながら問い返す。 「そうだ。この施設のアップグレードを行なうことこそが、祖父が残した遺言だった。」 と話した時、珠博士が小さく息を飲むのがわかった。全てを理解したと、そんな様子で。 「つまり、この施設を建造したのは……」 「我が祖父である、銀 憂治(シロガネ・ユウジ)。彼が残した全ての遺産は、この施設ということになるのだ」 「そうだったんですか……」 珠博士は神妙な面持ちで、私が手にしたCD-ROMを見つめていた。 「このディスクこそが私に課せられた最後の使命。……これが終われば、全てが終わる」 呟いてから、ケースからディスクを取り出そうとした。しかし、 「……全て?」 と小さく問い返された声に、思わず手を止めていた。 珠博士に目を向ければ、彼女は私を見つめた後、ふっと目を伏せる。 「貴女には……銀博士には、素晴らしい功績がありますわ。今後の研究を期待している人々だって、きっと世界中にたくさんいるはずです」 「……言うな。私はもう科学者ではないのだ」 「え……?」 あまり深く話すべき事柄ではなかったのに、つい口を衝いて出てしまった。 珠博士は私の言葉に動揺したように、表情を曇らせて問いを重ねた。 「何故ですか?貴女は科学者として素晴らしい方です。それなのに何故、そのようなことを」 「科学者として素晴らしい。その言葉、何度も言われてきたことだ。……科学者としては、素晴らしい」 「……」 「私から科学を取れば何も残らない。私は無力な人間だ。……科学者を辞めた今、もう私には何も残っていないのだ。……良いか、アップグレードを終えれば私はこの施設を後にする。止めるな」 「……お言葉ですが、自虐的にも程があります」 「珠博士にはわかるのか?私から科学を取って、残るものが……」 真っ直ぐに相手を見ることも出来ず、意固地になってばかりで、態度だって非常識なものだろう。 私はこうして生きてきた。何の疑問も抱かずに生きてきた。 私はそれで認められていたのだ。――科学者として。 幼い頃から科学者として育てられ、科学だけが生き甲斐でもあった。 友人などいなかった。友人と遊ぶ暇などがあれば研究に没頭した。 そうして、ここまで生きてきた――それなのに。 米軍に研究所を奪われ、そして愛する人すら失って。 残ったのはCD-ROMが一枚とこの身体一つだけ。 CD-ROMをこの施設に届けることで、最後の使命も終わる。 この抜け殻同然の身体すら、解き放つことが出来る、はずだった。 「……放しませんわ」 珠博士はぽつりと言って、そして不意に背後から私の身体を抱きすくめていた。 パチン、と音を立て、開きかけていたCD-ROMケースが閉じて、私の手から離れゆく。 突然のことに驚きながらも、小さく身を捩って抵抗する。すると彼女は一層強い力で私を抱いた。 「何故、こんなこと……」 「私が教えて差し上げます。科学者ではない貴女を。……だから、行かないで」 「珠、博士……?」 初めて会ったばかりなのに一体何を言い出すのか。 理解出来ぬことばかりで、混乱に陥ってしまう。 私の身体に纏いつく彼女の体温が、益々冷静さを失わせてゆく。 「恋をすれば良いのよ……簡単なこと。――私を求めなさい、美憂」 耳元で囁かれた言葉に、ゾクッと寒気が駆け抜けた。 否、それは寒気に似た何かだ。 今まで経験したこともないような、不思議なもの。 「恋、など……」 珠博士を振りほどこうと、弱く力を加えた。すると呆気なく腕が解かれて、躊躇いながら振り向いた。 細められた鋭い瞳が私を突き刺し、その気迫に飲まれていた。 ドンッ。突如私は両肩を押さえつけられ、壁に背を打つ。 すぐに珠博士はその身体を私に押し付け、密着させた。 「ッ、何をする!」 「言ったでしょう?……私が教えてあげる」 彼女はそう囁いてから、強引に私の唇を奪っていた。 ほんの一瞬、覚悟も何も決めぬうちに唇を交わして、そのまま幾度も啄ばむようなキスを繰り返された。 押さえつけられ、抵抗すら侭ならぬ状態で、強制的な行為は長く続く。 「ンッ……!」 不意に彼女の舌先が、私の口内へするりと滑り込んだ。 貪るような、吸い尽くすような、深い深い口付けだった。 今までに経験したこともない、強引で――どこか扇情的な、行為。 「……、ふッ…ぅ…」 長いキスは、私の脳をぴりぴりと痺れさせるまで続けられた。 ようやく唇を離しても、彼女の甘い味が残っているような錯覚に捉われる。 蛇のような舌が這いまわった感覚が、離れても尚消えない。 珠博士は微かに上気した吐息で舌なめずりをして、唇に付着した唾液を拭った。 その舌が、紅い唇が、目を付いて離れない。 「ね、美憂……私に身を委ねてごらんなさい……とても気持ちの良いことよ」 「……珠、博士……このような、……」 「……熱があるわね、貴女」 「え……?」 彼女の言葉を理解する言語中枢すらも麻痺してしまっているようだった。 額に手を当てられ、冷たい手の感覚がじんわりと馴染む。 心地良さに感け、私は力が抜けてぺたりとその場に座り込んでいた。 ぼんやりと見上げれば、珠博士は紅い唇に笑みを湛え、私を見下ろす。 どこか冷たく、それでいて優しい、矛盾した眼差しだ。 彼女は私が持ってきたアップグレードディスクを機械の上に置き、落ちていた鞄も拾い上げて同じ場所に置いた。そしてしゃがみ込むと、またその身体を私に寄せる。 「アップグレードは後でも出来ますわ。……貴女を止めることは、今しか出来ない。そうでしょう?銀博士」 「……止める……私を……?」 「ええ。貴女にはここにいて欲しい。――科学者ではなくてもね、美憂」 「……」 「今は私も科学者じゃない……貪欲な女よ。……十六夜って呼んで」 彼女の鼻に掛かる声は、私の理性を溶かしていくような甘いものだった。 理知的で聡明そうな珠博士と……蛇のように絡みついて離れぬ妖艶な女、十六夜。 その二面性こそが、彼女を美しく見せていた。 再び寄せられたくちづけは、先ほどよりも穏やかなものだった。それは私が拒まぬ故なのだろうか。 焦らすように唇を食んでは離れ、小さな笑みを浮かべてからまた吸いつく。 彼女の意図は容易に伝わってくるものだ。私を陥れるための、じれったいくちづけ。 幾度か繰り返される度、もどかしい思いが膨れ上がって行く。 「意地が悪い……」 「あら、私のお願いを聞いてくれないからでしょう?」 「……お願い?」 先ほど彼女が何と告げていたか、それを思い起こそうとしたが、痺れた頭では不可能だった。 そんな私に「忘れちゃや」と囁いてから、ヒントを出すように彼女は言った。 「美憂って、呼んでいるのに……私だけなの?」 「……あぁ」 「わかった?」 クスクスと耳元で聞く小さな笑み、そして私の言葉を待つように、彼女はすっと身を離した。 やはり意地が悪い。私が行動に出なければ、彼女はこのまま何もしないつもりだろうか。 「……もっと、そばに……十六夜」 「ふふ。よく出来ました」 彼女は――十六夜は妖艶な笑みを含ませ、またゆっくりと私に顔を近づける。 今度はほんの一瞬の軽いキスの後、その唇は額に寄せられた。 「……風邪、ひいてるんじゃないかしら」 「かもしれない……」 「移っちゃうわね。……今夜はやめにする?」 「え……?」 思わず物欲しげな声を上げてから、ふっと我に返って顔を伏せる。 顔に血液が集まって赤くなるのを感じながらも、同時に本能的な欲求が高まってゆく。 淫佚な宵を示唆する艶かしい笑みが、私の視界でじわりと揺れ、零れ落ちる。 何故ここで涙が溢れるのだろう。私にはわからない。 わからないけど、ただ、この女に身を委ねていたいと、そう思い、私は静かに目を伏せた。 そんな私に十六夜は熱い吐息をふわりと伝え、細い指先を私の唇に触れさせた。 「今夜はキスだけよ。甘いキスだけで、いかせてあげるわ」 「……何処に?」 「……ふふ、なんでもない」 午前四時半。 室内の照明を落とし、光源となるのは蝋燭が一本だけ。 二人の間で揺らめく炎は、ぼんやりと互いの輪郭を浮かび上がらせているだろう。 こんな夜更け。人々が深い眠りについている頃、彼らは活発に動き出す。 「……」 私―――可愛川鈴―――の眼前には、目を伏せて意識を集中させている妙花の姿。 彼女が外すことのない色眼鏡は、炎に照らされても尚闇色を湛え、私が妙花の目元を捉えることは出来なかった。そしてその奥に潜む、禍々しい存在も。 「……中断する」 長い沈黙を破り、私は言った。すると妙花は僅かに顔を上げ、「はい」と小さな声で頷く。 霊媒は、今回もまた失敗という結果に終わった。 妙花の内に潜む霊を呼び出す試みは、これまでに幾度となく行なってきたことだった。 しかし彼女の内から邪悪な念を発するだけで、決してその正体を現さぬ不可解な霊。 この私ですらも手を焼く厄介な霊は、妙花の身体を触媒としてこの世に居座り続けている。 本来の霊媒は、私のような媒介者に乗り移らせるものなのだが、妙花の場合は違っている。第一に霊を霊界から呼び出すのではなく、妙花の内に潜んでいる霊を呼び出すという違い。そして第二に、媒介者は私ではなく妙花だという違い。 このような例は今までに無い、不可解な次元での試みであった。 故に唱えも、どのような呪い(まじない)を持って試みれば良いかすらわからない。 何もかもが手探りの状態での霊媒が続いていた。 「妙花、身体の調子はどうか」 「落ち着いています。鈴様とご一緒している間はずっと」 「そうか。……私が妙花のそばに居ることが逆に、霊魂を押さえつけていることになるのやも知れぬ」 「……なるほど。鈴様に恐れをなしているのかもしれませんね」 妙花はふっと弱い笑みを口元に湛え、それから静かに顔を伏せた。 彼女も辛いことだろう。悪霊によって彼女が奪われたものは数知れない。 「でもこれは……自業自得、なんでしょうか」 ぽつりと漏らされた声に、「何故そう思う?」と問い返せば、妙花は小さくかぶりを振った。 「私にもよくわかりませんけど……私に住み着いている霊が、私を選んでいるのだとしたら」 「怨念を持って妙花の中に潜んでいる可能性か。……確かに否定は出来ない」 「……」 「しかし、心当たりでもあるのか?死者に恨まれるようなことが」 「え?!」 私の言葉に、妙花は驚いたように顔を上げた。そしてすぐに大きく首を左右に振って「ないです!」ときっぱりと否定していた。そこまで断言するのなら疑いの余地もないだろう。 「仕方あるまい。今後も試みて行くとしよう。……では私は自室に戻る」 言って立ち上がった私に、「あっ」と妙花が慌てたような声を上げた。 「どうかしたか?」 「あ、あの……もう少し。……ご一緒して頂けませんか」 「……うむ、良かろう」 懇願の言葉を不思議に思いながらも頷き、室内の照明を灯す。 それから妙花の前で揺らめく蝋燭の炎を吹き消し、霊媒に使用する物品を片付けた。 「……鈴様、私……この時間帯、苦手なんです」 妙花は呟くように言ってから、すっと顔を上げた。天井の明りが照らすことによって色眼鏡の奥に透けて見える妙花の瞳、真っ直ぐに私を見上げてから、すい、と逸らされる。 「何か理由が?」 「……悪い夢を見るんです。明け方の微睡みに」 「なるほど。……頻繁に、か?」 「三日に一度ぐらい……でも、鈴様とご一緒するようになってからは、減ったような気もします」 その言葉に、私はとある可能性が思い当たっていた。 私と一緒になってからは悪夢が減った。となると、それはやはり霊と関係のあることなのかもしれない。 「夢の内容を覚えておるか?」 座り込んでいる妙花と視線を合わせるように屈んで、そう問いかけた。 妙花は視線を落としたまま少しの逡巡を見せ、やがて首を横に振る。 「覚えてません。ただ、とても怖い夢だと言うことが印象に残っていて……」 「……そうか」 「鈴様、私はこれから一体どうなるんでしょう。不安なんです。私、皆を不幸にしてしまう……」 様々な要因の恐怖が募り、妙花は参っているようだった。 確かに彼女が精神的に追い詰められていることは理解出来る。 「仕事を辞めさせられたことも、霊の仕業だと言っていたな」 「はい……私が工場に出たら、原因不明の事故がたくさん起こって……大怪我を負った人までいるんです」 「恐ろしいことだ。……しかし妙花が気に病むことはない」 「でも……」 不安げに顔を伏せる妙花に、私は一寸苦笑した。 妙花の頭に手を当て「顔を上げろ」と小さく告げる。 「悪しきは霊。お前には何の罪も無い。必ず私が、霊を追い出してみせる」 「鈴様……」 「心配無用」 きっぱりと言うと、私を見上げていた妙花はようやく小さな笑みを漏らした。 そして不意にがばっと私に抱き縋り、きゅっと弱く力を加える。 「……私に任せておけば良い」 指先で妙花の黒髪を撫で、安堵させるように告げる。 妙花は私に縋ったまま、ただ静かに沈黙していた。 暫しの間、妙花を落ち着かせるためにじっと時の経過を待った。 そろそろ顔を上げさせようかと思っていた頃だった。 がたん、と微かに床が揺れ、施設内のどこからか大きな音が響き出す。 「何事だ……?」 妙花も顔を上げ、驚いた様子で立ち上った。 我々は一旦顔を見合わせた後、揃って廊下出て辺りを見渡す。 「……?」 一瞬は何事もなかったかのように普段通りの光景が広がっていると思った。 しかし違った。部屋を出て左を見た時、そこには驚くべき光景があったのだ。 「……増えてません?」 「そのようだな」 妙花の言葉に頷き、我々は廊下を歩み出す。 本来は壁があった箇所を通過する。妙花の言った通り増えているのだ――廊下が。 そして廊下の左右には幾つもの扉があり、「十一号室」以降の部屋が増えていた。 ……増えた?何故? 「見事ですわね」 「うむ」 突如背後から聞こえた声に振り向くと、そこには二人の人物の姿があった。 一人は珠十六夜。私には無縁の場、制御室を司る女だと聞いた。 そしてもう一人は初めて見る女だ。眼鏡を掛け白衣を羽織り、銀色の髪を持つ小柄な女である。 「驚いたであろう。我が祖父が残した地下施設をアップグレードさせたのだ」 小柄な女はそう言って、我々のそばで足を止め、ゆるりと左右を見渡した。 そうして満足げに頷くと、私に目を向けて言った。 「感謝しろ。この施設の機能を増幅させたのはこの私、銀美憂だ」 「……」 銀(シロガネ)と名乗った女と珠は我々のそばを通り過ぎ、更に奥へと向かって行く。 何者だ、あの態度の大きい女は一体。 「科学者さん、でしょうか」 「科学者?」 妙花がぽつりと言った言葉を、怪訝に聞き返す。 珠が科学者だという話はちらりと聞いていたが、あの銀とやらまでも科学者というのか。 「馬鹿馬鹿しい。世の中、科学などでは乗り越えられぬ問題が山積みだというのに」 呆れながら言った言葉に、我々より随分前を歩いていた銀がくるりと振り返る。 そしてつかつかと私に歩み寄り、低い視線から見上げながら言う。 「今何と言った?」 「科学など馬鹿馬鹿しいと言ったのだ。それが何か?」 「科学を侮辱する者は許さんぞ」 どうやら私の言葉が気に障ったようだ。 しかし馬鹿馬鹿しいものは馬鹿馬鹿しいのだ。 私は肩を竦め、銀から目を逸らす。 「少なくとも科学者などという下らん職業よりは、我が陰陽師の血統の方が明らかに崇高だ」 「陰陽師?何だそれは。馬鹿馬鹿しいとはこちらの台詞だ。わけもわからぬ血統を謳われても困るな」 「陰陽師を馬鹿にするでない。平安より続く高貴な血統であるぞ!」 「所詮は迷信を信じる輩が生み出した俗業であろう?」 「科学などで破壊を促す輩に言われる筋合いは持たぬぞ」 「何だと!科学は破壊するものではなく生み出すものだ!」 私に向かって身を乗り出す銀を、背後から引き止める珠。 「ふん。同業者に止められるとは無様なものだ」 「私は迷信に縋って偉そうにふんぞるお前とは違うのだ!」 「何を言うか!」 思わず銀に向かって一歩踏み出す私を、妙花が背後から引き止める。 私と銀は互いに睨み合った後、ふい、と目を逸らした。 全く、このような馬鹿の相手はしていられない。 「行くぞ、珠博士。下らぬ言い争いをしている暇はない」 「え、ええ……」 珠を連れて我々に背を向け歩いていく銀を暫し睨んだ後、私は妙花に向き直った。 「癪に障るやつだ。我々も戻るぞ」 「は、はい……」 いけ好かぬやつと顔を合わせてしまい、無性に気分が悪かった。 今宵は――もう朝だが、部屋に戻って眠ることとしよう。 そもそも科学など、この地球には必要がなかったのだ。 科学の所為で自然が怒り、災害が起こった。自ら壊したようなものなのだ。 そんな科学の作った施設に滞在すること自体が私には相応しくないのだろう。 妙花の霊さえ退治できれば、こんな施設はさっさと後にしよう。 人間は自然の中に在るのが一番だ。 「人間は科学によって生かされてきたのだ。そのことばかりはしかと主張せねばなるまい。……科学者を引退した身とは言えども」 腕を組んで不機嫌そうにしながら、銀博士は言った。 「仰る通りです」 隣を歩く私―――珠十六夜―――はそう同意しながらも、繕うように彼女が言った言葉が引っかかる。 科学者を引退した身、か。天下の銀博士が突如引退なんてあってはならないことだ。 何か理由があってのことなのだと察する。後で聞いてみることにしよう。 ひとまずは、この施設に留まってくれるみたいだし……ね。 『十六夜が望むのならば……もう暫く、ここに居てやっても良い』 私のキスでメロメロにされて、彼女は確かにそう告げた。 私が欲しかったのはその一言だ。全ては彼女の――科学技術のため。 銀博士の……否、美憂の言う通り、彼女から科学を取ってしまえば何の変哲もない少女だろう。 私だって、そんな少女が必要なわけではない。 私は科学者としての銀博士が欲しい。彼女の知識と技術を私に教授して貰いたい。 だから私は説得した。強引に理由をつけて、強引に誘惑して。 銀博士も所詮は十九歳の少女、呆気ないものだ。大人のキスで、こうも参ってくれるなんて、ね。 これで彼女は地下施設に留まることになった。 後は……もう一度、彼女を科学者にさせる必要があるわけだけれど。 「この世を統べるものこそが科学……あの女はわかっておらぬな」 先ほどの可愛川さんとの遭遇で、怒り心頭といった様子の彼女。 その様子だけ見れば……彼女を科学者に戻すことは、容易なようにも思えていた。 この子は骨の髄まで科学に染められている。科学者の血が通っている。 故に科学を批難されてあそこまで怒るのだ。そこにあるのは科学者としてのプライドだ。 加えて、アップグレードによって起こったこの地下施設の変化を目にした時の彼女の様子。 玩具を与えられた子どものように嬉々とした瞳を見逃さないわけがない。 銀美憂……今一度、世界的に高名な科学者としての本領を、発揮して貰わなくっちゃ。 「個室の増加に関しても、特に問題はないようですわね。11、12...15号室まで」 話をアップグレードのことに戻し、左右に並ぶ扉を見渡しながら私は言った。 先ほどの情事の後、銀博士が持ち込んだディスクを起動し、プログラムを実行した。 すると施設内のマップが表示され、新たな区域に入れるようになったというわけだ。 「そうだな。この奥には医務室と武器庫、それから倉庫がある」 廊下の角を曲り、彼女の言う三つの部屋へ通じる廊下を歩いて行く。 食堂付近の廊下が不自然な行き止まりだったのは、こういう仕組みがあったわけね。 「さすがは銀博士のおじいさま……元より素晴らしい施設でしたけれど、アップグレードによってまたその素晴らしさを見せ付けられましたわ」 「祖父は我が銀一族の中でも、際立って科学的素質を秘めていた人物だった。……しかし、決して名を残すような研究はしない人だった。こんな施設を造るぐらいだからな」 「でも、この施設のお陰で私達は生き長らえているのですから……やはり偉大な方です」 そう言った私の言葉に、銀博士は深く頷いた。 「その通りなのだ。文明の栄えた当時にこの施設の案を出し、当時の人々には怪訝な目で見られながら建設に着工した。彼の研究は常に未来を見据えたものだった。……私も、その意志を引き継ぎたいと思った」 最後の言葉は零すような響きを持って、尻すぼみなものだった。 そんな様子に言葉を返そうとしたけれど、丁度医務室に足を踏み入れたタイミングだった。 私はふっと言葉を失い、室内の設備に見入ってしまう。 「……凄いわ」 ぽつりと零すと、銀博士も一つ頷き、先立って奥へと進んでいく。 充実した薬品棚、簡易ベッドが三つ、様々な医療用機材も揃っているようだった。 銀博士は真っ直ぐに、部屋の奥で何かを仕切るように掛けられたカーテンを捲った。 「これがプロトタイプか……」 そう呟いている銀博士の背後から覗き込み、そして私はまた言葉を失うこととなる。 そこにあったのは二十年前当時の最先端とも言われていた医療ポット。 ドーム状の強化プラスチックで覆われ、内部には人が身を横たえられるほどのスペースと、細々とした配線が見える。人間の治癒力を引き出しながら、病状に合わせて最適の空間を自動的に作り出す医療器具だった。 私と銀博士は暫し黙り込んだまま、医療ポットを見つめていた。 銀博士は小さな手をポットに伸ばし、透明なプラスチックを撫ぜた。二十年前に、彼女の祖父もまたこの空間にいたのだろうか。そんな想いに捉われているかのように、どこか懐かしげな銀博士の横顔。 「どうして銀博士は、科学者を辞めるなどと仰るのですか。」 「それは……」 「おじいさまの意志を引き継ぐんでしょう?」 一歩後ろから彼女に向けて告げると、銀博士は困惑した表情で私を見遣り、すぐに目を伏せた。 くるりとその場で踵を返し、私の隣を通り過ぎようとする銀博士。 私は横に手を伸ばし、彼女の進行を阻んでから、その手で彼女の肩を抱いた。 「……十六夜」 彼女はぽつりと私の名を呼び、少しの間沈黙した後、そっと私の手に触れた。 「聞かせてくれる?」 美憂は困惑した様子だったが、こくりと頷きを見せた。 そして私の手を解き、医務室の中をゆっくりと歩きながら彼女は話し始めた。 「私には以前、恋人がいた。三つ年上の、素朴な女性。……私は彼女のことが好きだった」 あら……意外。 てっきり私が初めてだとばかり思っていたのに。少し妬けてしまう――なんて、ね。 「彼女はアグリカルチャーの家の娘で……本当に素朴で、柔らかくて、真っ直ぐな人だった。」 私とは正反対の彼女さんね。 だけど美憂らしいような気がする。 美憂には、そういう女性の方が似合うのかもしれない。 「……私は、自分が科学者であることを彼女に話さなかったのだ。アメリカの片田舎、あるのは広大な畑と、そして畑を害すると言われていた我々の研究施設ぐらいのものだった。私と彼女は決まって畑の隅の大樹の下で会っては……他愛もないことを話したり、していた」 「その人は、科学者ではない美憂を認めてくれたということでしょう?」 そう問うと、美憂は小さく頷いて、それからくっと押し黙る。 簡易ベッドに腰を下ろし、美憂は目を伏せたままでゆっくりと言葉を続ける。 「科学者ではない私を認めてくれた、唯一の人、だったのに。……ある日彼女は一枚の新聞を手に、やってきたのだ。普段の温厚な表情ではなく、険しく、それでいて悲しげな顔で」 「……」 「研究が成功し、新聞で大々的に取り扱われた日。……彼女に私が科学者であると、ばれてしまった日」 美憂は弱い言葉で言いながらふと、自らが羽織った白衣を見下ろして小さく笑った。「何故私は今も白衣を着ているのだろう」と呆れたように漏らし、その白衣を脱ごうと手を掛けた。 「話を続けて」 私はそう告げながら美憂に歩み寄り、見上げる視線を感じながら隣に腰を下ろす。 白衣に掛けた手を引いて、温かい手の平をぎゅっと握る。 「……彼女は科学者を毛嫌いした。科学は地球を壊し、破壊を生み出すと言って泣いた。そして私に別れを告げたのだ」 「酷い話ね。科学者はそんな」 「彼女のことを悪く言うな。……私は、彼女のことが好きだった」 私の言葉を切って、美憂は悲しげに言った。 捨てられても尚愛し続ける、か。純粋そうな美憂ならではのエピソードだ。 「だから科学者を辞めるというの?もうその彼女は貴女のそばにはいないんでしょう?」 「でも、私は……」 「科学者を辞めて、どうなるの?」 「……」 難しい年頃ね。好きな人のために科学者を辞めると言いながらも、科学者ではない自分に自信がなくて。 結局全てを失ったような気になって、自暴自棄になっている。 「バカねぇ……こんなに単純なことがわからないの?」 「……?」 呆れた声で告げれば、美憂は憮然とした様子でちらりと私を見上げた。 私はクスリと笑みを漏らして、そっと美憂に身を近づける。 「私がいるでしょ?そんな女、忘れさせてあげる。貴女の全てを愛してあげるわ。科学者である美憂も、ね」 耳元で囁いて、指先で美憂の首筋を軽く撫ぜた。 美憂はくすぐったそうに身を捩りながら、「でも」と抵抗の色を見せた。 「十六夜が欲しいのは、科学者である私だ。……違うか」 核心を指摘され、内心肩を竦めながらも「違うわよ」と反論を返す。 「私が貴女を利用していると言いたいのかしら?」 「……」 「美憂は私のことが嫌い?」 「……まだ会ったばかりだ。確固とした感情など抱けない」 「あら……そう?」 言葉を交わしながら、美憂の首筋に這わせていた指先をするりと滑らせ、彼女の頭を抱いた。 熱っぽい体温が指先にじわりと滲み、その感覚が愛おしい。 顔を近づけ、真っ直ぐに見つめれば、美憂はビクッと身を竦ませて目を逸らす。 ほらね。一度落ちた女は弱い。頭で納得出来なくても、身体が納得してくれるものよ。 「私は好きよ……貴女とのキス」 そう囁いて、強引に唇を奪う。 最初こそ抗えど、触れてしまえばそれ以上美憂が抗うこともない。 私はそのままどさりと彼女を簡易ベッドに押し倒し、上から落とすキスを繰り返す。 美憂は小さく震える指で私の腕を握り、熱っぽい息を漏らしながら顔を背けた。 「……十六夜のキスは身体をおかしくするから、や、だ」 「おかしくなってるの……?どんなふうに?」 「芯が痺れるような、感覚が――……ッ!?」 ビクンッと大きく跳ねた美憂の身体、その深みは、案の定平熱以上の温度を発していた。 ……って、風邪ひいてるんだったわね。 「十六夜に一つ提案、する」 「なぁに?」 「……私だけ熱くなるのは、本当に利用されているような気がして嫌、なのだ」 美憂は掠れた声で言っては、腕を握っていた手を離して私の頭を緩く撫でた。 続く言葉を発すように開かれた唇、きょとんとして言葉を待っていたら――不意に。 美憂から強引に引き寄せられて、拙くも深いキスを奪われた。 目を白黒させながらも、短い舌がくすぐるような感覚が心地良く、私も次第にキスに応えた。 少女からキスされるなんて。……ちょっとだけ刺激的だったわ。 「ン……不意打ち、しないで」 「散々しておいて何を言う」 「……で、さっきの提案って?」 改めて問うと、美憂はどこか気恥ずかしそうに頬を赤らめながらも、悪戯っぽい口調で言った。 「十六夜も熱くなっていれば、今後暫く、科学者としての知識を与えてやっても良いだろう」 「あら、意地悪ね。――でも」 自らの身体に手を這わせ、普段よりも少し早く打つ心音を確かめてから、更に深い場所へと下る。 クスッと笑みを浮かべれば、美憂は不思議そうな顔で。 ――わかってる。私、利用しているだけじゃない。ただ単純に、こんな淫らな行為が好きなだけ。 「もう、熱くなってるわ。……貴女とのキス、本当に好きよ」 そう囁いて美憂の唇を求め、彼女の指を求めていった。 今だけは科学者じゃない。美憂も私もね。 女の子の美憂を見せて。 女の私を、もっと見て。 「……くしゅんッ」 「ケホッ、ゲホ……」 昼下がりの食堂で、私―――乾千景―――は奇妙な光景を目にしていた。 隅の席で食事を取る、十六夜さんと……銀さん、だっけか。 二人はしきりにくしゃみやら咳やらを漏らしつつ、黙々と食事を取っていた。 朝起きて、施設の変化に気付いた私は制御室に赴いたのだが『ごめんなさい、今忙しいのよ』と十六夜さんにあっさりあしらわれ、制御室に入れてすらもらえなかった。「え。いや、何事?」と呆気に取られつつも、後で改めて出直そうと思い部屋に戻った。 そして昼過ぎ、一人で食事を取りに来た食堂で、奇妙な光景を目にしたのだった。 くしゃみと咳がそこまで物珍しいものではないのだが、十六夜さんと銀さんだし、しかも二人揃ってグスンと鼻を啜っている始末。怪訝に立ち竦んでしまうほど、奇妙な光景だった。 私は二人のいるテーブルに近づいて「ちょっといい?」と声を掛ける。揃って顔を上げた二人、どこか熱っぽいその様子にまた言葉を飲んだ後、思い切って十六夜さんの隣に腰を下ろす。 「ねぇ、この施設、なんで部屋増えてるの?っていうか銀さん、体調の方は大丈夫?」 何もかもが飲み込めずに問うと、隣で十六夜さんが「くしゅっ」と小さくくしゃみを漏らしてから言った。 「……風邪、移るわよ」 「…………」 銀さんはともかく、なんで十六夜さんまで風邪ひいてるんだろう。 呆気に取られている私に、銀さんはお粥を掬っていた手を止めてようやく私へと目を向けた。 「昨日は突然のことで驚いただろう。私はこの施設を建造した銀憂治の孫娘の銀美憂と申す者。祖父の遺言に従い、この施設のアップグレードディスクを持ち込み実行した。部屋が増えているのはその結果だ。本来の目的は達成したことになるのだが、出来れば今後も暫く世話になりたい」 「………………え!?孫!?」 淡々と告げられて、暫く言葉が飲み込めず、長い間の後で私は大声で聞き返していた。 この施設を建造した人の孫!?アップグレードディスク!?なにそれ!? 「千景さん。昨日言った通り、銀博士は偉大な方なのよ。ご無礼のないようにね」 十六夜さんに素っ気なく告げられて「え、あ、はい」と慌てて頷く。 無礼のないようにっつっても……こんな若い子を前にして偉大な方って言われてもなぁ。 でも施設をパワーアップさせたのはこの子ってことか。じゃやっぱ凄い人なのか。 「……え、っと、とりあえず、部屋の数が足りなくなりそうだったから今回のグレードアップは助かったわ。銀さんがここに滞在してもらうのも勿論歓迎だし。うん。……あ、私は一応この施設の管理をしている、警官の乾千景。……宜しくね」 「うむ。こちらこそ宜しく頼む」 突然舞い込んだ色んな話に、私の頭は半分スパークしかけているというのに、銀さんは至って冷静だ。 なんか悔しいぞ。こんな年下の子にテンパってる私って……。 「くしゅんッ」 「……ゲフッ」 二人はまた風邪っぴきっぷりを見せながら、黙々とお粥を口にしていく。 だから、なんで二人一緒に風邪ひいてんの……。 「……む」 ふと、銀さんが何かに気付いたように顔を上げ、僅かにその表情を険しくした。彼女の視線の先には食堂の入り口がある。何を見ているのかと振り向いた時、ぽそりと銀さんは小声で漏らす。 「出たなインチキ陰陽師……」 その言葉と、私の目に可愛川さんの姿が映ったのはほぼ同時。 可愛川さんがインチキ!? 「し、銀さん、そういうこと言っちゃだめでしょ、可愛川さんは本物っぽくない?」 「陰陽師などという職業そのものがインチキだ。本物も偽物もなかろう」 「で、でも可愛川さんのお払いって結構効きそうだし……」 「お払い?乾が経験したのか?」 「まぁね……払ってもらったわよ。可愛川さんに霊に憑かれてるって言われた時から怖くてさ」 「……それこそがインチキだ。憑かれているという言葉そのものが嘘だったらどうする?」 「え……」 銀さん、ビシバシと言ってからまた私の後ろに目を移す。 険しくなる銀さんの表情と、そして背後に感じる痛烈なオーラ…… 「楽しそうに話しておるのぅ。誰がインチキだと?」 「え、え、可愛川さん、違うんすよ、これは、いや、その」 しろどもどろになりながら弁解する私とは違い、銀さんはやはりビシバシだった。 「お前のことだ、可愛川鈴。霊魂などという不確かな存在を言い張り、恐怖を煽った上でお払いなどと言って荒稼ぎをしているのだろう。全く、インチキにも程がある」 「なんと無礼な!昨日で懲りたかと思えば、まだ反省すらしていなかったとは。……霊魂を信じぬも自由だが、もしお前が憑かれたとしても絶対に払ってやらぬぞ」 「憑かれるはずもなかろう。霊魂など存在しない。つまり心理的な罠になど掛からんということだ。この世の中には科学的に説明できないことなど存在しない。霊魂などという不確かなものは、人間が作り上げたまやかしに過ぎんのだ」 「浅はかよの。そうやって目に見えるものだけを信じて行くとは、全くもって浅はかだ。祖先の霊魂が嘆いておることだろう」 「死んだ者は泣いたりなどしない。馬鹿げた説教はそのへんにしておけ」 「銀美憂、悲しい娘だな……」 ――と、とんでもない言い争いだ。 確かに科学者と陰陽師は対をなす存在って感じだけど、ここまで対立するとは思わなかった。 可愛川さんはふっと息を吐いてから、ふいっと踵を返し私達のいるテーブルから離れていく。 私は改めて銀さんに目を移し、反省の色はないかと眺めてみたが、 「口論に負けて逃げ帰るとはな」 と、全くもって反省の色、ナシ。 嗚呼、こういう時私は一体どうしたらいいのだろうかっ! 一先ずは様子を見るしかなさそうだ。後は、あの二人を接触させないようにする、だとか。 せめて佳乃がいればなぁ。「喧嘩はよくないですよぅ」とかなんとか言ってくれそうなものだけど。 残念ながら佳乃は今、この施設にいない。 昨日の昼間に蓮池課長に呼び出され、一時的に署に戻っているのだ。 佳乃は上手くやっているだろうか。課長と一緒だから大丈夫だとは思うけど。 「……くしゅん」 「ゲホッ、ケホ」 …………。 で、出来れば早く戻って来てよ、佳乃……。 私、一人でやっていく自信がちょっとだけ欠けてるわよー……。 |