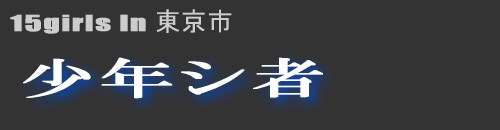
|
「お前のこと、襲いたいっつったらどうする?」 ベッドサイドに置いた煙草に手を伸ばしかけていた女は、その問いを耳にして動きを止めた。 次に向けられるのはギロリと鋭い眼差し。 「何言ってんだ?」 そう言って、バカバカしいと肩を竦めながら女は煙草を手に取った。 女の一挙一動を眺め、暫しの思案。……この女、どうだろうか。 「……うーん」 いまいちだ。ベッドにどっかりと胡座をかいて、腕を組んで、瞑想スタイルで上げる小さな唸り声。考えど求めるものは見つからず、結局あたし―――萩原憐―――は腕を解いてドサリとベッドに倒れこんだ。 この隔離された施設にやってきて、はや三日。ここにいるメンバーとも顔見知りになって、幾人かとは言葉も交わした。都や伽世のようなおめでたい奴等もいれば、命や水散といったカップルちっくな奴等もいる。しかしあたしが本当に求めている存在は、ここにはいないようだった。 「ちくしょう」 小さく歯噛みして身を起こし、隣のベッドに乗り移る。ベッドに座って煙草をふかしていた伊純が、じろりとあたしを見上げて睨みつける。そんな視線でめげるわけもなく、ガスッ、と軽く伊純の背中に蹴りを入れた。 「何だよ……」 伊純は煙を吐き出しながら煙草を灰皿に押し付ける。その手から危ないモンが消えたところで、あたしは後ろから伊純を抱きすくめていた。 「この際お前でいいからさ……お姉さんと楽しいことして遊ぼ?」 「ふざけるな」 折角あたしが甘い声で美味しい誘いをかけてやってんのに、伊純はバッサリ拒絶する。 ぎゅっと伊純に身体を寄せて、その背中に胸を押し付ける。そこいらの男ならこれでイチコロなんだけどな。 「いいじゃん、あたしだって妥協して伊純で良いって言ってんだから」 「妥協するなら別のやつですりゃいーだろ」 「いーずみぃん、そんな酷いこと言わないでさァ」 女の武器、甘えるような上擦った声。これを使えば男だけじゃなく女だってイチコロなはずなのに。 全く興味なしといった様子であたしを軽々と振りほどき、溜息一つを零しては、刺々しい視線を送りながら伊純は言った。 「イチャイチャしたいなら他にもフリーのやつがゴロゴロしてるだろ?お前の趣味に合うかは知らねぇけど」 「それがいないんだって、趣味に合うやつが。大人の女には興味ないしなぁ」 「……、じゃ、何。幼女?」 伊純はあからさまに引いた様子でぽつりと問うが、その言葉には「チッチッチ」と指を横に振る。 「幼女なわけないだろ?」 「……じゃオヤジか」 「んなわけねーだろ、誰がオヤジ趣味だっつーの」 「……え、じゃあ何?」 どこか不思議そうに瞬きながら眉を顰める伊純に軽く凭れ、あたしはどこへともなく視線を向けて言った。 「ここだけの話な。あたし、年下の男が大ッッッッ好きで」 「……ショタコン」 「そう!それ!」 蔑み混じりの伊純の言葉を肯定し、うっとりと目を細める。抱きすくめると華奢でひんやりしてて、でもそれとなく男の香りがするぐらいの少年ってやつが好みど真ん中ってワケ。ちょっと中性的なぐらいがイイんだよな。そんなやつがいたら最高なのにッ―――生憎、この施設に男はいない。 「でな、妥協するとしたら伊純が一番近いんだよ、胸もないし身体も華奢いし」 「……殺されたいのか?」 「うーん、もう、伊純のいけずッ。いいだろぉ?お前みたいなヤツでも、脱げば案外可愛いかもしれな……」 ガスッ、と伊純の裏拳が額にヒットして、あたしは強制的に黙らされた。 ち、ちくしょう。こういう素直じゃないヤツは嫌いだ。 「少年ってのは、お姉さんの言うことはなんでも聞くんだぁぁッ」 「うるせー」 軽々しくあしらわれ、仕方なくあたしは伊純のそばから離れることにした。 だめだ、コイツには期待できない。 他に心当たりも全くないし、この施設にいるメンバーも大したことないよなぁ。 と言いつつも、ここから出て行かない辺りが甘いんだけどな。そりゃこんな美味しい話を手離せるわけないよなぁ。飯は幾らでも食えるし、ベッドまで与えられて、危険もない、と。 食欲も睡眠欲も十分に満たせる場所だ。……だが、やはり不満は残る。 性欲はどこで満たせっつーんだよッッ!! 欲気を紛らわすべく歩む廊下。欲気というよりは退屈と言った方が間違いないか。 夕方十七時、施設内はしんと静まり返っていた。どこか賑やかな場所はないかと彷徨い歩いているうち、T字路に差し掛かる。その時不意に、ポーン、と微かな音が聞こえて音の方に目を向けた。 普段は滅多に通らぬ廊下の奥、確か制御室とやらの扉の前に一人の女が立っていた。――女というよりも、ガキか。ピンク色の髪が目立つそのガキは、初めて目にした人物だ。何気なくガキの様子を眺めていれば、そいつはあたしの視線に気付いたようにこちらに目を向け、そのままで固まった。 随分と遠目なのに、ガキの視線が真っ直ぐにあたしを突き刺すようだ。感情の無い、それなのに貫くような力を持った視線に、あたしも少しだけ動くことを忘れていた。 少ししてガキはあたしから目を逸らし、扉に向けて何事かを告げたようだった。声は言葉という形ではなく、反響した形をなさぬ音としてあたしの耳に届いていた。どこか掠れた、少女の、声。 やがて扉が開き、ガキは制御室の中に姿を消した。あたしはぽつんと廊下に立ったまま、ガキが立っていた場所を見つめ、暫しの間思考が停止したようにそのままでいた。 はっと我に返り、あたしは一体何をしていたんだろうと首を捻る。何てことないガキの姿を目に止めただけだったというのに、頭が少しオカシクなってんじゃないか。 ただ、何かが引っかかっているようなもどかしい思いに捉われていた。 その時不意にどこからか、静寂を破って聞こえてくる女の声が廊下に響いた。 「だからさぁ、あたしが求めてるのは華奢でかぁいい男の子なのッ!」 まるであたしの思いを代弁するような声を開けっ広げに放つのは、食堂から現れた遼だった。 相変わらずセーラー服に身を包んでいる女子高生。……やっぱ、中学生に見えるけどな。 「そんなこと言われてもなぁ」 遼の言葉に困ったように返したのは冴月だ。あたしのご主人様、ってな。 冴月はあたしに気付くと、「憐ちゃんだ」と笑みを浮かべて、こちらへと歩み寄ってきた。 「憐ちゃん、何してるの?」 「何も。暇だったからし、なんか面白れーことないかと思って……」 そう答えながら自然に視線が制御室の方に向く。この退屈な施設の中で、不意に目を引かれた一人のガキが頭を過ぎり、あのガキのことを冴月に聞いてみようかとも思った。けれど、やめた。 あんなガキのこと気にしてるなんて格好悪ぃしな。 「あたし達もめっちゃ暇してるんだよぉ。でもこないだみたいに抜け出すわけにもいかないし……ね、遼。」 「う、うん……まぁね」 遼はどこかぎこちなく頷いた後、視野からあたしを外すかのように軽く顔を背けた。 コイツ、明らかにあたしに敵意を持ってるな。……一体何が気に食わないんだか。 「なぁハルカ」 挑発じみた口調で名を呼べば、遼は鋭い視線をあたしに向ける。 鈍そうな冴月もこの雰囲気には気付いたか、ふっと困ったような顔をして黙り込んでいる。 「カワイイ男の子、いたらいいよなぁ」 「……う」 「同感だぜ。半分こしような?」 ク、と飲み込むように笑ってから、あたしは二人のそばを通り過ぎる。 遼は挑発しすぎると逆上するタイプだろう。関わらない方が賢明だ。 少し早めの飯でも食うかと、食堂に入ろうとした時だった。 あたしの背中に言葉を放ったのは遼。 「お前になんか渡すか。……可愛い男の子は、汚れた女は嫌いに決まってんじゃん」 「……ほぅ」 思わず言い返そうとしたが、かろうじて飲み込んで微かに残る感嘆の声。 あんなガキにキレるわけには―― 「やっぱあたしみたいに、可愛くて若くないと」 「んだとコノヤロウ。あたしが若くないっつーのか?え?」 ……い、けね。 何も考えずに言い返してしまった。 遼は薄い笑みを浮かべてあたしを見据え、余裕じみた言葉を返す。 「当たり前でしょ。自分が若いと思ってんの?バカにも程があるよね、若いって言っていいのは二十歳以下だっての」 「じゃあ何か、若けりゃいいわけか?あぁ?可愛い男の子ってのはな、大人の女に憧れるもんなんだぜ」 「大人のオンナだぁ?益々バカじゃないの?それは都さんとか十六夜さんのことを言うんだよ」 「年齢云々言ってんじゃねーぞ?色気があるかどうかだ。……その点不利だよなぁ遼は。カワイソーに」 「な、……あ、あたしだって脱げばそれなりに胸だってあるし」 「ほぅ。じゃあ脱いで見せろよ今ここで。」 「……はぁ?!」 そんな言い争いの後、共に動きを止めて数秒間。 ……な、なんだこのガキの喧嘩は。クソ、あたしとしたことが。 「だ、誰が脱ぐか、バーカ!」 遼も若干顔を赤くして言い捨て、「行くよ!」と冴月を促しながら早足に廊下を歩いていく。 先ほどからうろたえっぱなしだった冴月はあたしに「ごめんね憐ちゃんっ」と頭を下げてから、慌てて遼の後を追っていった。 ようやく訪れた静寂の中、一人で小さく溜息を吐く。 そもそも可愛い男の子なんて居ないっつーの。……アホらし。 トンッ。 軽やかにビルの屋上に降り立って、指先で風を切りながら月を見上げる。 今宵は盈月、現れるならこんな明るい夜でしょう。 「怪盗FB……」 宿敵である人物の名を呟いて、私―――伴都―――は静かに息を吸い込んだ。 『私の狙いは一つだけ――貴女ですよ、HAPPY』 和葉ちゃんとのデート中に現れて、馬鹿げた台詞を吐いた怪盗FB。 しかし私は、それを馬鹿げた台詞だと言うことは出来ないのだ。 だって、私、本当に奪われちゃったんだもん。……唇を。 あれ以来、私の胸の奥底でふつふつと煮え上がる感情。 それは復讐という名の憎悪。乙女の唇は高いのよッ! しかし同時に、私の唇を奪うなどという暴挙に出たFBという人物への好奇心が膨れ上がる。 私を、奪いたい、なんて。……今考えれば、結構衝撃発言なんじゃなーい? 楽しみなような、あんまり会いたくないような。 複雑な感情を抱いて、辺りを見渡す高いビルの屋上に立っている私。 知っているんでしょう?聞こえているんでしょう、FB? 「さぁ、来なさいFB。――貴方が求めている怪盗HAPPYは、ここにいるわ」 ぽつりと囁いた声の後、静寂。 強い風が吹き、空気を薙いで、流れていく。 背後の闇が、微かに揺らめいたと同時に、ドン、と背を押すような気迫に息を詰めた。 「怪盗FB、参上。レディをお待たせするのは、私の性に合いませんからね。」 「……来たわね」 ゆっくりと振り向けば、そこには、白き衣装に身を包んだFBの姿がある。 こうして見れば薄暗い夜の中で、灰色に濁って見えるけれど――これが白き人の正体なんだ。 FBは目深に被ったシルクハットをクッと上げ、笑みを湛える口元を覗かせた。 「ごきげんよう、HAPPY。またお会い出来て光栄です」 「なぁにが光栄よ。紳士ぶってるくせに、これはないんじゃない?」 そう言って指先で弾いたのは、小型の追跡機だった。いつの間にか――おそらく先日接触した時、私の服に付着させたのだろう。追跡機の存在に気付いたのは施設に戻ってからだった。姑息なことをしてくれるものだ。だからこの追跡機を利用して、FBを呼び出すことにした。 「申し訳ありません。こうでもしなければ、貴女を見失ってしまいそうだった。HAPPYとの別れは、永久の悲しみです。私はそれに耐えられそうにもなかったのですよ」 「……言ってくれるわね」 返す言葉もない。軽く肩を竦めてみせれば、FBは静かに歩を進め、私の方へと近づいた。 十メートルほどの距離を置いて対峙し、睨み合う。――と言っても、私から見えるのはFBの口元だけだ。 HAPPYだって普段は皮のつなぎとゴーグルで顔を隠しているわけだけど、今夜は素顔のままでここに赴いた。FBは既にHAPPYの正体が伴都だと知ってるんだから、隠す必要もない。 「今宵は、何かご用があったのですか?」 不敵な笑みの消えぬ口元が紡ぐ言葉に、私は小さく頷いた。 そしてビシッとFBに指を突きつけて、言い放つ。 「単刀直入に言わせてもらうわ!……貴方は何者なの?怪盗FB!」 するとFBは笑みを消し、沈黙を置いた後で小さく言った。 「怪盗HAPPYに焦がれるしがない怪盗です。……それ以上のことが、知りたいですか?」 「焦がれてくれるのは嬉しいけどね。FBは私の正体を知っている、でも私は何も知らない。不公平だと思わない?……私だって知りたいのよ、貴方のことが。」 怪盗FBという存在そのものが、謎に包まれている。 決して名高い怪盗ではない。私ですら聞いたことのない名前だった。 しかしFBの手口や技術を――そう、あの時私の唇を奪うなどという芸当を思えば、只者ではないことは推して知れる。そんなFBに興味を抱かずにはいられないのだ。 男なの?女なの?年齢は?名前は?……知ってどうなるものでもないのに、知りたくて仕方がない。 「HAPPY。貴女がこの怪盗FBに興味を抱いてくれることが、私はとても嬉しいのです。」 FBは静かな口調で言い、指先をシルクハットのつばに置いた。 「貴女にならば、全てを知られても構わない」 「……じゃあ見せて頂戴。その素顔を。」 そう言った私の言葉に応えるように――FBはシルクハットを空へ放った。 その瞬間は瞬きすらも忘れて、私はFBの姿に見入っていた。 露わになったFBの素顔。それが、意外だった、から。 「……男の子……?」 ぽつりと呟くと、FBははにかむように弱く微笑んで、目を伏せた。 綺麗な顔をした少年。それがFBの素顔だった。 柔らかそうな髪が揺れ、彼は指先でその髪をかきあげた。 白いスーツに身を包んだ華奢な身体、どこか幼気な雰囲気の残る顔立ち。 中性的な声にも合点がいく。 「初めましてHAPPY……いや、都さん。これが僕の、怪盗FBの素顔です。」 「……あ、……うん」 「幻滅しましたか?僕、まだ、十五歳だから……子どもだってバカにされるかと思って、怖かった……」 「げ、幻滅してないッ!可愛いわね、君……」 まだどこか現実感のない目の前の情景に、言葉すらも勝手に零れた。 少年は気恥ずかしそうに微笑んで、「照れます」と頬を掻く。 そんな仕草すら可愛くて、ドキッとしてしまう。 こないだ私の唇を奪ったのは、この子だったの?……本当に? たった十五歳の男の子が、私に憧れてくれて、あんなことしちゃったんだ……? なんか、許せちゃいそう、っていうか私既に、許してる。 「もっと近づいてもいい、ですか?……都さんの綺麗なお顔、もっと近くで見てもいいですか?」 「……ん、いいわよ。遠慮しないで」 FBはおずおずと私の方に歩み寄り、ほんの一メートルほどの距離で私を見つめては、ふっと恥ずかしそうに目を逸らす。背は結構、高いんだ。少し見上げてFBの頬に手を伸ばせば、彼は赤くなってビクッと身体を震わせた。そんな一挙一動が、本ッッ当に可愛くて。 「君……保護者とか、いるの?」 思わずそんな問いをかければ、FBは不思議そうに瞬いてから、どこか悲しげに首を横に振った。 「……お父さんもお母さんも、少し前に亡くなって……今は一人ぼっちなんです」 「それじゃあッ……あの、……私のところ、いや、私達のところに来ない?」 誘いの言葉に、FBは驚いたように私を見つめ「いいんですか?」と問い返す。 そんな期待の篭った眼差し向けられたら、オッケーに決まってるじゃないッッ! 「いいわよ!私が面倒見てあげるッ」 「HAPPY……あ、ありがとう……」 ふわりと零れる儚げな微笑に、きゅん、と胸がときめいた。 やだ、私ってば十歳も下の男の子にこんな気持ちになるなんて。 ……でも、こういうのもアリよね?だってこの子、どうしようもなく可愛いんだもん。 その仕草、その照れ笑い、その言葉―― 反則。 母性本能をくすぐって止まぬ少年を、私は地下施設に連れ帰ることにしたのだった。 しかし私は先の予測にまで考えが至っていなかった。 普通に考えればわかることだったのかもしれない。 もしも女だらけの施設に、こんなに可愛い男の子が放り込まれたら……と。 「御園秋巴(ミソノ・アキト)君……十五歳か。女ばっかりの施設だけど大丈夫?」 事情聴取用の椅子にちょこんと座って、千景ちゃんの事情聴取に応えていく男の子。 千景ちゃんの問いかけに、アキトくんは「はい、大丈夫です」と小さく頷いて見せた。 いやーんッ。超、可愛いッッッ!! また新メンバーが増えるという話を聞きつけて、あたし―――三宅遼―――はダッシュでホールへとやってきた。別に女が一人二人増えたところで騒ぐことでもないんだけど、今回は違った。 新メンバーは最高に可愛い男の子なんだもんッ!嗚呼神様、あたしの願いを叶えてくれてありがとう! そんなわけで早速事情聴取の様子を眺めていたわけだけど、邪魔者が現れたんだよなぁ。 「……アキトかぁ。フフ、お姉さんが可愛がってあげるぅ」 口調まで変えて笑顔でアキト君に語りかけるのは、ついさっき廊下で対立したばっかりの憐だった。 あの時は、居もしない男の子の話でぶつかるなんて自分でもバカバカしかったんだけど、まさか現実になるなんて。……ヤバァーイッ! 「あ、あの、えと、宜しくお願いします」 アキト君は緊張した様子で取り囲んでいる面々を見渡し、ぺこりと頭を下げる。 「あたし、三宅遼。気軽にハルカって呼んでね。歳も近いから仲良く出来ると思うの。宜しくね?」 「ガキは放っといて、あたしと遊ぼうな?あたしは萩原憐。覚えろよ、アキト」 「ちょっと、何勝手に呼び捨てしてんの?ごめんねアキ君、こんな下品な女無視してね」 「お前こそアキ君って何だよ、ったく」 ずずいっと争うようにアキ君に近づいて、憐と睨みあう。 そんなあたしたちの頭をパコパコッと背後から叩いたのは、アキ君を連れてきた都さんだった。 「アキトはもう想い人がいるんだから、無様な争いはやめなさい」 「お、想い人!?」 「なんだと!?」 突如告げられた衝撃的な言葉に、あたしと憐はまたアキ君に詰め寄っていた。 アキ君はきょとんとしてあたし達と都さんを見上げては、ふっと頬を赤くして首を横に振る。 「そ、その、でも、……いや、僕、恋人とかがいるわけじゃないので」 「ならいいじゃんッ」 「ま、恋人が居ても奪ってやるけどな?」 さっきから憐がうるさいけど、アキ君は本当に本当に可愛くてッ。 あぁどうしよう、今からアキ君と恋に落ちて、久々に純愛なんかしちゃったりして! でもあたし二個上だし、ちょっと年上ぶって色々教えてあげるのもいいかなぁ。 「……アキト」 都さんはふっと小さく笑みを浮かべると、アキ君の耳元に唇を近づけ、何事かを囁いた。 都さんの言葉を聞いた途端、アキ君は頬を赤くして顔を伏せる。 な、何よ、何囁いたのー!? 都さんは「アキトに変なことしちゃだめよ?」と言い残し、ご機嫌に鼻歌交じりでホールを後にした。 むむ、都さんも密かにライバルだったりするわけ?許せなぁい。 一瞬にして築かれたアキ君を取り巻く四角関係を目の当たりにして、千景ちゃんは溜息混じりに言った。 「あんたら……お願いだから間違ったこと、しないでね……この子を穢しちゃだめよ」 そうして事情聴取のノートをまとめ、「くれぐれもね?」と釘を刺しながら千景ちゃんもホールから去っていく。 残るのは、あたしとアキ君と、邪魔者である憐の三人だ。 アキ君は椅子から立ち上がると、ゆるりとホール内を見回してから小首を傾げる。いやん、些細な仕草すら超可愛いんですけどー。 「ね、ね、アキ君、あたしが施設の中案内してあげよっか?」 「あ、そうして頂けると嬉しいです」 アキ君は小さく頷きながらふわりと微笑む。その笑みにまたドキッとしてしまうあたしがいるわけで。 「じゃあ行こう!二人っきりで」 「なわけないだろ?アキトはあたしと一緒に行くんだよな?」 アキ君を促して行きかけるあたしの肩を憐がガシッと掴み、あたしとアキ君に視線を送る。 んなわけないに決まってんじゃん、バッカじゃないの? 「あ、あの、皆で一緒に行きましょう。……だめ、ですか?」 アキ君は憐に気遣ったのか、そんな提案をした。んもう、アキ君ってば優しいんだからッ。 でも、そんな子犬みたいな目ぇされちゃったらだめなんて言えないッ。 「仕方ないなぁ。じゃ行こッ」 あたしはアキ君の右腕にさりげなく抱きついて、改めてアキ君を促した。 「両手に花か。まぁ片方は蕾もイイトコだし、このまま咲きそうにもない花だけど」 気付けば、憐がアキ君の左腕を抱いてあたしに嫌味な視線を向けている。 「そ、それなら片方はもう枯れかけた花だよねぇ。アキ君はあたしみたいに、可憐な蕾でもいいでしょぉ?」 「それよりも、熟した花の方がいいに決まってるよなぁ?」 憐ってばアキ君の腕に胸押し付けたりしてやがるぅ……。 当のアキ君はきょとんとしてあたし達を交互に見ると、 「僕は、どちらも綺麗なお花だと思います。」 と、笑みを浮かべて言ってくれる。半分お世辞を言わされてるアキ君も健気で素敵ッ! そんな感じで、アキ君の左右にあたしと憐という形で落ち着き、三人で歩いていく。向かう先は食堂、その途中途中で衣服室や制御室なんかも教えていった。 「女性ばかりで共同生活なんて賑やかで楽しいでしょう?……僕、混じっても良かったのかなぁ」 道中、アキ君がぽつりと呟いた言葉に、あたしと憐はほぼ同時に言葉を返す。 「良いに決まってるでしょ」 「良いんだよ、お前は」 今回ばかりは珍しく意見が合った。 当然だ、皆きっとアキ君を歓迎してくれるし、何よりあたしが大歓迎だし。 即答にも似た二人の答えに、アキ君はふっと嬉しそうに微笑んだ。 「ありがとうございます……遼さんに、憐さん。二人がいてくれて、僕、本当に嬉しいです」 「そんな改まって言われると照れちゃうよ、やん、もうアキ君ってば」 「お前みたいな男は貴重だからな?……拒絶するわけないだろ?」 相変わらず憐が邪魔だけど、なんだかほのぼのした雰囲気になって、あたしはぎゅってアキ君の腕に抱きついた。アキ君は少しだけくすぐったそうにして、あたしの顔を見下ろす。背ぇ高いアキ君の目、真っ直ぐに見上げてると、なんだかドキドキする。 本当、可愛いし格好良いし……惚れちゃいそうだよ、アキ君。 「遼、お前くっつきす……」 「あ、遼!ちょっといいー?」 憐が文句を言い掛けた、その時だった。背後から聞こえた声に振り向けば、廊下を駆けて来る千景ちゃんの姿。千景ちゃんはあたしたちのところまでやって来ると、 「遼にちょっと用事があってね。保護者云々のこと。大したことじゃないんだけど、来てくれる?」 と、あたしにそんな言葉を告げる。……千景ちゃんタイミング悪すぎだよ。 「仕方ないなぁ……すぐ戻るから待っててね?」 あたしはアキ君にそう言って、千景ちゃんと一緒に歩き出した。 「えっとね、遼のご両親に遼のことを保護するっていう申請を……」 千景ちゃんが何か言ってるけど、あたしはそんな言葉も耳に入らずに、二人っきりにしてしまうアキ君と憐の姿を気にかけて何度も振り返る。そんなあたしに呆れたように、千景ちゃんは言ったのだった。 「遼も男の前じゃ、ちゃんと乙女になれるのね」 「早くアキ君のところに帰してよぅッ!」 廊下ですれ違った遼さんは、しきりとそんな言葉を繰り返していた。 「わぁってるってば」 と千景さんが宥めるように言い、尚も騒がしく二人は歩いていく。 そんな姿に思わず振り返り、私―――悠祈水散―――と命さんは呆気に取られているのだった。 「アキト君ブームみたいね……」 「そのようですね……」 命さんの言葉に頷いて、噂のアキトさんとはどのような人物なのかと想像する。 実は部屋を出てすぐに鉢合わせた都さんも、同じ名前を出していたのだ。「アキトっていう可愛い男の子が来たから、二人も仲良くしてあげてね」と嬉しそうに話していた。 立て続けにアキトさんという名前を耳にすれば、その人物がブームと考えるのも自然だろう。 狭い施設だから、そのうち顔を合わせることになると思うけれど……少し楽しみだ。 「ま、男が珍しくてはしゃいでるだけだと思うけどね」 命さんは素っ気なく言いながら、ひょい、と軽く肩を竦めた。その様子に苦笑して「どうなんでしょう」と言葉を濁す。命さんって色んな面で冷めている人だなと改めて思う。けれど時々情熱的で、そのギャップにドキッとしてしまう。 今でも少しだけ不思議な気持ちで命さんのそばにいる私。もう一週間以上が経ったのに、未だに現実感がないのは何故だろう。恋だとかそんなのじゃなくて、ただそばにいるこの関係が、嬉しいのだけど慣れなくて。 「水散さんは、アキト君に揺れたりしたら許さないよ?」 「……え?」 命さんの言葉を聞き逃して、小さく聞き返した。彼女はクスッと笑ってから、長い髪を耳に掛け、私より一歩前に出てそそくさと歩いていく。「なんでもない」とごまかされた言葉、腑に落ちなくて余計気になってしまう。 彼女の隣に戻ろうと慌てて追いかけると、命さんはまた私より一歩先に進むようにピョンッと足を踏み出して、それから不意にくるりと振り向き、クスクスと笑んだ。遊ばれているような気がして少し頬を膨らませてみれば、命さんは笑みを深めて言った。 「隣がいい?」 「……です」 「どして?」 「どうしてって……うぅ。後ろより隣の方が、近い気がしますッ」 「水散さん、あたしに近い方がいいんだ?」 そう問われた時にようやく嵌められたと気づきながらも、これは命さんの常套手段。 頑なに否定すればきっと彼女は余計に面白がるだろうし、いつもみたいに素直に肯定すれば―― 「……近い方がいい、です」 「そっか。……うん、あたしも近い方がいい」 と、嬉しそうに目を細め、素直に喜んでくれる。 命さんがすっと手を差し伸べ、私はそっと手を重ねる。きゅっと優しく握られて、また二人で歩いていく。 こんな行為、恋人同士がするものだと思っていた。だけど今は恋人でもないのに、こうして戯れ合って、こうして手を繋いで歩く。そんな関係が不思議でくすぐったくて、でもやっぱり嬉しくて。 命さんはどうしてこんなに優しいんだろう。……でも、反対のことも考えてしまう。 どうして命さんは、これ以上求めないんだろう。 軽いハグも、頬や額に落とすキスも、彼女にとっては友愛の印なのかなぁ。 私は彼女の行為の一つ一つで、ドキドキしてしまうのに。 命さんはいつも冷静で、いつも悪戯っぽい笑みを浮かべる。……ちょっとだけ意地悪だ。 そんなこんなで、嬉しいのに複雑な道中を経て、私達は夜の食堂に辿り着いた。 食堂の照明は、時間によって自動的に切り替わっているらしい。朝から夜の二十二時ぐらいまでは明々と点いているのだけど、それ以降はキッチンとそれに近いテーブルの辺りが照らされているだけで、奥の方の照明は消えてしまう節電システムだ。 今は二十二時を少し回った頃だろうか。命さんが「おやつ食べたーい」と突然言い出したので、テイクアウトでおやつを調達しに来たというわけで。この時間にもなれば食堂には誰もいないと思っていたし、食堂内に足を踏み入れた時にも誰もいないと思い込んでいた。 「……ん?」 食品製造機に向かいながら、命さんは何かに気付いたように顔を上げ、ふっと口元に笑みを湛えた。 すぐに彼女は何事もなかったかのような素振りで食品製造機の操作をするが、ちらりと視線だけを私に向け、小声で言う。 「刺激的よねぇ……暗い食堂の片隅で、こっそり逢引してるなんて」 その言葉の意味がわからず、「片隅?」と小声で聞き返すと、命さんは潜めた声で続けた。 「人の気配がする。……二人、ね。気付かない振りしてあげようか」 「あ、……はいッ」 ようやく意味を理解して、私は小さく頷いた。 てっきり誰もいないと思っていたのに――こんなところで、逢引? 確かに命さんの言う通り、刺激的なのかもしれない。というか、私達邪魔しちゃったのかな。 ピー。と音がして食器製造気の戸が開けば、命さんは手際よく出来上がったクッキーをお皿に乗せ、紅茶をボトルに詰めてお盆にまとめた。私は暗がりに潜む二人の存在が気になってしまって、彼女の手伝いを怠ってしまう。命さんはそのことを気に止めるでもなく「行こうか」と促して食堂の出入り口へと歩いて行った。 私は命さんのすぐ後を追いながらも、思わず暗がりの方にちらりと目を向けた。確かに隅っこなら命さんに敏感じゃない限り気付かないだろうし……でもこんなところで潜まなくても。なんだかドキドキしてしまう。 食堂を出て少し歩いてから、命さんはふっと気を抜くように吐息を漏らす。 「あーあ、ヤバいもの見ちゃった。……あたしね、伊達に猫目じゃないんだよ」 「見ちゃった……?」 命さんは小さく笑みながら、お盆から片手を外して元々切れ長な瞳をピッと上げて見せた。 確かに彼女の目の造形は、猫の目の形に似ている。 「闇で目が利くの。暗いとことかね、結構見えちゃうわけ」 「そんな特技が……って、それじゃさっきの二人、見えたんですか?」 驚きながら問い掛けると、命さんは「ふふん」と楽しげに笑みながら頷いた。 あ、あんまり立ち入っちゃいけないことだと思うけれど、その、好奇心も……。 「一人は多分、噂のアキト君ね。結構背の高い男の子かな?」 「え……じゃあ、アキトさんともう一人が逢引です?」 「うんうん。逢引なのは間違いないでしょー。じゃなきゃあんなにくっつかないよね」 あんなにと言われても、私は実際に目にしたわけじゃないからわからない。 けれどあんなにくっつかない、ということは、かなりくっついていた、ということになるのだろうか。 命さんはクスクスと笑みを含ませて「もう一人も知りたい?」と私を見遣る。 そ、そんなこと聞かれても、どう答えれば良いかッ…… 「もう一人はね、憐ちゃ――」 命さんが衝撃のレポートを告げようとした、しかし、私は彼女が告げた名前以上に別の物音に驚かされていた。命さんもふっと言葉を止めて、辺りを見回す。 食堂から個室へ戻る途中には、事情聴取を行なった広いホールを通りかかることになる。ホールには外へと続く通路があり、そして音が聞こえるのはその通路の向こうからだった。 ゴゴゴゴ、と響くような物音は、以前にも聞いたことがある。 頑丈で大きな施設の扉が開閉する音だった。 「こんな時間に誰が……?」 命さんの言葉の後、響く音が止み、少しの静寂。この場で待っていれば、入ってきた人物と顔を合わせることになるはずだった。しかし聞こえたのは足音ではなく、どさりと何かが――おそらく人間が倒れる音。 命さんは手にしていたお盆を事情聴取用のテーブルに置くと、出入り口の方へ駆ける。私もその後を追い、通路に差し掛かったところで倒れている人物が目に映る。 「……!?」 小さく息を飲んだのは命さん。私もその光景が、ありえない光景だということだけは理解できた。 扉から入ってすぐのところで倒れ伏せた人物は――この施設の人間ではなかったからだ。 「だ、大丈夫ですか!?」 私は人物に駆け寄り、うつ伏せに倒れた身体に触れた。 人物は銀色の髪を持つ、小柄な女性だった。女性は私に気付いて僅かに顔を上げたが、すぐに身体から力が抜けるようにがくりと脱力する。眼鏡を掛けていたようだが、倒れた衝撃で床に落ちてしまったらしい。 私はそっと女性を抱いて楽なようにと仰向けに寝かせた。彼女が羽織っているのは白衣だ。それが医者のものか科学者のものかという問題ではなく、この極寒の時期に防寒服と呼べるものが白衣一枚だけなのだ。白衣の下に着込んでいるのも、そう厚い感じではないハイネックとストレートパンツ。女性の身体には雪の粉がついているし、身体自体も冷え切っているようだった。 女性は薄っすらと目を開けて、掠れた声を上げた。 「……ここが、……渋谷の、地下施設か……」 問いかけにも独り言にも近い言葉だった。しかし私はその言葉に答えるよりもすべきことがある。 「命さん、誰か呼んできて下さいッ。それと、できれば毛布か何か!」 「わかった」 私の言葉に頷いて、命さんは駆けて行く。 「……、ッ……」 女性は尚も何事かを紡ごうとしたが、震える唇では言葉すらも発することが出来ないようだった。 身体を震わせ、冷え切った身体。 この状態に私の治癒が効くのかどうかわからなかったけれど、しないよりはましだろう。 私は女性の身体を抱いたまま目を閉じ、意識を集中させた。 コンコンッ。 Room01の扉を軽くノックすると、程なくして「はーい」と声が返って来る。 「珠です。この部屋に迷い込んできた少女を寝かせていると聞いたのだけど」 そう告げると、カチャリと扉が開いて千景さんが顔を出した。 千景さんは私―――珠十六夜―――を室内に促し、「まだ眠ったままよ」と状況を説明する。 私は部屋の奥へと進み、ベッドで毛布を掛けられ眠っている少女に近づいた。 「施設のパスワードを知っていた少女……この子が」 少女に付き添っていた悠祈さんが顔を上げ、不思議そうに瞬いた後でふと気づいたように「そっか」と声を上げた。 「ここの扉、外部の人間が開けることは出来ないんですよね……。私達も最初は、誰かが戻って来たんだと思い込んでいました。だから、驚いて……」 彼女は真田命さんと一緒に、この少女を最初に発見した人物だと聞いた。 まだ詳しいことはよくわからない。ただ驚くべきことが起こった、その事実だけが今明らかになっていること。 私がいつものように制御室でデータ解析に勤しんでいた時、この施設の扉が開き人間が出入りしたという合図となるアラームが鳴った。都さんのようにしょっちゅう施設を抜け出す人物もいることだし、気にするほどのことでもなかったのだが、時間も時間だ。誰が出入りしたかということだけを確認しておこうと思った。 しかし画面に現れたメッセージは、現在登録している人物データの中には該当者がいないという内容だった。 その不可解なメッセージに、機械の故障も考えた。滅多にありうることではないのだ。この施設に滞在している誰かが外部の人間にパスワードを教えたか、或いは外部の人間が元からパスワードを知っていたか、そのどちらかということになる。 事の真相を確かめるべくホールへと向かえば、食堂に向かう途中の真田さんと鉢合わせた。そして彼女が告げたのは「この施設の人間じゃないわ。今、乾達の部屋……Room01に寝かせてある」とのことだった。 そうして私は少女が眠る部屋、Room01に赴いたというわけだ。 「身体が凍えていること以外には、特に怪我も見当たりませんし命に別状はないと思います。今、命さんに温かいスープか何かを作りに行ってもらっています」 悠祈さんは少女の容態についてそう説明した後、「もう治癒も必要ないみたいです」と付け加えた。 治癒……?手当てのことを言っているのだろうか。ともあれ、少女が無事なのは幸いだ。 「ところで、この子は誰かの知り合いかしら?内側から誰かが開けたわけでもないようだし」 この場にいる二人、悠祈さんと千景さんに問い掛けるも、二人は揃って首を傾げた。 「皆に聞いてみないことにはわからないけど……でも最初の諸注意で言ったわよね、外部にはこの施設のパスワードを漏らさないことって」 千景さんの言葉に頷く。確かにこの施設、外部に――特に米軍に知られては厄介だ。情報はどこから漏れるかもわからない。だからこの施設の人間以外には漏らさないこと、と厳重に注意していたのは記憶に残っている。 「まさかこの女性が、元々パスワードを知っていたなんてことは……?」 悠祈さんはぽつりと言って、視線を少女へと向ける。私もつられて少女へ目を向けながら首を捻った。 「施設についての情報そのものが、一体どこから来たものかということになるわね。二十年間も封じられていた施設でしょう?」 「警察の極秘情報だったのよ……危機に瀕した時に使えっていうね」 「その極秘情報を知っていたのは?」 「警察の人間でもほんの一握りね。今は蓮池課長ぐらいしか知らないんじゃないかな」 ということは、益々この施設のパスワードを知っている人物は絞られてくる。 そもそも警察に極秘情報を渡したのは誰?――この施設を作った人物は? 「……まさかね」 微かな寝息を漏らす少女に手を伸ばしながら、小さく呟く。この少女――せいぜい二十歳前後といったところだろう。そんな人物が二十年も昔に施設を作ったはずがない。 「この子は一体、何者なのかしら……」 「目、覚まさないことにはねぇ」 そんな千景さんの言葉には「確かにね」と同意して、ふっと息を吐く。 この少女が目覚めたら、全てが明らかになるのだろうか。 そう思った、けれど――何かが引っかかる。 妙な違和感。不思議な感覚に捉われ、私は少女の顔を見つめて眉を寄せた。 「……どうかした?」 千景さんの言葉に顔を上げ、顎に手を当てて思案した後、私は言った。 「この子……眼鏡、掛けていなかった?」 「あぁ、掛けてたわね。この子の荷物と一緒に、棚に置いてあるけど」 「取ってきてもらえるかしら」 「はいはい」 きょとんとしつつ、私の言い付けを聞いて隣のベッドから腰を上げる千景さん。 目を伏せた少女の顔、この幼げな、けれどどこか鋭い顔立ち―― やがて千景さんは「はい、眼鏡」と青色のフレームの眼鏡を差し出した。 レンズにひびが入ってしまっているけれど、このフレームの形は…… 少女の目元に眼鏡を近づけ、眼鏡を掛けている状態に近い形を作ってから、改めて少女の顔を見つめる。 ……やっぱり。 どうして気付かなかったのだろう。この姿、何度となく目にして来たというのに。 「私、この子のこと……知っているわ」 「え!?」 「あ、珠さんのお知り合いだったんですか?」 驚いた様子の二人に、「知り合いではないの」と小さく告げる。 でも、何故なの?……何故、彼女がこんなところに? この少女は今頃、遠く離れた地で名声を手にしているはずだった。 こんな薄着で寒さに凍え、荒んだ東京市にいるべき存在ではないのだ。 「誰なの、この子……?」 千景さんの問いに、私は少しだけ躊躇して、深く息を吸った。 もしも少女が本当にあの方ならば、私は……。 「……銀 美憂(シロガネ・ミユウ)。この少女は、世界的に有名な科学者なのよ」 「科学者?こんな若い子が?」 「ええ。歴史的研究を成し遂げた偉大な人物よ。……まだ若干、十九歳なのにね」 「ふぅん?なんか凄そうね」 千景さんの軽い相槌が滑稽なほど、偉大な人物だというのに。 科学者でこの少女の名を知らぬ者はいない。 否、一般常識としても彼女の名前は知っておくべきである。 彼女こそが、荒廃した地球で未来への先駆けを担うことの出来る人物であるはずだ。 ――しかし何故、今私の目の前で彼女が眠っているのか。少女の正体を確信しても尚付き纏う違和感ばかりは、彼女自身の口から事実を聞かぬことにはどうしようもないことだった。 「またネズミが一匹紛れ込んだみたいだな……」 薄いドアの向こう側で呟かれた言葉を耳にして、ドアノブに伸ばした手を止めた。 蔑むような、嘲笑うような響きを持ったその声は、聞き覚えのあるものだ。 しかし今、このドアの向こう側にいるはずの人物のものではなかった。 「紛れ込んだのはネズミだけですか?」 楽しげな笑みを含んで上げられたもう一つの声こそが、約束していた人物のもの。 私―――伴都―――が呼び出した人物、アキトの声だ。 「お、言ってくれるじゃねぇか。悪いなぁ、逢引の邪魔しちゃってさ」 「とんでもない。きっと歓迎してくれますよ……そうですよね、都さん?」 「……」 さすがは怪盗FBといったところか。ドア一枚を隔てただけの気配なんてお見通しね。 しかし名を呼ばれておいても尚、ドアノブに伸ばした手を動かすことが出来なかった。 先ほど顔を合わせた彼――少年らしい純粋そうなアキトとは、何かが違う気がして。 ここまで来て引き返すわけにもいかず、私はドアノブに手を掛けてカチャリと回した。 ホールから入ることの出来る備品室、滅多に使う部屋ではなく、スイッチによって電気が点るようになっている。ドアを引くと、室内は暗闇。ホールから差し込んだ一筋の光が、部屋の奥で密着する男女の姿を浮かび上がらせた。 「……どういうことよ、これは」 室内に足を踏み入れて、手探りでスイッチを探す。 「何のことですか……?」 アキトは不思議そうに、しかしその奥で愉快そうなニュアンスを含ませてとぼけるように問い返す。 カチリ、電気を灯せば目に映る。部屋の奥の木箱に腰を下ろすアキトの姿と、アキトの膝の上に乗ってその手をアキトの首に絡ませる、憐の姿。 「……子どもだと思って侮ってた私が悪かったのね。一人で舞い上がって、私バカみたいじゃない?」 自嘲的な言葉を投げ掛けながらも、微かな憤りと失意とが胸に渦巻いて、僅かに声が上擦った。 憐が悪女だってのは見ればわかる話だけど、……アキトまで、私を裏切るなんて思わなかった。 純粋そうな目を笑みに歪めて、アキトは言った。 「何、言ってるんですか……?僕はずっと、都さんのことだけを……」 「イチャイチャしながら言ったって説得力なんかないわよ。いい加減にしなさい」 私が裏切られる様を見て笑ってる。酷いじゃない、そんなの。 アキトを睨みつければ、憐がクスクスと笑いながら「イチャイチャってこういうことか?」とアキトの頭を引き寄せた。憐の唇がアキトの顔に触れるか否かのところで、私は二人から目を逸らす。 バカみたい。こんなの見せ付けられるために来たんじゃない。 私はアキトが純粋に、想ってくれてることが嬉しかっただけなのに。 結局騙されてただけじゃない。こんなんじゃ怪盗HAPPYの名が朽ちるわよッ。 「……もういいから。憐と仲良くね」 吐き捨てるように言って二人に背を向けた。 「まぁ待てって……」 気だるそうに掛けられる憐の声、無視しようかと迷ったけれど、「何よ」と苛立ちながら小さく返す。 カツン、カツン――硬い靴音が室内に反響し、やがて私の背後までやってくる。 振り向けば、憐は私を見上げクスッと笑みを漏らす。 「あたしはお前らのキューピットになってやろうと思っただけだ。……感謝してもらいたいな」 憐はゆっくりと私の周りを歩きながら言って、その手を扉に置いた。ちらりと横目で見遣る視線がふっと細められた――刹那、ドンッ!と背中を押され、私はアキトの方に数歩押しやられる。 「何を」 振り向いて憐を見遣る。その時突然ガシッと腕を掴まれ、見上げれば薄い笑みを浮かべるアキトがいた。 カチャッ、と小さく施錠の音が聞こえたと同時に、強い力を掛けられて私は壁に背をついていた。 アキトの両手が私の肩を押さえつけ、抗うことも侭ならない。 「……ッ」 焦りを覚えながら憐に目を遣れば、「ごゆっくり」とこの先の展開を示唆する呟きを返された。 アキトは表情から笑みを消し、真っ直ぐに私を見下ろしている。 「何、すんの?……バカなこと、しないでよ……?」 壁際に追い詰められ、男に強い力で押さえつけられて―― この現状を考えれば、この先の展開は見えたも同然だった。 協力者の憐、そして、主犯は…… 「都さん……僕は、ただ貴女のことを奪いたいだけだった……」 「ふざけないで!こんな、やり方ッ」 不意にアキトの指先が、するりと私の首筋を撫ぜる。男の子にしては柔らかくて細い指先が、私のうなじを滑り、髪の生際をくすぐるように這いまわる。冷たい指の温度が、敏感な箇所を鋭くなぞった。 「僕は、もう奪ってしまった……。強引な口づけはほんの一瞬だったけど……僕は、嬉しかった」 「……、……」 怒号が喉の奥まで出かけるけれど、声が消える。 アキトの声も、言葉も、純粋で少年じみたものだった。 そんなアキトがこんなふうに、強引に私を押さえつけているなんて、信じられなくて。 「僕は願ってしまった……貴女のことをもっと知りたい……貴女に近づきたい……」 偏執的なまでに純粋な想いで、彼がこんなことをしているのならば…… 私……どう、したらいい? 「都さん……」 切なげに名を呼ばれ、言葉に詰まる。 アキトは首筋に這わせていた指を離し、私の前髪を撫ぜるように梳いた。 それから少し強引に額を押さえ、私の顔を上げさせる。 真っ直ぐな瞳が私を見下ろす。貫くように真っ直ぐな瞳が私を見据える。 ゆっくりと顔が近づいて、彼の唇がふわりと私の頬を掠めた。 「……アキト?」 私の肩に顔を埋め、アキトは小さく身体を震わせた。 何故、震えているの? 一体何に対して……? 「都さんは、僕を……少し、誤解しているようです」 アキトは震えた声で言いながら、私の手を取った。 彼が何を言わんとしているのかがわからずに、私は続く言葉を待つ。 私の手を、その身体にゆっくりと導きながら、彼は言った。 「怪盗FBは何の略か……ご存知ですか?」 「え?」 「怪盗False Boy。」 「……」 ふにゃ。 彼の手が導いた、彼の身体、彼の胸元―― 触れたその手触りに、私は暫し、頭が真っ白になっていた。 「ッ、クク……ごめんなさい、都さッ……」 アキトは震える身体をゆっくりと上げて、そして耐えかねたといった様子で……笑った。 見れば、憐もクスクスと笑いを堪え、私と目が合えばブッと思いきり吹き出す。 「え?…ちょ、ちょっと待って、何、アキトって……!!」 「言ったでしょう?False Boyの訳は?」 「ニセモノの……男の子」 「ご名答!」 満面の笑みで肯定され、私は言葉を失った。 未だにアキトの胸元に寄せた手、確かめるように握ると――ふにっ。 ちょ、ちょちょちょちょ、ちょっと待ってーーー!! 何、なんなのこの柔らかさは!私よりでかいじゃんッ!……嘘ォッ!? 「つ、つ、つま、つまりッ、アキトは男の子じゃなくて……」 「女の子です!」 …………絶句。 あ、あぁ、もうわけわかんないわよ。 アキトは女だし、じゃあ何、アキトじゃないじゃん。 憐も爆笑してるし、ええ!?もう、何、これって…… 「だ、騙したの!?」 「はい、騙しちゃいました。」 「騙しちゃいましたって……」 カラッと爽やかに言われた言葉に、脱力して思わずその場に座り込んでいた。 そんな私に、アキトは紳士的な笑みを浮かべて腰を屈める。 「御園秋巴(ミソノ・アキハ)、二十六歳、正真正銘の女でした」 「あ……アキハだぁ?に、二十六歳だぁ……?」 「えへへ。都さんも皆さんも、見事に騙されてくれるから楽しかったです。……憐さんにバレた時は焦りましたけどね?」 そう言ってアキトは……いや、アキハは、扉のところで今もケタケタと笑っている憐に目を向ける。 憐は涙を拭いながらこくこくと頷いて言った。 「あたしだって驚いたっつーの。触ったら胸あるんだもん、ありえないよなー」 「いや、まさか触られるとは思わなかったんですよ。憐さんってばセクハラー」 「うるせぇ、お前だってノリ気っぽかったじゃんよー」 「いやぁ、男の子演じてる以上は憐さんみたいな色っぽい人にはドキッてしとかなきゃかなって思ったんです」 「なんだよそれ!女でもドキッとしろよッ」 和気藹々と話しているアキハと憐に、私はようやく状況を把握し、それと同時に空笑いが漏れてくる。 本当に可愛い男の子だと思ってたのに……二十六歳、女って……年上じゃん。 「でもほら、僕……じゃなかった、私って元々少年顔だからね。これ素顔なんですけど、どう?まじまじと見ても男の子で通用するでしょ?」 「……はぁ。遼にちゃんと謝っときなさいよ」 「あぁ、どうしようかなぁ。アキ君って呼ばれるのも結構楽しかったし!」 アキハはそう言って「えへへ」と笑う。変なやつぅ……。 散々騙されて、弄ばれて、私ってば健気じゃーんとか思うわけ。 アキハはアキハで……散々遊んでくれちゃったわけだけど……。 「ともあれ、男でも女でもこの施設にお世話になるのは決めちゃったから!宜しくね、都さん」 そう言って手を差し出すアキハに、私はまた少しの空笑いを漏らしてから、手を重ねたのだった。 「都でいいわよ。……バカ秋巴」 「あたしは絶ッッッッ対に認めなぁぁぁぁーい!!!」 ドンッ、とテーブルに手をついて怒鳴りつけるのは、今回の一番の被害者とも言える遼ちゃんだった。 因みに加害者は私―――御園秋巴―――だったりするんだけどね。えへ。 「んなこと言っても……ついてるもんはついてるし、ついてないもんはついてないんだからしょうがないでしょ」 千景ちゃんが調書のデータを書き換えながらサバサバとした口調で言っては、「女ねぇ」と感心したように声を漏らした。いやぁ、敏腕婦警さんまで騙せちゃってたなんて、私も結構やるなぁ。 「だ、だ、だって!!いきなりアキ君が女とか言われてもッ、そんなッ……うぅ」 ホールの隅っこのテーブルで再事情聴取が行なわれ、そこに物凄い勢いでやってきた遼ちゃん。 遼ちゃんは第一声で先ほどの怒声を放ったかと思えば、千景ちゃんにあっさりあしらわれてガクリとその場に膝をついた。 「……アキ君、あたしとのドリームは何だったの?ねぇアキ君答えてよぅ」 遼ちゃんはテーブルにべったりと頬をくっつけ、恨みがましそうな視線を私を向ける。 あはは、これはちょっと大変だなぁ。 「ごめんね、遼ちゃん。でも君とドリームなんて――」 ……した覚えないけどなぁ。と言おうとしたけど、ギロリと怖いぐらいの視線を向けられて押し黙る。 そ、そんなにアキ君が好きだったんだ。困っちゃったなぁ。 「あたしね、アキ君のことが好きだったの。……え?本当?じ、実は僕も遼さんのことが……きゃぁッ!あたし達相思相愛だったのね!……う、嬉しいです!遼さん!……アキ君!」 「……」 「そして二人は抱き合って、互いの体温を感じるの……少し経った頃、アキ君の指先があたしの熱い頬に触れるのよ、そして静かに顔が近づいて、あたしは目を閉じてその瞬間を待つの!あぁっ、アキ君だめよ、嬉しいのはわかるけど、そんな熱いキスだなんてッッ!!」 「……は、遼ちゃん?」 「いやん、待ってアキ君。嬉しいよ、あたしもアキ君と一つになりたいっ。でも、お互い初めて同士だし……ゆっくり、優しく、して?」 「なぁーにが初めて同士よ、マセガキッ」 パコンッ! エキサイトしていた遼ちゃんに、千景ちゃんの一撃が容赦なく降り注ぐ。 あまりに美しすぎるノートショットに、私は言葉を失って二人の様子を眺めていた。 遼ちゃんはテーブルに突っ伏せ、僅かに打ち震えた後で「ふぅぅ」と息を吐いて沈黙。 「……ま、まぁとにかく、秋巴さんは今後も普通にここで暮らしてもらっていいし」 「はーい、お世話になります」 「可愛い男の子が来たって誤解してる人たちには、ちゃんと弁解しといてね?」 「わかりましたー」 千景ちゃんの言葉に頷くと、千景ちゃんは席を立ちつつ遼ちゃんに目を向けて「問題はこいつか」と呟く。 少しの沈黙の後、励ますようにぽんぽんと遼ちゃんの肩を叩いて彼女は言った。 「アキトがアキハになっただけなんだから、そんなに落ち込まないでよ。ほら、秋巴って漢字も変わらないんだし、大差ないでしょ?ね?」 「うぅぅぅ」 遼ちゃんはギギギギッと顔を上げて千景ちゃんを見上げたかと思えば、ガバッと身を起こして数歩後ろに引いた。わなわなと打ち震えながらも、大きく息を吸い込み、そして吠える。 「アキ君なんかいなくたって!!!あたしには先生がいるんだもんーーっっ!!!」 言い切ってから即、遼ちゃんは土煙を上げんばかりの勢いで駆け出した。 「せ、センセ……?」 千景ちゃんがきょとんとしている間に、ドドドドドド……とどこへともなく消えていった遼ちゃん。 残された私と千景ちゃんは顔を見合わせ、揃って首を捻る。 「……よ、よくわからないけど、大丈夫みたい?」 私が言うと、千景ちゃんは尚も首を捻りながら「そうねぇ」と頷く。 「先生なんて初耳だわ……遼ってば、年下の男の子かと思えば今度は教師っすか……」 「……マッチョの体育教師とかだったらヤだなぁ」 「……ヤだなぁ」 素朴に二人で同意してから、また揃って首を捻った。 御園秋巴(ミソノ・アキハ)、地下施設での初日は、そんな騒動の中で幕を下ろしたのだった。 ちゃんちゃん。 |