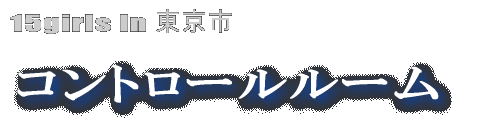
|
午後十四時。 地下施設に入ってから、大よそ五十七時間が経過した。 睡眠と食事以外、大部分の時間を、私―――珠十六夜―――はこの制御室で過ごしている。 科学者である以上、この部屋に入り浸ることは当然と言えるだろう。ここには過去の機材が豊富に揃っており、コンピューターのHDには過去に記録されたデータが多く残っている。いずれも、現代にはもう残されていない貴重なものであり、私は寝る間も惜しんでデータ解析に勤しんでいた。 過去の文明とは、なんて偉大なのだろうか。残されたデータを見ては感嘆の繰り返し。せめて私があと十年早く生まれていれば、この素晴らしい文明の利器の中で研究を行なうことが出来たというのに。 忌まわしき血の大晦日が起こったのは、私が齢九歳の頃だった。私の家族は科学とは縁遠く、その頃は私自身も科学に特別興味を抱いていたわけではなかった。幸い被災から逃れた珠家は東京市から遠く離れた場所で平穏に暮らしていた。血の大晦日を機に文明は崩壊し、人々はアナログ的な生活を強いられることとなったのだが、それもいつしか慣れ、原始的な生活が当然になっていった。 十八になった頃、両親が感染症にかかって他界した。私は両親が残した遺産を使い、東京市内の小さな地下住宅を購入した。中古物件だったその住宅には、不可解な機器が多く放置されたままだった。生活に必要なスペースは確保できていたので、機器を取り除くことはせずに放置したまま一年程が過ぎた頃。私は一人の女性と出逢うことになる。 小さな食品会社で働いていた私の先輩に当たる人物。既に四十歳を越えた婦人だった。彼女とは、幾度か仕事で一緒になることがあった。そして偶然、家に放置された機材のことを話した時、彼女は目を輝かせて私の自宅に訪れたいと申し出た。 彼女は科学的な分野で、新たな食品を製造する研究を行なっていた。私にとってはガラクタでしかなかった機材の山は、科学者である彼女にとっては宝の山だったのだ。彼女は何度も私の家に通い、機材について様々なことを教えてくれた。そして私も次第に、家にある機材に、そしてそれを活用して未知の世界を見出す科学という分野に興味を惹かれていった。 彼女の指導と独学により、私は彼女の後続人として食品研究に没頭した。そしてある時、彼女は言った。 『十六夜さんは立派な科学者ね。もう教えることはないわ』と。 その数ヵ月後に、彼女は戦争に巻き込まれて命を落とした。 あれから長い時が経ち、私はすっかり科学の世界に身を染めている。 科学とは奥の深い分野だ。過去の人々が作り出した文明を再構築すると共に、自らも新しく開拓して行くことができる。決して終りなどない世界に、見事に取り込まれてしまった。 そして私は、食物関連の研究を進めて行くうちに、意外な方向の技術を見出すことに成功した。 医学か、或いは生物学か。それは――人体改造という、法にも触れる、危険な技術。 生憎、研究は途中で凍結したままで、自宅でもあった研究所を米軍に占領されてしまった。 しかし、この地下施設の設備を使用すれば。あの研究の続きを、ここで行なうことも可能かもしれない。 そのための模索も兼ね、様々な機器を隈なく調査している最中。……だったのだが、残念ながらこの施設にあるのは人間が生きていく上で必要最低限の設備でしかなく、私の求める機材は揃っていないようにも思えていた。当時の技術を考えれば、そのような機材が過去に存在していた可能性は大きいのだが。 後は、この施設の設備を応用して新しく機材自体を作り上げるという手も……。 ポーン――と、不意に私の思索を遮る音が室内に鳴り響き、私は顔を上げる。 この音は、制御室の出入り口に取り付けられたインターフォンの呼鈴だ。 私は席を立ち、制御室入り口に備えられたカメラ付きインターフォンに接続されているテレビ電話の受話器を取った。画面に映し出されたのは、私がこの施設へと連れてきた少女、千咲だった。 米倉千咲、十五歳。とある理由で行動を共にしていた幼い少女。十五歳という年齢から見て、千咲は比較的幼い顔立ちをしている。雰囲気や挙動も相俟って、千咲が年齢相応に見られることは少ない。けれど相反し、その耳には螺旋の形をしたピアスがついていたり、髪色も派手なピンク色だったりと、垢抜けた部分も持ち合わせている。その矛盾した様相にも、理由があるわけなのだが。 「……イザヨイ」 千咲はカメラを見上げ、ぽつりと私の名前を呼んだ。心を閉ざした子どものように、千咲の表情はいつもどこか強張っている。 「どうしたの?私に用事?」 インターフォン越しに問い掛ければ、千咲は戸惑いを滲ませて黙り込んだ後、再度カメラを見上げてぽつりと続けた。 「チサ、ずっと、ひとり。イザヨイ、いそがしい?」 たどたどしく言葉を紡ぐ千咲の表情は寂しげだった。 十五歳ではあるけれど、千咲の精神年齢は今現在、著しく低下している。そんな彼女が、孤独に耐えられるだけの強さを持っているはずもない。 「入れてあげるわ。だけどまだお仕事が残っているから、少しだけね。」 そう言って扉のロックを解除すれば、自動扉が開き、千咲がおずおずと制御室内に足を踏み入れた。 千咲がこの部屋に来るのは初めてのことだ。科学機材に気を引かれるように辺りを見回しながら、奥の私のところまでやってくる。 「イザヨイのおしごと、いつ、おわる?」 千咲は私を見上げ、僅かに眉を寄せて問い掛けた。そんな千咲の髪に手を伸ばし、あやすように軽く撫ぜてからそばの椅子に座らせる。そっと千咲の肩に手を置き、その顔を覗き込んだ。 「千咲が寂しい思いをしているのはわかるけれど……私も忙しいの。やるべきことはまだ沢山あって、貴女を構っている暇はないのよ。……わかるわよね?」 「……うん」 私の厳しい口調に、千咲は不思議そうに瞬いてから頷いた。 きっと千咲にはわかっていない。千咲には何もわからない。 ただ、私の言葉には従順であらねばならない。 どんなに寂しくても、千咲が駄々をこねることはない。 それを確認した上で、私は次なる段階の問いを投げ掛けた。 「千咲。身体のおかしいところはないかしら?」 「……チサ、元気」 「そう。ご飯はちゃんと食べているわね?」 「……イザヨイの言ったやつ。えきたい、りゅう……りゅう……」 「流動食。」 「……うん。それ」 私の言いつけをしっかり守っているようだ。 千咲の身体を撫ぜるようにしながら、その身体の一部一部の触り具合を確かめて行く。 至って正常。問題無し。 「それじゃあ千咲、私はお仕事の続きがあるから、部屋に戻っていなさい。」 「……」 「いいわね?」 「……うん」 判断に若干の遅れあり。人格も確かということね。 問題はない。問題はない、けれど……。 このままの状態を維持すること自体に、少し問題があるようにも思える。 否、研究が続けられない現状では手の打ちようがないのだから、仕方がない。 私は千咲を促して席を立たせ、入り口まで一緒に歩いた。扉の前、千咲は寂しげに私を見上げたが、言いたげにした言葉は口にせずに、ぽつりと挨拶だけして去って行く。 「じゃね、イザヨイ……バイバイ」 「はい、またね。大人しくしているのよ」 そうして千咲の姿を見送ってから、私は奥の席へと戻り、傍らに置いていた煙草の箱を手に取った。 正直なところ、子守にはなかなか慣れない。ある意味千咲は私の子どものようなものだけど、実際は他人なのだし……いつまであの子の面倒を見れば良いのかしら。 私が欲しいのはただ一つ。研究の成果が挙がれば、それで十分なのに。 「あれれ、珍しい」 「……?」 食堂で少し遅めのお昼ご飯を食べ終えて、私―――高村杏子―――と未姫さんは個室に戻るために廊下を歩いていた。何気ない世間話など交わしつつ歩を進めていたその時、制御室から続いている廊下を歩いてきた少女と鉢合わせ、私は足を止めた。 普段顔を合わせている人物ならば簡単な挨拶でも交わすところだったけれど、その少女の姿を見たのは随分と久しぶりだった。三日間ぐらいこの施設で一緒に過ごしているはずなのに、この子の姿を見たのは調書を取った時以来である。 確か、チサちゃんって言ったっけ。米倉千咲ちゃんだ。ピンクの髪の可愛い女の子。 「千咲ちゃん、こんにちはー」 私は笑んで、千咲ちゃんに声を掛けた。折角だから仲良くなってみたいなぁなんて思っていたりして。 未姫さんも私につられるように「こんにちは」と慌てて頭を下げている。 だけど、千咲ちゃんは不思議そうに私達に目を向けるだけで、言葉を返してはくれなかった。 う、うぅ、もしかして人見知りかな。私達、そんなに怖いお姉さんに見えちゃってるのかなっ。 「えっと……千咲ちゃん、十六夜さんのところに行って来たのかな?」 なんとか話題を作ろうと言葉を投げ掛けるが、千咲ちゃんは不思議そうに瞳を揺らし、私を見上げるばかり。わ、わ、どうしよう。千咲ちゃん、もしかして私達に怯えてますかっ?! 「……あー」 不意に未姫さん、どこか間の抜けた声を上げ、ゆるりと首を傾げて見せた。 「ピンクの、髪……可愛い、です……ね?」 「……ぴんく。」 わ!千咲ちゃん喋ったよっ! 私には反応してくれなかったのに……なんだかちょっぴりショックな杏子なのです。 がっくりしながら、二人の様子を見守ります。 「私も……金色と、黒色です。」 「……きんぱつ。」 「はい。でも片方は黒色で、ある意味、目立つ髪……?」 「……うん」 なんだかテンポの掴み難い二人の会話。これは独特の周波数があるのかなぁ。 色々経験してきたつもりなのに、こんなにも会話に入れないなんて前代未聞だよ。 「ピンク髪さんと……金と黒なので」 「……うん」 「ちょっと、似てるかな、と。思います」 「……うん、にてる。」 似てないよ!!……って思うんだけど、当人である二人が言うんだから似てるのかな。 変わった髪色をした二人だけにわかる世界。変わった髪色同盟? わ、私も髪の毛の色変えちゃおうかな。紫とかに。 ……。 とりあえず髪の毛の色が変わってて似てる、っていうお話だったんだよね。 で、そのお話が終わったから沈黙してるんだよね。 ……。 ど、どうしよう!私、もう話題が思いつかない! また何か話し掛けて黙り込まれちゃうとショックだしなぁ。 「……あ」 と、沈黙を破ったのは千咲ちゃんだった。何かに気付いたように瞬いた後、困ったように後ろを――多分、制御室の方を見て、それから私達の方に目を戻す。 「チサ、おとなしくしてるのよ、っていわれた。……しゃべるの、だめだった」 千咲ちゃんは肩を落として呟いた後、口元を覆って顔を伏せる。 「喋るのだめ……?で、でも大人しくしてなさい、だから、特に暴れたりしなかったら良いんじゃないかな?」 余りの落胆の仕方に少し驚きつつ、私は笑みを浮かべて千咲ちゃんにアドバイス。 千咲ちゃんは私の言葉に不思議そうに瞬いてから、今度は両手で口を覆ってブンブカと首を横に振る。 そして、逃げるようにして私達の前から立ち去っていた。その逃げ足の早さに呆気に取られてしまう。 「……変な子、ですね」 「……う、うん。」 未姫さんの言葉に思わず同意していた。未姫さんもしっかり変な人だけど、千咲ちゃんはそれを上回っている。確か十五歳って言ってたはずだけど、とてもそうは思えない。 何か裏がありそうな!やっぱりここは小説家として調査すべきだよね! 「そうだ!十六夜さんに聞けばいいんだよ」 私は名案を思いつき、未姫さんに「ね?」と同意を求める。 未姫さんはきょとんとして私の顔を見つめた後、少し小首を傾げて考えてから、「かもしれません……多分」と、ちょっと引っかかるけど、一応同意してくれた。よし。そうと決まれば早速! 私達は目的地を個室から制御室に変更して、千咲ちゃんが来た廊下へ進む。普段は滅多に通らない廊下、ドキドキしつつ未姫さんと一緒に歩いてく。実は十六夜さんとも、あんまり顔を合わせたことがない。彼女はずっと制御室にいるとかで、調書の日の後は一度廊下ですれ違っただけだ。三つ上のお姉さんなんだけど、うぅん、同じ二十代後半とは思えない大人っぽい人だったなぁ。あ、私はまだ二十六なんだから、二十代後半じゃなくて二十代半ばって言いたいんだけどね! さて、私達は制御室の扉の前に到着し、一度顔を見合わせた。なんだか重厚な扉を前にして、ちょっとだけ気が引けちゃったりもする。だけど勇気を出して、インターフォンを押してみようッ! ポーン。 小さく響いたチャイム、それから少し経って、インターフォンのテレビに十六夜さんのお顔が映る。 「こんにちは。高村です。」 「飯島、です」 私達はぺこりと頭を下げ、十六夜さんにご挨拶。 十六夜さんは来客者が私達だったことが意外なのか、どこか不思議そうな表情だった。 『あら、ごきげんよう。どうかなさったのかしら』 「少し聞きたいことがありまして。千咲ちゃんのことなんですけど」 『千咲の?……どのような?』 「別段知りたいことがあるっていうよりも、不思議な子だなぁって思って。あんまりお話してくれないし……それで、本人が話してくれないから十六夜さんにお聞きしようかな、と……」 と話しながら、勢いでここまで来てしまった自分の行動、少ぉし後悔。 わざわざ十六夜さんに聞くようなことでもないかもしれない。それに、十六夜さんって忙しそうだし。 「あ、あの、忙しいならいいんです」 慌てて付け加えると、十六夜さんは思案するように目を逸らした後、こう続けた。 『構わないわ。私がどこまでお話出来るかはわからないけれど……入って頂ける?』 「はいっ」 思いの外、あっさりと扉を開けてくれた十六夜さんに少し拍子抜けしつつ、ここまで来た以上は後に引けないなぁと覚悟を決める。こうなったら千咲ちゃんのこと、聞いて聞いて聞きまくっちゃうんだからッッ。 杏子さんに連れてこられる形で、私―――飯島未姫―――は十六夜さんのいらっしゃる制御室に足を踏み入れていた。部屋中に沢山の機械……置いてあるんじゃなくて、殆どが壁に埋め込まれているような形で、どこを見ても機械だらけのお部屋だった。こんなに機械がいっぱいじゃ、機械酔いしてしまいそう……。 私達を招き入れた十六夜さんは、部屋の奥で煙草を揉み消しながら「煙たくてごめんなさいね」と謝る。あぁなるほど、やっぱりお酒を飲むと煙草が進むと言うし、機械酔い……ン?なにかちがう? それはとにかく、私と杏子さんは部屋の奥の方へと進んで、改めて十六夜さんに会釈した。 十六夜さんはすらりとした綺麗なスタイルで、さり気なく羽織っている白衣も格好良い。眼鏡の奥には鋭い瞳、赤いルージュの引かれた唇にしてもそうだけれど、まさしく「大人のオンナ」という感じの人である。 そんな十六夜さん、困ったように室内を見渡していた。つられて私もきょろきょろと辺りを見回して、彼女が探しているのは椅子だろうかと思い当たる。この部屋にはコンピューターに向かう椅子しかなくって、来客用の応接セットなんてものは置いてない。そんなものを置くぐらいなら機械、なのだろうか。 「ろくにお構いも出来なくて申し訳ないわ。立ち話になってしまうけれど……」 「あ、いいですいいです。いきなり押しかけちゃったのも悪いんです」 十六夜さんの言葉に、杏子さんは苦笑を浮かべて言った。確かに、突然押しかけるの、良くないかなと、先ほどちらりと思っていた。だけど杏子さんがあまりにキラキラした瞳を見せるので……つい。 それに、私も千咲ちゃんのことが気にならないわけではなかった。なんだか不思議な子。 私と通じるものを感じるような……周波数というか……電波というか……雰囲気……。 「千咲のことを聞きたいと言っていたわね?」 十六夜さんが切り出した言葉に、杏子さんと一緒にこくこくと頷く。十六夜さんはふっと弱い笑みを浮かべると、冷たそうな鉄の機械の側面に凭れながら髪を軽く掻き上げた。か、かっこいい。 「……千咲、どんな様子だったの?」 「可愛らしかったですよ。未姫さんと髪の色のお話とかして。ねぇ未姫さん」 私は杏子さんに全てを任せる気満々だったので、突然話を振られてうろたえる。髪の色。髪の色が。 「ピンクと金と黒が……」 「似てるんですって」 しどろもどろになる私に続けて、杏子さんが言ってくれた。 私達の言葉に十六夜さんは眉を顰め、「似てるの?」と小さく問う。 「似てるんです」 「……らしいです」 「…………」 私の肯定と、杏子さんの曖昧な言葉と、十六夜さんの沈黙。 あぁ、違う、この周波数じゃ十六夜さんには届かないッ?! 微妙な空気に支配され、黙り込むこと十数秒。 気を取り直すように杏子さんが漏らしたコホン、という咳払いで、ようやく元通りの空気が戻ってくる。 十六夜さんは少しやりにくそうにしながらも、ゆるりと宙に視線を巡らせてから口を開いた。 「千咲のこと……」 ぽつりと零すような言葉。切れ長な瞳、伏せられると、カーブを描く三日月のような輪郭。 聞きに来たというわりに問いかけを放たぬ杏子さんの代わりに、十六夜さんは紡ぐ。 「変な子だと思ったんでしょう。人間的な何かが欠けている、と」 「……」 私と杏子さんはちらりと視線を交わし、揃って十六夜さんの言葉に黙り込んでいた。 確かに彼女の言う通り、千咲ちゃんってなんだか変な子、で。 だから聞きに来た、ということになるけれど、そんなことを面と向かって言えるわけもない。 視線をフロアに落としていた十六夜さんは、不意に闇色の眼球で私達の姿を捉えた。 刺すような鋭さを持った一視には、感情が篭っていない。 「……知りたい?」 ストレートな問いに、また私達は黙り込んでから、一つだけ頷き返す。 だけどこの時私は、この部屋に来て、そして千咲ちゃんの名を出した――そのこと自体が間違いだったのかもしれないと、微かな不安を抱かずにはいられなかった。十六夜さんの目が、あまりに冷たかったから。 「千咲のことは、別に隠す必要などないの。……だけどわざわざ話す必要もなかった。貴女達が聞きたいと言うのならば」 「……聞きたいです」 杏子さんは先ほどよりも幾分表情を硬くして、足を一歩踏み出した。 十六夜さんの口調は、重たくて、冷たかった。だから気付く。 千咲ちゃんという少女は、私達が思っていたよりもずっと深い場所に何か秘密を隠し持っているのだろう。 その秘密に今触れようとしている。触れた以上はもう後戻りできない。 そう理解した上で、杏子さんは頷いた。……私も、今この場から逃げ出すほどの勇気はない。 ほんの僅かな時間で冷たく張り詰めた空気の中、私は小さく息を吸い込み、十六夜さんの言葉を待った。 十六夜さんは思惟の時を持ち、やがて淡々とした口調で語りだす。不思議な少女の、正体を。 「一年前、千咲は死にかけたの」 「え……」 「……死、にかけた?」 開口早々の十六夜さんの突飛な発言に、私達は目を丸めていた。 十六夜さんは私達の反応に小さく頷くのみで、構わずに話を続ける。 「一年前、あの子は大きな事故に巻き込まれた。身体中に怪我を幾つも負って、脳にすら損傷が及んでいたわ。病院に委ねたとしても、間違いなく死に至る程の大怪我だったの。……だから、私が治したのよ」 治した?治したって……十六夜さんは科学者さんであって、お医者さんではないはずだ。 想像を絶する話に、私は返す言葉もなく十六夜さんの言葉に耳を傾けた。 「医学というのは、投薬や手術によって人間を治すもの。とすれば私が行なったのは、医学を凌駕したものと言えるのかもしれないわ。先ほど、私が治したと言ったけれど、千咲は治すことなど出来ないレベルの損傷を受けていた。だから私は――新しく、作ったの。」 「それ、って……」 杏子さんも、こんな話が出てくるとは思わなかったのだろう。驚きを隠せぬ様子で、先を急かすように呟いた。十六夜さんは表情もなく、淡々と言葉を続けていく。 「千咲に行なったのは、人体改造。機械を埋め込むことによって生命器官を継続させる禁術よ。」 「じゃ、じゃあ千咲ちゃんって、……改造人間、ってことになるんですか」 「そういうことね。現実的な話には聞こえないかもしれないけれど、これは事実なの」 「……はぁ」 と、杏子さんが漏らした感嘆の声、緊張感のないその声が滑稽に思える程に、十六夜さんが語ったことが、とんでもないお話だということぐらいは私にも理解出来る。 人体改造。人間の身体に機械を埋め込む。人造人間。 あの千咲ちゃんが?……人間であって、人間ではない、存在? 「で、でもその……成功、してるんです、よね……?」 私は小声で口を挟んだ。今まで聞いた内容が、良いのか悪いのかの次元で考えてみた時に、私にはその判断が出来なかった。やはりそれは――人の為になったのならば、良い、ということになるのか。 しかし返された答えは、良いこと、とは断定できぬ曖昧なものだった。 「……成功している、とは言い切れない」 十六夜さんは少し重たい口調で言ってから、ふっと言葉を止めて手を伸ばす。小さな机に無造作に置かれていた煙草の箱から一本の白い煙草を取り出し、赤い唇に緩く咥えた。白と赤のコントラストが鮮やかで、少しだけ彼女の口元に見惚れてしまった。 シュ、と火が付いて、赤が点る。 ほんの数秒のじれったい間を置いてから、煙を吐き出し、そして十六夜さんは言った。 「失敗とも言い切れない。……現段階ではまだ、結果が出ていないわ」 煙草のフィルターを唇に寄せようとし、ふと止める。彼女は唇に軽く煙草を触れさせたままでこう続けた。 「貴女達が見た千咲……年齢に不相応な、精神的に未熟な千咲。あれはね、千咲の記憶が呼び起こせていないからなの。今はまだ幼い頃の記憶しか残っていない。だから……」 「あんなに幼い感じがするんですね……」 杏子さんがぽつりと続ける。私よりも先に納得したのか、「そっか」と小さく呟いて。 私は十六夜さんの言うことが現実離れしすぎているように思えて、未だに納得に至っていない。だけどそれが事実と言われた以上は、納得する他ないのだろう。 ついさっき、初めて言葉を交わしたばかりの少女。私は千咲ちゃんという人間そのものに殆ど触れることもなく、十六夜さんから真実を聞いてしまった。だから、先ほどの少女の姿と、十六夜さんの話す千咲という少女の姿が、今一つ合致せずにいた。 本当の千咲ちゃんって、一体どんな子なのだろう。 もしも「成功」したならば、私達は本当の千咲ちゃんに会うことが出来るのだろうか――? 「……千咲」 静まり返った部屋の中で、ぽつりと少女の名を呼んだ。 薄暗い室内、奥へと歩けば、ベッドに身を横たえて眠る千咲の姿が目に映る。 安らかな寝息を漏らして熟睡している少女。こうして見ると、ごく普通の少女なのに。 私―――珠十六夜―――は久々に戻った部屋で、久々に自分のベッドに腰を下ろす。先ほどの二人、高村さんと飯島さんが制御室を後にしてから然程経たぬうちに、私も制御室を出て私と千咲の個室へと足を向けた。ここのところ制御室に入り浸っていてろくに睡眠も取っていなかったし、いい加減身体が悲鳴を上げている。こんな時間から子どもと一緒に眠りにつくなんて、なんだか少し情けない気もするのだけれど。 「イザ、ヨイ」 眠っているはずの千咲が私の名を呼ぶ。目を遣れば、千咲は目を瞑って寝息を漏らしているし、今のはおそらく寝言だったのだろう。少しの間千咲の姿を見つめた後で、私はふっと息を吐いた。 この少女のための研究を始めてから、既に一年が経とうとしている。その長い労働に値する報酬は、既に千咲の両親から貰っていた。前金で百五十万。そして――千咲の両親が死亡した時に下りた保険金、二人合わせて一億円。その殆どをつぎ込んで、千咲の研究に長い時間を費やして。 ようやくここまで来たのに。……後、少しなのに。 「千咲――もしも、貴女が」 立ち上がり、千咲が身を横たえるベッドに軽く腰を掛けた。 千咲の寝顔には何の翳りもない、少女らしい、無邪気な寝顔。 だけどこの子にだって十五年という長い人生があったはずだ。 事故の後、一年間は眠っていたも同然だが、それでもやはり十四年。 私の知らない十四年間が、この少女の中に眠っている。 私の知らない千咲が、千咲の中に眠っている。 もしその千咲が目を覚ましたら、私は――― 「……危うい、かしら?」 答えを持たぬ少女に投げ掛けて、一人で微かな空笑いを漏らす。 私が知っている千咲は、幼い頃の記憶しか持たぬ千咲。 以前、千咲の両親から聞いた十五歳の千咲。 それは今の千咲とは別人のように、残酷だという。 本当の千咲が目を覚ました時に―― きっと、この幼さなど、泡沫のように消えてしまうことだろう。 『金出すか、死ぬか。選択肢、二個しかないから』 鋭いナイフを向けて、千咲は薄く笑う。 ピンク色に染めた髪をふわりと揺らして、首を傾げる。 『金ぐらい出せるでしょ?……それとも死にたいのかな?』 ナイフの切っ先は怯えきった少女に向けられ、冷たい刀身が少女の頬を打つ。 少女は唇を震わせるばかりで、言葉を発そうとはしない。 『知ってる?チサ、本気で言ってるんだよ』 千咲はクスクスと笑いながら、ぐっと少女の前髪を掴み上げた。 涙を溜めた瞳で千咲を見上げる少女を、千咲は冷たく一瞥する。 そしてナイフの切っ先が、少女の頬に深い傷を刻みつけた。 『痛い?ねぇ痛い?キャハハハ!』 高らかな笑い声は止むことがない。 叫びにもならぬ声を上げてその場に倒れこむ少女に、千咲は加減を知らぬ蹴りを叩き込む。 血塗れになった唇で、少女は掠れた声を漏らした。『……お金、払うから、許し、て』 『……許して?』 千咲は少女の顔を覗き込み、頬を裂く傷口に指を触れさせる。 傷を抉るように力を加え、溢れて来る血液を眺めて笑った。 『許して下さいって言え。礼儀を知らないやつだなぁ』 クスクスと笑いながら、言葉を改める少女の言葉を耳にした。 少女が震える手で、ポケットから紙幣の覗く財布を取り出し千咲に差し出す。 千咲はそれを受け取ると、また小さな笑みを浮かべ、立ち去った。 悪魔の仔。 そんな異名を持つ不良グループが存在していた。 地方都市を拠点として暴れ回る少年少女。千咲もその一員だった。 悪魔の子ども達は、恐喝や窃盗、或いは暴行や傷害と、傍若無人の限りを尽くす。 子ども故に手加減を知らず、子ども故に罪から逃れた。 身寄りのない子どもや、教育を知らぬ子どもが多く所属していたが、千咲は違った。 千咲の両親はそれなりに裕福で、千咲自身も中学校にも通っていた。他のメンバーよりも裕福であった千咲は、仲間達の食い扶ちを賄う代わりにグループ内で権力を手にしていた。 千咲の両親は、千咲が不良グループの所属していることも知っていたし、千咲の悪事も知っていた。けれどその全てに目を瞑っていた。理由は単純だ。―――娘を、溺愛していたから。 そうして悪行三昧の日々を送っていたある時、千咲は、事故によって瀕死の状況に追い込まれることとなる。千咲が十四歳の誕生日を迎えた数日後のことだった。 不良グループの仲間達は、誰一人として見舞いには来なかった。果てにはこんなことまで囁かれた。 『罰が当たったんだ。あれだけ酷いことをしていれば当然だ』。 その後、千咲は死んだという噂が広まり、今ではそれを信じぬ者はいない。 だけど千咲は生きていた。娘を溺愛する両親の措置によって、千咲は一命を取り止めた。 千咲の両親が死亡したのは、千咲の事故から数ヵ月後。二人は交通事故によって命を落としたことになっているが、実際の真意は定かではない。ただ残ったのは、千咲が死んだという偽りの情報と、そして名も知れぬ科学者の元に渡ったという多額の保険金のみだ。 ―――米倉千咲。 彼女の存在は薄れ、少女の目覚めを待っている者は一人もいない。 私を――この手で千咲の身体を修復した科学者である珠十六夜を、除いては。 「だけどね、千咲……」 未だ、安らかな寝息を漏らす千咲の髪を緩く撫ぜながら、独り言にも似た言葉を呟く。 私は何のために、この少女を修復したのか。それは報酬のためであり、研究のためだ。 私が欲しいのは研究の成果であり、本来の人格すら知らぬ少女の目覚めを待ち望めるわけもない。 千咲の両親が淡々と話していた、この少女の本性。――その残虐性。 私は心のどこかで恐れている。千咲という少女の本性を。 「……貴女を目覚めさせることは、道徳的に考えれば、必要のないことなのよ」 もう、この少女を迎える人物なんていないのに。 可哀相な少女。今や千咲は、私の研究材料と言っても過言ではないだろう。 だけど私は研究のために、この少女を目覚めさせなければならない。 そして千咲が目覚めれば後はもう――千咲は、用なしなのだ。 その事実に良心が痛む。 いっそ今のまま、幼い千咲のままであれたら、人々にも受け入れられるかもしれないのに。 この施設に残酷な人間は相応しくない。保護に値しない。 科学者として、そして人間としての葛藤に苛まれ、溜息を吐いた。 葛藤の結果は薄っすらと見えている。―――私だって残酷な人間だもの。 この少女の痛みに代えてでも、手に入れたいものがある。 「十六夜さぁーん……?」 制御室のインターフォンを何度押しても、反応がない。 私―――乾千景―――は少し待った後、連打とかもしてみるのだがやはり反応がない。 どうしようかと首を捻った後、私は恐る恐る入り口の開閉ボタンを押した。 室内に人がいればロックが掛かり、内側からしか開けられない仕組みになっている制御室。しかし今回は、フゥゥン、と空気を圧すような独特の音がして自動扉が開いていた。ってことは、やはり十六夜さんは不在ということだ。 室内に足を踏み入れて、軽く見渡す。前にもちらっと訪れたことはあったけど、相変わらずわけのわからない機械が並んでいて眩暈がしそう。一応、ここの機械は自動制御になっているとのことだけど、もしもの時には十六夜さんがいないことには話にならないだろう。 制御室を訪れたのは、この地下施設に人が出入りした時に残るデータを見せてもらうためだった。最近、無断外出が非常に多くて困っている。和葉ちゃんとか都とか都とか都とか。厳しく注意するために、証拠を用意しようと思ったわけ。 しかし十六夜さんがいないんじゃどうしようもないかな、と思いつつも、好奇心のままに奥へ進む。確か先日データを見せて貰った時は、一番奥にある大きな機械の画面だったような気が。 「……んーと」 一番奥までやって来て、顎に指を当てつつ様々な機械を見渡す。そしてど真ん中にドドンッと置かれている機械の画面に、目的のデータを発見した。 『2101.01.09. PM13:19 01名の入室を確認 現在の在室人数・15名。 施設内の全機能を作動中。』 最新の入出情報はこれになるんだろう。十三時十九分って言ったら、確か佳乃と伊純が帰って来た頃か。 あれから二時間ちょっと経ったわけだけど……佳乃、少しは落ち着いただろうか。 廊下で伊純に会った後、佳乃が休んでいるはずの私と佳乃の個室に戻ったけれど、部屋に佳乃はいなかった。心配になって探していれば、冴月と遼のコンビに会って。 『佳乃ちゃんなら、伊純ちゃんの部屋に入ってくとこ見たよぉ』と、意味深な笑いを含ませながら言っていた。 その様子で大体のことは察する。やっぱり佳乃は伊純のこと、頼りにしてるみたいだから。 私がいなくても……大丈夫なのよね。 「……」 佳乃のことを考えていると、ふっと息が詰まるような苦しさが襲う。 伊純と佳乃。想像もしなかった組み合わせをぼんやりと思い浮かべれば、苦悩は加速する。 何故、佳乃の隣にいるのは私じゃなくて、伊純なんだろう。 ずっとずっと、佳乃の面倒を見てきたのは私なのに。それなのに……。 ――ポーン。 不意に鳴り響いたチャイムに慌てて辺りを見回して、何事かとうろたえる。そしてテレビ電話みたいな物のランプが点滅していることに気付いた。あ、これインターフォンか。ビックリした。 「はーい」 受話器を取って応えると、画面に映し出されたのは意外な人物だった。 向こうも意外そうな顔で瞬いた後、「あ」と声を上げる。 『あ、あ、あの、千景さん、えっと、十六夜さんいらっしゃいますか?』 と、相変わらず挙動不審な未姫さんだった。 「いや、それが……私も十六夜さんに用があって来たんだけど、今いないみたいなの。入る?」 『あー……そうなのですか。えっと、はい、入ります』 未姫さんは躊躇するようにきょろきょろと左右を見回しつつも、こくこくと頷く。見回すのと頷くの、どっちか一つにしたらいいのに。未姫さんの様子になんだか和みつつ、扉のロック解除ボタンを押した。 自動扉が開いて、「お邪魔します……」と未姫さんは制御室に足を踏み入れた。 「どうぞどうぞ。お構いも出来ませんが」 別に私の部屋でもないんだけど、お決まりの台詞を言いつつ未姫さんを迎え入れる。未姫さんは私のそばまでやってくると、ゆるりと首を傾げ、ぽむ、と手を打った。 「十六夜さんに用事……というか、用事……うぅん……千咲ちゃんのお話をしたかったんです」 と、未姫さんの言葉は少し意外だった。そもそも未姫さんが十六夜さんに用事っていう時点で意外だし、更に彼女の口から千咲ちゃんの名前が出てくるとも思わない。千咲ちゃんって言ったら、私ですら調書の日以来一度も会っていないレアな人物だ。 「未姫さん、千咲ちゃんと会ったの?」 「あ……はい、つい先ほど。廊下で。」 「へぇ。どんな様子だった?」 「え、と。……ピンクの髪が可愛かった、です」 「……な、なるほど」 妙なテンポで告げられた言葉に、とりあえず頷き返す。納得……したようなしてないような。 千咲ちゃんって調書の時に寝てたのよね。だから一度も話したことがない。千咲ちゃんの声を聞いたのは一度きり。この地下施設へのパスワード、『センソウ』と呟いた、その一言だけだ。 千咲ちゃんも色々と謎に満ちた女の子だけど……それを言えば、保護者の十六夜さんだってミステリアスよね。正直なところ、ちょっと危ないマッドサイエンティストぐらいにしか思ってなかったけど。 ――待てよ。 ミステリアスの話ならば、私は一番大事な人を忘れていやしないか。そう、目の前にいるこの人。 未姫さんこそが究極のミステリアス……のような気が、する。 PTSDの病気とか、そういう部分とはまた別の次元で、不思議ちゃんというか。 「……?」 未姫さんは私の視線を感じてか、不思議そうに瞬きながら首を傾げた。 十六夜さんも帰ってこないことだし、少し未姫さんのことについても聞いてみようか。 「あのさ、未姫さんって……」 「は、はい」 「…………」 聞いてみるって、どう聞けば良い、のか。 未姫さんって不思議ちゃん?……いやいや、それじゃあまりにストレートすぎる。 未姫さんってどういう環境で育ったの?……いやいや、でも家族亡くしてるからNGよね。 未姫さんってどんな地質が好き?……いやいや、聞いてどうするよ私。 「ど、どうかなさいましたか?」 動きを停止して考え込んでいる私に、未姫さんは慌てた様子で言った。 私はぶんぶかと首を横に振り、 「いや、その、えっと……未姫さんって、こ、恋人とかいたのかなぁ?」 と、苦し紛れに思いついた問いかけを放っていた。 未姫さんはそんな私の問いに、きょとんとして固まった後、「あれ」と小さく呟く。 「……言いません、でした?……旦那が、いたんです、けど」 「………………え?」 「その、だから……死別した、家族っていうのが……」 「えええええぇぇっ!!?」 ちょ、ちょちょ、ちょっと待って!聞いてないっっ! だ、だ、だだ、旦那!?結婚してたの!? 私の混乱を他所に、未姫さんはきょとんとしたままで「言うの忘れてた、かも、です」などと呟く。 「い、いやっ、忘れないでそれは!……じゃあ何、未姫さんって……未亡人?」 恐る恐る掛けた問いかけに、未姫さんは暫し私を見つめて押し黙った後、こくん、と頷いた。 ま、マジっすか……。 「……千景さん」 「は、はい?」 「言い忘れてたの……まずかった、ですか……?」 未姫さんは泣きそうな顔をして、少しだけ低い視点から私を見上げる。 ぐすん、と鼻を啜ってから、その瞳に涙を溜め――いやいやいや。 「未姫さん、べ、別にいいから!気にしなくていいからっ。だから泣かないで、いや本当、泣くことじゃないからそれは。ね?」 と慌てて慰めると、未姫さんはまたぐすんと鼻を啜り、「ごめんなさい」と小さく呟く。 「……ショウマっていう、人」 「ショウマ?」 「……私の旦那さん、だった人、です」 「あ……」 そ、うか。未姫さんは言い忘れてたことを気にして泣きそうになってるんじゃなくて―― 死別した旦那のこと、思い出しちゃったのか。 「……ごめんなさ、い……忘れなきゃって、思うのに……」 未姫さんは悲しげに目を細め、ふっと私から目を逸らした。 そして力が抜けるようにぺたんとその場に座り込み、冷たそうな機械に背を凭せ掛ける。 堪えるように唇を噛んで、震える手をぎゅっと握って、目を伏せて。 未姫さんって睫毛が長くって、目ぇ伏せると、そのシルエットがすごく綺麗だったりする。 「大丈夫よ。……なんていうか、うん」 こういう時、すぐに別の人が見つかる、なんていう言葉は禁句だろうか。 だけどそれが私の本心だ。未姫さんって綺麗だし――それは、顔だけじゃなくて、 心も綺麗な人だと、思うし。 だからすぐに、未姫さんのこと想ってくれる人、見つかると確信出来る。 「でも、千景さん……私、PTSDなんか患ってる……それに、人とお話しするの、下手だし……こんな私は、ショウマみたいな優しい人じゃないと、きっと……」 ずっとフロアに目を落としたまま、未姫さんは悲しげに紡ぐ。 そんな姿、見てられなくて、私は彼女の前にしゃがみ込んだ。 「卑下しないの。未姫さんなら大丈夫だって。……きっとまた、未姫さんのこと想ってくれる人が」 「現れる、……って、言えます、か?」 「……うん。そう言いたい。」 疑心すら滲んだ視線で、未姫さんは私を見つめた。 私は嘘なんかちっとも言ってない。だから真っ直ぐに未姫さんを見つめ返す。 彼女には少しだけ自信が足りないのかもしれない。もっと自分を信じれば、もっと素敵になれるのに。 「嘘……」 未姫さんは私の視線を受け入れてくれなかった。すっと目を逸らし、俯いて首を横に振る。 頑なに心を閉ざす未姫さんに焦れて、私は少し強引に彼女の肩に手を置いた。 距離を縮めて、驚いたように私を見る未姫さんを、改めて見据え直す。 「話聞くときは相手の目を見なさい。私だってこんなに真剣に言ってるんだから、信じてよ」 「……あ、……ご、ごめんなさい」 私の少し厳しい言い方に、未姫さんは怯えたように身を縮めた。だけど私の言葉はちゃんと受け止めてくれた。ぎこちなく私を見つめ返し、「ありがとうございます」と小さく言った。 少しの沈黙の後、未姫さんの細い指先がきゅっと私の両腕を掴む。一瞬、嫌がられているのかと思って身を引こうとしたが、未姫さんは私の腕を掴んだままで押すことも引くこともしなかった。 「……未姫さん?どした?」 堪えきれぬように俯いて、微かに身体を震わせる。そんな様子に、私は小さく言葉を掛けた。 未姫さんは押し黙ったまま。だけど私を掴んだ手だけは決して離さずに、数十秒の間を置いた。 「――怖い、です」 やがてぽつりと言葉を漏らしながら顔を上げ、未姫さんは濡れた双眸で私を見上げた。頬を伝った涙の跡が、幾筋も残っている。一体何に怯えているのかと、私は彼女に身を任せたままで言葉を待った。 「心を許したら、また……恐怖が加速する。……失ったらもう、戻って来ないのに……」 「……失うことに怯えて、何も出来ないのね」 「……」 彼女の恐怖の理由は、誰しもに付き纏うものと言えるだろう。 出会いがあれば別れがある。永遠なんて存在しない。 ただ――未姫さんはその別れを、あまりに早くに経験しすぎてしまった。 まだ私と同い年なのに。愛する人を失って、その悲しみに染まりすぎて。 人を愛することに、怯えてしまっているのだろう。 「でもね。別れがあるから出会いもあるのよ。……最初から別れを怯えてたら、一人で辛いだけじゃない」 「……はい」 「わかってるのよね?……ただ、踏み切れないだけ。そうなんでしょ?」 静かに告げる問いかけに、未姫さんは小さく頷いた。 ――出会いなんて、既に終わってるはずなのにね。 私がこうやって未姫さんと話してるのは、未姫さんと出会ったからだ。 警察管理下の避難という状況で、奇しくも十四名――米兵のMinaも合わせれば十五名の女性が出会って、同じ施設で暮らすようになって。まだお互いによく知らない同士ばっかりだけど、きっとこれから少しずつ深く知り合っていくことになるだろう。 未姫さんにだって、杏子さんを始めとして、十六夜さんとか遼や冴月とか。今はまだ言葉を交わしただけの知り合いでしかないかもしれないけど、これから親しくなっていく人々だろうし、あ、もちろん私もね。 出会いは終わってる。いつかは別れることが決まってる。 だけど、未姫さんはまだ怯えている。――もう一つの出会いに? 「私が出会っちゃだめ?……無理矢理、奪ってもいい?」 「……千景、さん?」 私の中ではまだ漠然とした、未姫さんの「出会い」の定義。 曖昧に問い掛けたら、未姫さんはきょとんとして私を見つめ、少しだけ頬を赤くする。 やっぱ、恋愛云々は含むものなのかな、これ。 ……。 少しだけ自棄も混じってるのかもしれない。 佳乃の顔がふっと浮かんだけど、すぐに掻き消して未姫さんを見据える。 ほんの数センチの距離で見つめ合って、私までなんだか照れてしまう。 「いいのよね……?」 胸の中には微かな自責。犯そうとしている罪が理解できているはずなのに。 嫉妬から逃避して、佳乃に対する想いを放置して、私は未姫さんに手を伸ばす。 こうすれば、誰も、傷つかないような気がして。 未姫さんだって、きっと、私に委ねてくれるから。 そっと彼女の肩に手を置いて、引き寄せた。 「……千景さん」 未姫さんは躊躇いを断ち切るように私の名前を呼んでから、儚い微笑みを見せる。 彼女の表情に胸が締め付けられるけれど、私はもう、未姫さんのことを求めてしまった。 そして未姫さんの答えもまた、私を拒絶するものではなかった。 華奢な身体が、私の胸元に寄せられる。 未姫さんの額が私の鎖骨に触れて、一度だけ私を見上げた後、ふわりと身体を密着させた。 まるで心音を聴くように、彼女は深く私に凭れ、身を委ねる。 「こんなふうに、なるなんて」 未姫さんはぽつりと呟いた。声に感情は滲まずに、ただ零すような一言を。 私は何も言えず、未姫さんの不思議な髪色に指先を滑らせた。 赤いビーズが指に絡み、纏いつく。まるで今の関係のようだと思った。 解けばすぐに、零れ落ちてしまうだろう。 だけど私と未姫さんは、互いに動かず、相手の存在を捕らえたまま―――離さない。 |