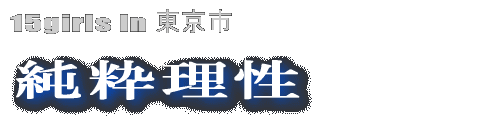
|
荒涼とした道を行く。 お昼間の東京市、相変わらず灰色の景色ではあるけれど、今日は天気が良い方だ。 薄っすらとかかった雲霧の向こうには、ぼんやりと太陽が浮かんでいる。 今、私―――伴都―――達が歩いている場所は、災害の被害もそう酷くはなかったのだろう。アスファルトはそれなりに綺麗だし、周りにぽつぽつと建っている建物も荒れ果てているといった風ではない。寧ろ人の気配すらするんだし、この辺は賑わっている場所とも言うことが出来る。 本日は和葉ちゃんの付き添いで内密外出、可愛い女の子との嬉し楽しい内密デート。本来の目的は和葉ちゃんの勤務先に赴いて、彼女の同僚さん達を保護するってことなんだけど。 和葉ちゃんに案内されて、例の地下施設から歩くこと三十分。それほど遠くもないが近くもない、そんな場所に和葉ちゃんが勤めていたお店はあるらしい。 「怪盗Happyさんも、のんびり歩いたりするんですね」 隣を歩く和葉ちゃんが、感心したような口調で切り出した。 その言葉に思わず吹き出して「そりゃそうよ」と頷いて見せる。 「バイクで飛ばしてもいいけど、たまにはのんびりお散歩気分になりたくなるのも人間の性でしょ?」 「あはは、そうなんですか?私はいっつも徒歩通勤でしたから」 ……まぁ実のところ、和葉ちゃんとデートってことで敢えて徒歩を選んだってのもあるんだけど。 Happy特製の簡易飛行機で和葉ちゃんと空中デートなんかも良いかなぁとは思った。しかし飛行機だと、ビューンと飛んでお終いだし、ついでに言うとすごく寒いし。徒歩ならば話す時間もたっぷりあるし、寄り添えば温かい。というわけで、やっぱり徒歩の方がデート向けなのだ。 「でも歩いてる人少ないですね……お昼間だからかな。夜になったらもうちょっと賑やかなんですよ、この辺」 「そうなの?この辺って、やっぱアレ?有楽町みたいな場所になるの?」 「そうですねー……そういうお店、多いですね」 やはり働いていただけあって、土地鑑に関しては和葉ちゃんには負ける。 ぱっと見た感じも怪しげな一帯ではあるけれど、ただ通りかかっただけじゃ“そういうお店”に辿りつくことはないだろう。ある程度情報通じゃなきゃいけない、ってことか。 「あ、こっちですー。この建物の地下にあるんですよ」 和葉ちゃんは前方の建物を指差すと、少し足を速めて入り口の方へと向かって行く。 ……って、こう、外から見た感じは“そういうお店”があるようには思えないんだけど。 パッと見はオフィスビルか。よくよく見ると建物の壁面に“そういう広告”が貼り付けてあったりもするけれど、これは普通、気付かない。 わたくし怪盗Happyこと伴都、かれこれ二十五年間生きて参りましたが、こういう「イヤーンバカーン」なお店に足を踏み入れるのは初めてです。まぁ今回もお客さんじゃないけどね。じゃないけどねッ。 足早に地下に続く階段を下りていく和葉ちゃんを慌てて追いかける。この子、職場に戻って来たからってはしゃいでるみたいだけど、危険はどこにでも潜んでいるものだ。 地下に下り、通路を少し歩いた先に幾つかの看板と扉があった。なるほど、“そういうお店”ってのはこうやって密集して存在してるものなのね。思わず顔を赤くしてしまいそうな店名が並んでいる。 和葉ちゃんが所属してるのが『若妻みぐい』とかだったらやだなぁ。っていうか妻じゃないか。 「あ、ここです、ここ。」 「どこ!?」 「……ここ、です」 私の剣幕に気付いてか、和葉ちゃんはどこかばつの悪そうな表情でお店の看板を小さく指差す。 『ぷにぷに☆メイドハート』 ……。 …………。 ……………まぁ。 「あ、あ、あの、都さん?……怒りますか?」 「え!?い、いや、いいと思うわよメイド!うん、ぷにぷに?」 「……。」 思わず顔を赤くする私に、和葉ちゃんも赤くなりながら目を逸らして俯いた。 気まずい。 別に風俗云々を批判する気は全くないし、人間の欲求を満たす場なのだから商売としても成り立っている。需要と供給のバランスも良いんだと思うし、メイド、世の中はやはり需要があるものを供給するのが商売の基本メイドであるからして、そういったメイド職場で働くことによりメイド給与を得るメイドということはメイド世の中にメイド貢献しつつメイド、自らのメイド食い扶ちも得てメイドいるということになるメイドわけでメイド、つまり素晴らしいメイドだと思う。 …………。 和葉ちゃんがメイドさん……可愛いだろうなぁ……。 「み、都さん、早く中に入りましょうよ……」 「ハッ。あ、ごめんごめん」 思わず直立不動で考え込んでいた私は、和葉ちゃんの声でようやく我に返る。 いけないいけない。私としたことがたかがメイドさんで心を乱すなんて。 自らを叱咤するようにペチペチと頬を叩いてから、そっとお店の扉に手を掛ける。 ドアノブを握り恐る恐る引くと、何の抵抗もなく扉は開いていた。 あぁやっぱりこういうお店でも「いらっしゃいませ」なのかしら。それともメイドだから「お帰りなさいませご主人様」になるのかしら。そんな疑問を抱きながら扉を開き、中に足を踏み入れ、た。 「…………」 「…………」 しかし、「いらっしゃいませ」も「お帰りなさいませ」もなにもない。 店内は静寂に包まれていた。 奥へ続く通路と、無人のフロントと、女の子の写真が貼り付けられたボード。 和葉ちゃんの写真を探したい気もしたのだが、それよりも―――この、異様な雰囲気。 「おかしいなぁ。この時間は営業してるはずだし、フロントに誰もいないなんて……」 そんな和葉ちゃんの呟きを耳にして、私の推測は確信にすら変わっていった。 和葉ちゃんにはわからないだろう。この異様な雰囲気が何を意味しているのかを。 残念ながら、私がメイドさんを目にすることは出来ないようだ。……生きているメイドさんは。 「和葉ちゃん、ちょっとここで待ってなさい。いいわね?」 「あ、はい」 私は和葉ちゃんに言いつけて、フロントを飛び越えた。おそらくこの奥に事務所なんかがあるのだろう。 不安げに私を見送る和葉ちゃんをちらりと見遣った後、私は真っ直ぐに奥の部屋に向かって行く。 フロントから少し入れば、簡素なコンクリートの打ちっぱなしの狭い廊下が続いていた。 少し鼻を利かせると、案の定。―――この匂い、いわゆる死臭というものだ。 匂いは奥に進めば進むほどきつくなる。むせ返るような匂いに堪えながら、一番奥の扉を開いた。 私は目に飛び込んできた光景に、思わず顔を顰めていた。 十二畳ほどのそれなりに広い部屋、室内にはデスクや本棚といった事務所らしい物が揃っている。 その部屋の中央、接客用のソファに横たわった亡き骸が、二つ。 金庫が荒らされているところを見ると、金銭目的の強盗といったところ。犯人は日本人なのか否か、それすらもわからないが―――とにかく、この二つの亡き骸は和葉ちゃんが言っていた「店長さん」や「同僚さん」であることに間違いはないだろう。死体の一体は羽振りの良さそうな男のもの、そしてもう一体はメイドさんのコスチュームに身を包んだ若い女のものだった。 私はすぐに踵を返し、和葉ちゃんが待っている入り口の方へと急ぐ。今の二人が殺されてから時間は経っているようだけど、油断は出来ない。ここは安全な場所とは言い難かった。 「和葉ちゃんッ」 フロントに出てすぐ、フロントの中でうずくまってなにやらごそごそしている和葉ちゃんの姿があった。 「あ……どうでしたか?」 和葉ちゃんはしゃがみ込んだまま私を見上げ、低いトーンで問い掛けた。その様子からして、和葉ちゃんも何かを察してはいるのだろう。ふと気付けば、フロントにあるレジにも無理矢理抉じ開けたような跡がある。 「四十代ぐらいの男性と、若い女の子。……随分前に、息絶えたみたいだった」 「……そうですか」 和葉ちゃんは俯いて、悲しげにふっと息を吐く。 微かに震えるその背中に、私は掛ける言葉を持っていなかった。 「一週間前に出勤した時は、皆、元気だったんです。」 「そう……」 「でも、米軍の人とトラブルになってるとも聞いて……だから私、怖くて。お休みしてたんです。」 和葉ちゃんは淡々とした口調で紡ぎながら、突然、身につけていた上着を脱ぎ出した。 「和葉ちゃん……?」 「どうして皆、争うんでしょう。……お金なんかのために、憎しみなんかのために、殺したりするんでしょうね」 そうして和葉ちゃんは、フロントの下の棚から取り出した何かを――このお店の制服を、身につける。 丈の短いワンピースに、フリルエプロン。白いフリルのカチューシャをつけ、手首には同じくフリルのカフス。 パチン、とボタンを留めてから、和葉ちゃんは私に向き直り、スカートの裾を握って微笑んだ。 「可愛いでしょう?」 「……うん。」 確かに、メイドさんの制服に身を包んだ和葉ちゃんは文句のつけどころがないレベルで可愛かった。 こんな時に、不謹慎だと思うけど――お互い様か。 「都さん。私達は、お客様に喜んで頂くためにお仕事をしてたんです。お客様が嬉しかったって言ってくれることが、私も嬉しかった。……なのに。こんなところにも、憎しみは生まれるんですね」 和葉ちゃんは悲しげに言って、何かに堪えるように俯いた。きゅっと唇を噛んで、微かに身体を震わせて。 私はそんな和葉ちゃんをただ見つめることしか出来なくて、そんな不甲斐ない自分に呆れていた。 「……都、さん」 やがて顔を上げた和葉ちゃんは、無理矢理作ったような笑顔を私に向けた。 そして私の手を取ると、強引に歩き出し、客室の方へと向かって行く。 可愛い衣装に身を包んで、目一杯の笑顔を振り撒いて、私の手を引いて。 意外な一面を見た、とも思うけれど、和葉ちゃんらしいとも思う。何とも言えない気分だった。 客室の方には被害は及ばなかったのだろう、静まり返った廊下を奥へ奥へと進んでいく。 「和葉ちゃん……自棄になっちゃ、だめよ?」 ぽつりと、彼女の背中に投げ掛けた。 本当は悲しいはずなのに、本当は苦しいはずなのに、それでも和葉ちゃんは笑ってる。 そんな笑顔を見ていると、なんだか切なくて。 「……ご心配なさらないで下さい。私は大丈夫です。――ご主人様。」 微笑んで告げられた言葉に、私はようやく理解した。 和葉ちゃんはお仕事がしたいんだ。おそらく最後になるであろう、お仕事を。 それなら私は、お客様として、素直に彼女の奉仕を受け入れても良いのだろうか。 和葉ちゃんが求めてるもの、私が与えることなんて出来るだろうか。 「こちらになります。……さぁ、どうぞ」 和葉ちゃんは一室の扉を開き、私を促した。 中は狭い部屋だった。あるのはシャワールームとベッド、たったそれだけの空間。 この空間には、他に必要なものなんてないんだ。 欲望を吐き捨てるだけのために存在する空間。お金と引き換えに、情欲を貪る空間。 それは醜い世界だと思っていた。……だけど。 「何なりとお申し付け下さい。」 和葉ちゃんは深々と頭を下げた後、嬉しそうに笑んで見せた。 この子が、そんな醜い世界にいるとは、思えない。 和葉ちゃんはもっと純粋なところで生きている。 相手を喜ばせたい、相手に笑って欲しい、そんな想いを抱いて。 「和葉ちゃん……」 私はそっと和葉ちゃんを引き寄せ、その肩に手を置いた。 和葉ちゃんは真っ直ぐな笑みを向け「はいっ」と従順な返事を紡ぐ。 この子は、私が喜んだら――嬉しい? 「……キス、してもいい?」 「はい……」 柔らかい表情で頷いてくれる和葉ちゃんに、「可愛い」と囁いて、 彼女の唇に、そっと、自らの唇を寄せた。 久々に触れた、他人の唇。 その時にふっと頭を過ぎる、忘れかけていた喜びのような感情。 誰かと触れ合うことは嬉しいことだ。誰かとこうして体温を分かち合うことは、幸せなことだ。 もしかしたら和葉ちゃんは、そんなものが欲しくて、この仕事を選んだんじゃないかって。 見ず知らずの他人の笑顔も、喜びも、体温も―― 嬉しいと思える、純粋な心を持った女の子。 「……和葉ちゃんのこと、抱きたい」 「はい……どうぞ、お望みのままに」 私は、その純粋な心が欲しいと、思った。 和葉ちゃんの体温が欲しくて、仕方がなかった。 だから――私は和葉ちゃんを抱いた。彼女の身体を弄んで、彼女の温度を受け入れた。 「……ご、しゅじん、さま」 喘ぎの中に混じるのは、従順に私に尽くす、どうしようもなく健気な言葉。 あぁ、この子に尽くされた客は、どんなに幸せだったことだろう。 こんなにも純粋な感情で、真っ直ぐな笑みを向けられて。 ―――どんなに、愛しかったことだろう。 「はぁ……」 お部屋のテーブルに突っ伏して、もう何度溜息を零したか。 なんとも言えない複雑な感情に、私―――高村杏子―――は太刀打ちできずにいた。 昨日の夜にセナちゃん――こと、冴月ちゃんと会ってから、ずーっとこんな感じだ。 これからのことを考えると本当に先が思いやられる。いつかはセナちゃんに私が月見夜だってことがバレて、そしたら嫌われちゃったり……するのかなぁ。うーん、やっぱりするよね、それは。 ずっと隠し通そうか。私のこと、セナちゃんにバレないように。 それも不可能じゃないと思う。だって私が月見夜だっていうことを知っている人なんてここにはいない。 でもでも、隠し事っていつかはバレちゃう運命にあったりするんだよね。 「どうしようー……」 頭を抱えて更に溜息一つ。悩んでもどうしようもないっていうのもわかるんだけど。 その時、カチャ、と小さな音がして私は顔を上げた。見れば、お部屋の入り口のところに未姫さんの姿。 三十分ぐらい前にご飯を食べに出て行ったから、お食事を終えて戻って来たのだろう。 「ただいま、です」 「おかえり、です」 どこか緊張がちに紡がれた挨拶に、少し笑って真似っこしてみた。 未姫さんは微苦笑を浮かべて私に歩み寄る。 「杏子さん、どうかしました……?」 「ふぇ?」 不思議そうな様子に、私も少しきょとんとして。その後で、私が頭を抱えて机にべったりな現状を思い出す。 「あ、ううん、なんでもないの。……うん」 ごまかすように笑って見せれば、未姫さんは不思議そうにしながらも「そう、ですか」と小さく頷く。 未姫さんに相談してもなぁ。どうしようもないよねぇ。うーん。 ぼんやりと未姫さんの姿を目で追いかけて、少しだけ小休止。考え事を続けてると疲れちゃうんだもん。 未姫さんの後ろ姿、やっぱり不思議な感じだった。彼女の独特の髪型の所為だ。右側は短い黒色、そして左は綺麗な金髪。当然、生まれた時からあんな風じゃなかったのは明らかだ。しかし彼女自身が故意にああしているとも思えない。 とすれば……彼女が事情聴取の時に話していた、核爆弾の影響と考えるのが自然だろう。放射能の被害によって神経に影響を及ぼした。その結果、あのような特殊な症状が髪に出た、だとか。そのぐらいしか私には思いつかない。 彼女は核爆弾の被害で家族を失ったと聞いた。あの爆弾による被害は今でも様々なところで続いている。彼女の髪が実際どうなのかはわからないけど――そう、未姫さんが抱えているという心の病気も、被害の一つだと言えるだろう。 「ねぇ、未姫さん」 二人きりの部屋なのに、お互いに黙り込んでいるのもなんだか変なもの。そう思って、私は未姫さんに話し掛けていた。話題は今考えていた、核爆弾の被害ぐらいしか思い浮かばないのだけれど。 「あ、……はいッ」 未姫さんってなんか、微妙な“間”があって可愛らしい。 人と話すことに慣れていないような、どぎまぎした間。だけど語彙なんかはしっかりしたもので、本当に人慣れしてないだけ、っていう感じなのかな。 「えっと、ね……」 何と、言葉を掛けたら良いだろう。核爆弾の被害のこと……と言っても。 彼女の傷を抉るようなことになってしまわないかと、そんなことがふと不安になった。 「……あ」 不意に、未姫さんが何かを思い出したように小さく声を上げる。 「えっとですね、さっき、食堂で、……うーんと」 「うん?」 「……あの、女の子。セ、……セ?」 「セ?」 「…………あ、冴月さん。そう、冴月さんとお会いしました」 あぁセナちゃんかぁ、と、心の中でギクリ。 そんな私の様子には気付かずに、未姫さんはぺたんとベッドに腰を下ろして言葉を続けた。 「昨日、杏子さんに失礼なことをしてしまった、とかで……その、ごめんなさい、と、伝えて欲しいと」 「……あ、あー」 失礼なことしちゃったのは私じゃないかなぁ。 セナちゃんにまで気を使ってもらっちゃうなんて、なんだか情けない。 思わず溜息なんか零しつつ、私はまたぺったりとテーブルに突っ伏した。 ……もう、いやぁ。 「あ、杏子さん?どうしました?」 私の様子に、未姫さんは焦ったような声を上げて立ち上がる。 なんでもない。――そんな言葉、すらも、出てこなかった。 私、なんでこんなに切羽詰っちゃってるのかな。どうしたらいいのかわからなくて、苦しくて。 セナちゃんにも悪いことしてるし、未姫さんにも心配掛けちゃうし、……ほんと、情けない。 「杏子さん……困ってることは、ちゃんと言わなくちゃだめ、です」 「……ふぇ?」 「そ、その……大事な人はいつ死んじゃうかもわかりません!」 「……う、……?」 ちょっとだけ、未姫さんの言葉の意味がわからなくてきょとんとしてしまう。 未姫さんはおずおずと私の向かい側の椅子に腰を下ろし、伏せ目がちに言葉を続ける。 「えっと……悩んでいること、一人で抱えても、解決しませんから。……悩んでいるうちに、大事な人、死んじゃうかもしれませんから。」 彼女の言っていること、やっぱりどこか的外れなようにも思える。 けど、未姫さんは真剣だ。――死んじゃうかもしれませんから、と。 それってもしかして、未姫さんの実体験と重ね合わせているのかな。 ……大事な人、死んじゃった、から? 「未姫さん……ありがと。」 私は少し笑んで見せ、ぽつりと告げた。 未姫さんはぶんぶかと首を横に振り、「とんでもないです!」と。……可愛らしい。 「でもね、私には大事な人なんていないんだよ。だから大丈夫」 そう続けると、未姫さんはどこか不思議そうな顔で私を見つめ、瞬いた。 「……大事な人なんていないから。だからね、私は失うことなんて何も」 言いかけてふと、未姫さんの悲しげな表情に、言葉が詰まる。 未姫さんは俯いて、目を伏せたままじっと押し黙っていた。 わ、私……なんか、変なこと言っちゃったかな……? 「だ、大事な人、っていうのは」 未姫さんはたどたどしい口調で切り出し、その綺麗な瞳で私を見つめる。 彼女の言い分に、私はじっと耳を傾けた。 「……失ったら物凄く、辛くて……悲しい、です。だから大事な人なんていない方が良いような気もするの、です、がッ……でも、でも、やっぱり大事な人っていうのは大事なんです……あ、えーと」 「…………」 よ、よくわからない。 首を傾げて、尚も未姫さんを見つめてみた。 未姫さんは「ごめんなさい」と呟くように謝った後、ドドンッ、と机に手を置いて言葉を続ける。 「だから、その!失うものがないのなら、怖いものなんてないはず、です。……です?……です。だから、お悩みがあるっていうことはやっぱりその、何か怖いことがあるわけで、だからつまり……」 「……あ。」 そっか。要するに私の言葉は間違ってるって言いたいんだ。 大事な人なんか、いない。それは間違いだって。 ……それは……。 「そう、なのかな。私はセナちゃんを失うことが怖いのかなぁ」 「……セナちゃん、です?」 未姫さんのきょとんとした目。 今まで出てきたことのない名前に、不思議そうな表情で。 「セナちゃん。冴月ちゃんのこと」 「……さ?セ……セナ、……冴月さんですか」 こくん。私は一個頷いてから、うーん、と考え込む。 未姫さんはやっぱり不思議そうな顔で私を見つめた後、「あ」と何かに気付いたように声を上げた。 「杏子さんの大事な人は、セナ……冴月さん、です?」 「……なのかなぁ」 「です?」 「……うーん」 「…………うーん」 二人して考え込んで、それから、ふと。 私達は何をしてるんだろう、とか、気付いてみる。 ……うーん。 「あのねぇ未姫さん……もしものお話、してもいい?」 「……は、はい。」 「未姫さんがね、例えば……メールで誰かと知り合うとするよ」 「……メール。」 「うん。それでね。そのメールの向こう側の相手と仲良くなるでしょ?」 「……はい」 「でもね、メールとかってやっぱり、実際とは違うキャラクター……みたいな感じでやりとりしちゃうと思うのね」 「……キャラクター。」 「そしたらね、相手の人は未姫さんのことをどう思う、かな。」 「……うーん。」 「それはもちろん未姫さんのメールの書き方次第だと思うんだけどね。」 「……書き方。」 「ほら、例えば、すごく頼りになるお姉さんとか、すごく美人さんとか思われたとしたら」 「……美人、さん。」 「未姫さんは実際に美人さんだからいいんだけど……。」 「……いえ、そんなことは。」 「だから、メールでお話するとの実際に会うのとってギャップがあると思うの。ね?」 「……はぁ。」 「ってことは、やっぱり相手は美化したイメージ持ってるかもしれなくて……」 「……イメージ。」 「実物の未姫さんと会った時、どう、思うかなぁ……」 「……えーと」 やっとこさで話し終え、私自身、自分の悩みを再確認。 そうなんだよ、きっとセナちゃんは私のことを美化してると思うのッ。 美人だとは言ったことないけど、頼りになるとか色々メッセンジャーで言われて来たしなぁ。 未姫さんは私の話した内容を反芻するようにぽそぽそと呟きながら考え込み、やがて顔を上げた。 「…………あのですね」 「はい。」 「私は、会わない方がいいと思います。」 「え。」 「……多分。」 「……う、うん。」 ……。 …………。 ど、どうしよう。 お話終わっちゃったよ。 私と未姫さん、しばらくの間見つめ合い、お互いに固まっていた。 先に口を開いたのは未姫さんだ。 「メールと現実は、一緒にしちゃいけない、ような気が……します。」 そう言ってまた「多分」と付け加える。 うぅん、未姫さんの言う通りかもしれないなぁ。 やっぱり、イメージ壊しちゃう。それで嫌われちゃう。だよね。 「……あ、ありがとう。」 私は小さく言って、少しだけ伏せていた目を上げ、未姫さんを見る。 未姫さんは不思議そうに瞬いては、「いえ」と首を横に振って見せた。 そっか。これが結論になるんだ。 ……私はやっぱり、セナちゃんには自分の正体を隠しておいた方が、いい。 隠し通そう。だって私、セナちゃんのこと……失いたく、ないから。 「……杏子さん」 「は、はい?」 「気をつけて下さいね」 「……う?うん」 曖昧に相槌を打ちながらふと、ぐぅ、と小さく音を立てるお腹に気付く。 私、お昼ご飯をまだ食べていなかった。 「よーし。美味しいご飯食べて、悩みなんか忘れちゃおう!」 ぽんっと手を打ち、私は椅子から立ち上がる。 未姫さんはパチパチと瞬きながら私を見上げ、それからコクンと頷いた。 「いってらっしゃい、です」 「いってきます、です」 そうしてまたまた未姫さんの真似っこをしたら、未姫さんは照れるように顔を伏せる。 可愛いなぁ、なんて思いつつ、私はお昼ご飯を食べに行くためにお部屋を後にしたのだった。 …………うぅん。 本当にあれで良かったのか、少しだけ、少しだけ疑問に思う。 杏子さん、悩んでいるようだったし、私―――飯島未姫―――が少しでも力になれたらと、そう思って……。 メール。メールで誰かとお話とか、あまりしたことがない、のだけど…… その、そういうのはあまり良くないことだと、昔、お母さんに聞いたことがあって。 何故かっていうと、メールは顔も見えないし匿名性が高いから、それを利用して騙そうとする人がいる、と。 だからだから、そういうのが危ないと思って、私、反対して……。 杏子さんの口ぶりからして、きっとあれは杏子さん自身のお話のような気が、します。 うん。杏子さんを危険に晒すわけにはいかないし、きっと間違ってないはず……。 …………あれ? じゃあ、えっと、冴月さんのお名前が出てきたのは何だったんだろう。 …………うぅん? 冴月さんは関係無い、のかな?あ、あれ? よくわからなくなっ…… 「杏子さーん。未姫さーん。」 私が椅子に座ってぼんやりと考え込んでいると、ふと、杏子さんと私の名前を呼びかける声が聞こえた。 扉の方からだ。私は慌てて席を立ち、扉へ向かう。 カチャリ、開けるとそこには婦警の千景さんの姿。 「お。未姫さん、元気?」 「あ、はい……元気です」 「あーっと、杏子さんは?」 「今、お食事に行ってます」 そうお話しすると、「あーね」と千景さんは頷いた後、廊下をきょろきょろと見回して 「ちょっと入れてくれる?」 と、小声で言った。私は何事かと思いながら、千景さんをお部屋に招き入れる。 千景さんは後ろ手に扉を閉じると、「ふぅ」と安堵したような吐息を漏らした。 「あのね……杏子さんって、……いじめっこだったりする?」 「は……?」 突然の千景さんの言葉に、私は呆気に取られて問い返していた。 千景さんは「実はね」と困ったような表情で、話し始めたのだった。 「さっき遼に言われてね。セナ……つまり、冴月が杏子さんにいじめられてるみたいなんだって。私も最初はわけわかんなかったんだけど、冴月が悩んでるのは事実みたい、でね?いじめられてるってことはないんだろうけど、杏子さんとの間でトラブルでもあったのかな、と」 「……なるほど」 そう言えばさっき食堂で冴月さんとお話した時に、隣にいた遼さんが何か言っていたような気がする。 確か……『なになに?セナってば、杏子さんと何かあったの?』 その問いかけに対し、冴月さんは……『ち、違うよ、そんなんじゃないって。』 そして遼さんは更に……『アッヤシー。さては杏子さんに何かされたなぁー?』 すると冴月さんは……『え、えええ!?な、な、何かって!いや、何かされたと言えばされた、けど、うー』 遼さんは納得したような顔で……『へぇ、あの杏子さんがねぇ。意外だなぁ』 冴月さんは困っていて……『いや、その、と、とにかく放っといて!ああ、もうー』 …………。 その会話の内容を千景さんにお話すると、千景さんは訝しげな表情で首を捻っていた。 「何かされたって……昨日のアレじゃないかな……」 「アレ、ですか?」 「昨日ね、杏子さんと都の共同戦線で、私と冴月が罠に嵌められたのよ」 「……罠。」 罠っていうと、バナナの皮とか……そんな次元……かなぁ……。 ……バナナ。 「まぁいいわ、未姫さんは何も知らないみたいだしね。お邪魔したわね」 千景さんは軽い笑みを見せ、私に背を向けて部屋を去ろうとした。 その時ふと、思い出したように振り向いて再度私に目を向ける。 「……未姫さん、例のPTSDってやつの具合、どう?」 不意の問いかけに少しだけ言葉を忘れて、具合、と首を傾げてから言葉を返す。 「今は、大丈夫です。落ち着いてます」 「ん。なら良かった。……もしも発症したら、私達にでも杏子さんにでも、すぐ言ってね?」 「は、はい。ご迷惑をお掛けします……」 言って頭を下げると、千景さんは軽い笑みを浮かべたままで首を横に振る。 「いいのいいの。未姫さんもあんまり気負わないで」 「はい……」 そうして気遣って頂けることが嬉しく、少しだけ情けなくて。 私、微妙な顔をして頷いてしまったようだ。千景さんはふっと零すような笑みの後、一歩私に近づいた。 「そうやって自分追い詰めちゃだめよ。甘える時はしっかり甘える!」 「……はぁ」 「私の胸でよければ、ドドンッと!」 千景さんは自分の胸を叩きながら言っては、ちょっと強く叩きすぎた、と咳き込みつつ笑みを深める。 彼女の笑顔は、善意のもの。建前なんかじゃなくて、心から言ってくれている言葉、というのは、彼女を見ていると伝わってくるものだ。その気持ちが嬉しくて、……でも少しだけ怖くって。 「ありがとうございます、千景さん。……ありがとう」 そう言って頭を下げながら、私はやはり彼女に甘えることなど出来ないと、実感して。 千景さんは今一つ腑に落ちないような、そんな様子で頬を掻き、「ん」と一つ頷いた。 「それじゃまたね。私は大体一号室に待機してるから、用があったら……なくてもいいから、遊びに来て?」 「はいっ。お言葉に甘え、ます。……多分」 「多分って……」 苦笑を浮かべながら扉を開き、最後にまた一つ手を振って去って行く千景さん。 見送って、やがて足音が遠ざかって。それから私は、ふっと気を抜くように息を吐き出した。 善意。甘え。大切な人。……そんなキーワード、少しだけ重たくて。 人を信じること、愛すること、求めること――それは案外、容易に抱くことの出来る感情だと思う。 だけどその感情を捨てることは容易じゃない。手に入れたものを手離すことは難しいこと。 「……また、あの人みたいに」 信じても、いつかは死んでしまうんじゃないかと、そう思うと―― 人を信じることが、とても無意味で、悲劇的に思えて、怖かった。 この施設にいることだって、本当はあまり、……。 千景さんも杏子さんも、皆、皆、私に優しくしてくれて、「甘えてもいいよ」と言ってくれて。 その度、彼女達に心を許してしまう自分が怖い。 ―――私は何故、さっき、杏子さんにあんなことを言ってしまったのだろう。 『やっぱり大事な人っていうのは大事なんです』 ……私がそんなことを言う筋合いなんてない、のに。 杏子さんの言葉に共感したのも私なのに。 『でもね、私には大事な人なんていないんだよ。だから大丈夫』 私だってもう。愛する人も死んで、家族も、何も、もう残っていなくて。 絶望の中で生きてきた。私には何もないような気がしていた。 だけど、怖かった。何かを失うことが、どうしようもなく怖かった。 まだ手に入れてもいない何かを失うことが、怖かった。 彼を――愛する人を失って、尚も私が求めているものは、何? それは。きっと。……多分、 “彼の代わりになる人物”なのだと、思う。 こんなにも貪欲に求めてる。また、私を愛してくれる人。 なのにその人を失うことが怖くって怯えている。 醜くて、情けなくて、馬鹿馬鹿しい感情だ。 ごめんなさい、ショウマ。 あなたのことを愛しているのに、裏切ろうとしている私。 どうか、許して。 杏子さん。月見夜さん。 そんな二人の人物に、あたし―――蓬莱冴月―――の思考回路は独占されまくり。 向かいの席にいる遼のことすら、どうでもよくなっちゃう。 遼が話し掛けてくる言葉も上の空、あぁごめんね遼。 「だーかーらー。セナってばあたしの話聞いてないでしょ?」 「え?あ、うん、聞いてない」 憮然とした表情でスプーンを咥えてる遼に、ようやくあたしは我に返って「ごめん」と呟く。 遼は咥えたスプーンをピコピコさせつつ、横目でちらりと、とある人物を見遣った。――杏子さんだ。 あたしと遼は、お昼過ぎの食堂で甘いパフェをぱくついていた。 この施設って個室と食堂と、あとはホールとか倉庫とか、そういうのしかないからさ、あたしたち乙女の娯楽と言えばやはり甘いスイーツになるわけだ。……というのは遼の言い分。スイーツなんて口にしたのは何年ぶりだろう。やっぱこの辺が遼ってばお嬢様だなぁと思わざるを得ない部分なわけで。 しかし実際、この施設にいると暇なのは事実だ。他にすることもないしってことで、こうやってスイーツ食べつつ遼とお喋りなんて洒落込んでいるんだけど、あたしは上の空だしね。遼も退屈そうに「セナってばー」とぼやいて、成立もしてない会話が半端に飛び交っていた、そんな時。 食堂に現れたのは、あたしの頭の中を支配している二人の片割れだった。片割れって、別に杏子さんと月見夜さんが仲間とかコンビとかってわけでもないんだけど、でも実際あたしを苛めてるのはこの二人の協力攻撃なわけだしなぁ。 片割れと言っても、ネット上だけの知り合いで顔も知らない、そんな月見夜さんなわけがない。つまりふらりと姿を現したのは杏子さんってわけ、なんだけど。……うー。 あたし、杏子さんに昨日のこと謝らなくちゃって思って。さっき未姫さんには言付けたけど、やっぱりそういうのは直接言わなきゃって思って。杏子さんに謝りに行くべく、立ち上がろうとした時、ふっと。 杏子さんと目が合った。 「…………」 杏子さんはあたしと目が合うと、困ったような表情を見せた後、まるであたしから逃げるように目を逸らした。そして奥のクッキングマシーンでご飯を作って、またあたし達のいるテーブル席の方にやってきたけれど、あたしを避けるようにして、離れた席に腰を下ろしていた。 ……あたし、もしかして、杏子さんのこと怒らせてる? 彼女の態度を見て、それでも彼女に近づいて昨日のことを謝るなんて、そんな勇気を持つことが出来なかった。あたし、あんまり人付き合いとか得意じゃないから。相手を傷つけたり、怒らせたり、そういう時に一体どうしたら良いのかがわからない。 「セナってさぁ、やっぱり杏子さんと何かあったんでしょ?明らかに挙動不審だし」 「う、うぇ……?」 遼の鋭いつっこみにギクっとしながらも、何かあったなんてこと、上手く言葉に出来なくて。 だって、一体どんなふうに言えばいい?昔好きだった人と似てるような気がするけど、昔好きだった人ってのは顔も声も何も知らなくて、なのに似てるだなんて明らかにおかしいし、でもでも昔好きだった人と重ね合わせちゃってギクシャクしてるのは事実だし。 「な、なんでもないよ」 「うそつけ。セナって本当に隠し事できないタイプね?身体全体から、何かありましたー、っていうオーラが出てるしね。もうバレバレ」 「うっ……」 肩を竦めて「ハハァン?」みたいな、遼の仰仰しい呆れ方にちょっとムカつきつつ、でも遼の言ってることは間違ってないので言い返せない。そ、そんなにあたしってわかりやすいのかなぁ。 「セナちゃんさぁ」 あ、来た。遼があたしを「セナちゃん」とか呼ぶときは大抵年上顔して色々言って来る時なんだよ。 今度はどんなこと言われるのかと、構えながら遼の続く言葉を聞く。 「……本当にこのままでいいわけ?」 「なにが……?」 「トラブってるままだと気分悪いでしょ?」 遼は杏子さんに声が届くことを考慮してか、潜めた声で言いながらスプーンをピッとあたしに突きつけた。 「それは……まぁ、あんまりスッキリはしないけど……」 「なら!ガツンッと当たって砕ければいいじゃん!んもぅー遼ちゃんはそういう優柔不断なのは嫌いだよー」 「…………」 実に遼らしい、と思った。 わかる気がする。遼ってうじうじ悩んでるぐらいならガツンと行っちゃうタイプだ。 それで物凄い喧嘩とか巻き起こしそうなタイプだ。 ……で、でもそれは遼のタイプであって、あたしとはまた別問題のような、気も。 「セナ、あたしの話を聞く気はないのね?」 黙りこんでいるあたしに、遼はじとーっとした視線を向けて問い掛けた。 聞く気は、っていうか、そういう問題じゃないような気がする、というか、遼の言うことも一理あるけど、でも 「じゃあいいよッ」 あたしが考え込んでる間に、遼はガタンッと立ち上がった。 「う、うー?」 遼まで怒らせた?と不安になって遼を見上げる。 遼はじっとあたしを見下ろした後、ダッとテーブルから離れて行った。 「セナが聞かないなら杏子さんに言ってやる!」 「えええええぇぇ!!!!?」 あたしは慌てて立ち上がり遼を止めようとした、が、遼は既に杏子さんのところに駆け寄ってるし、杏子さんもあたし達の騒動に気付いてか顔を上げてきょとんとした表情を浮かべているし。 「杏子さん!」 遼の大声はあたしのところまでしっかり聞こえていた。 あぁ、もうだめだ……。 「セナが嫌いなら嫌いってはっきり言いましょうよ!」 ………………。 ……ち、致命傷。 遼、ひどい。そんなはっきり言わなくてもいいじゃん。 あたしは脱力して、半分魂すら抜けかけながらテーブルに突っ伏した。 もういいや。どうでもいいや。杏子さんに嫌われてたって、悪いのはあたしだし……。 「……」 「見てればわかりますって!セナも悩んでるんだし、そういうのははっきり言った方がいいと思います!」 「……」 「だーかーらー!!」 遼の声はしっかり聞こえているけれど、杏子さんの声はあたしのところには届かない。 二人が一体どんな会話を交わしているのか、聞きたいような聞きたくないような。 あたしはそっと顔を上げて、二人の様子を見ようとし――……あ? 「あ……わわ」 気付けば杏子さんは、あたしの方に歩み寄っていた。慌てて顔を上げて佇まいを正す。 杏子さんはあたしのそばまで近づくと、ふっと弱い笑みを見せた。 「……私、セナちゃんのこと悩ませちゃってたんだね。」 「あ、い、いえ、こっちこそ」 しどろもどろに言葉を返しつつ、ふと杏子さんの後ろを見た。けしかけた当人である遼は、あたし達の様子を見てか「パフェ片付けといてね」と言いたげにテーブルを指差し、そのまま食堂を後にした。 な、なんていうか、無責任だよ遼……! 「座ってもいい?」 「ど、どうぞッ」 杏子さんの問いにこくこくと頷けば、杏子さんはあたしの向かい側、さっきまで遼が座ってたところに腰を下ろす。それから少し目を伏せて、沈黙。あたしも一体何て言っていいかわからず、押し黙ってしまう。 「……セナちゃん、もしかして怒ってた、かな?……その、私が昨日都さんと変なことしたから?」 「え?……い、いえ、その、あたしは怒ってなんかない、です。……杏子さんこそ、昨日……あたしが変なこと言ったから、怒ってるのかなって……」 杏子さんの言葉は予想外だった。てっきり怒ってるんだと思ってた、のに、杏子さんも同じこと思ってたの? そしてあたしの言葉にも、杏子さんは不思議そうな顔をしていた。 「私も怒ってないよ?……うん、セナちゃんは何も悪くないもの」 そう言って、杏子さんは微笑む。 ふわっとした、優しい笑み。……あぁ、まただよ。月見夜さんと重なって見える。 これさえなければ、杏子さんって本当に素敵な人なのに。……ううん、こうやって重なって見えちゃうのはあたしが悪いんだから、杏子さん自身は本当に本当に素敵な人なんだ。 杏子さんだって何も悪くないのに。悪いのはあたしなのに。 それからあたし達はまた黙り込んで、暫しの沈黙。 変に思ってるかな。あたしの態度、やっぱりおかしいよね。……うぅ。 「……ねぇセナちゃん」 「は、はい」 「私の態度、おかしいよね。」 「……え?」 投げ掛けられた言葉、一瞬わけがわからなくて、固まった。 な、なんで?なんで杏子さんもあたしと同じこと考えてるの? おかしいのはあたしだよ。杏子さんは、何も……。 「ごめんね、セナちゃん。……」 「……」 杏子さんは、昨日までは確か――あたしのことを冴月ちゃんって、呼んでたような気がする。 なのに今日は、どして、あたしのことをセナって呼ぶんだろう。 そんなふうに呼ばれたら、あたし、余計に……。 「セナちゃんは本当に、何も悪くないんだよ。……だから」 「あ、杏子さん、あたし……ッ」 思わず口にしてから、ふっと言葉が途切れて。 あたしの言葉を待つように、見つめる二つの瞳。 ドキッと胸が騒いで、自分の胸元をぎゅっと握った。 杏子さんに、あんなふうに気遣ってもらうの、耐えられないよ。 あたし……やっぱり本当のこと、ちゃんと言おう。 杏子さんにしてみれば失礼な話かもしれないけど。見ず知らずの誰かと一緒にされてるなんて、怒るかもしれないけど。でも、ちゃんと言わなきゃ。そうしなきゃ問題は解決しない。 トラブってるままだと気分悪い、ってね、遼の言う通りだよ。 「……あたし、実は……」 「う、うん……?」 「杏子さんの、こと……」 「……う、ん?」 杏子さんは僅かに表情を強張らせて、あたしの言葉を待っているみたいだった。 どして、そんな顔するのかなって少し疑問に思いながらも、あたしは続けた。 「昔好きだった人と、重ね合わせて見てるんです。……その人とは、会ったこともないし顔も知らないし……でも、ずっと好きで。……杏子さんが、なんとなくその人と似ているような気がして、それで、あたし」 「……」 「ごめんなさい。」 ……ッ、言っちゃった、よ。 怒られるかな。でもこればっかりは、やっぱり、ちゃんと言っとかないとって、そう思うし。 心臓がドキドキしてる。 杏子さんは月見夜さんじゃないのに、なのにまるで、月見夜さんが目の前にいるみたいだ。 伏せた目を、少し上げて、杏子さんの姿を見る。 怒ってるかなって怖かったけど。……杏子さんは怒ってなかった。 ただ、どこか驚いたような、複雑そうな表情を浮かべて、少しの間あたしを見つめた。 「あ、……あの、……セナちゃん」 「はいッ……」 「……それ、本当?」 「…………え?」 杏子さんの微妙なリアクションにビクビクしながらも、もう隠すわけにもいかないし、とそう思って頷く。 「本当、です。……昔好きだった人に、似て」 「好きだったの……?」 「……え?」 「………………あ」 いまいち噛みあわないやりとりの後、杏子さんはハッとしたように瞬いて目を逸らす。 う、やば、やっぱり怒っちゃったかな。 目を合わせずに、杏子さんは暫く押し黙って。 それから再度あたしに目を向け「そっか」と小さく頷いた。 「セナちゃん。……私ももしかしたら、同じなのかなぁ」 「同じ……?」 「……うん。セナちゃん、私が昔好きだった人に似てる、かもしれない」 杏子さんは零すような口調で言って、ふっと弱く笑んで見せた。 杏子さんが昔、好きだった人――? あたしが?似てる……? 「だからね。ちょっとギクシャクしちゃったのかも。……ごめんね」 「あ、えと、いえ!こちらこそ!」 思いっきり頭を下げつつ、未だにちょっと混乱している頭を整理する。 ど、どういうことだっけ? あたしは杏子さんのこと、月見夜さんみたいに思えてて、それで一方的にギクシャクしてるんだと思った。 でも、違った。杏子さんもあたしと同じで、あたしが昔好きだった人に似ているからギクシャクしてた。 それであたしたち、噛み合わなかった?それで余計ややこしくなってたの? な、なぁんだ。じゃああたしばっか悪いわけじゃ……、いや、そういう問題じゃないのかな。 杏子さんが月見夜さんに似てたり、あたしが杏子さんの昔の恋人さんに似ていたり、 そういう次元じゃないところで、考えるべきなのかもしれない。 「だから……その」 ようやく頭の中でまとめ終えて、あたしは小さく切り出した。 未だにどこか複雑そうな杏子さんに、あたしは慣れない笑みを、見せて。 「あんまり、深く考えない方がいいです、よね。……杏子さんが月見夜さんに似てるとかそんなんじゃなくて。」 「……うん。」 「杏子さんは杏子さんだし、あたしはあたしだし。……そういうふうに見れるように、なれたら」 「……そうだね」 たどたどしいあたしの言葉に、杏子さんは優しく微笑んでくれた。 その笑みにドキッとしてしまうのは――彼女が月見夜さんに似てるから、じゃなくて。 杏子さんの笑みが素敵だから、ドキッとしてしまうんだ。……きっと。 「セナちゃん。……あ、違うね、冴月ちゃん。……その、月見夜さんっていう人、よりも。私……素敵な人になれたいいと、思うよ」 「……?」 「…………なんでもない」 杏子さんの言葉、よくわからにゃい、けど…… 多分、その、月見夜さんと重ねるんじゃなくて、杏子さん自身を見て欲しい、ってことかな? 杏子さんは笑んでくれるし、うん、もうあんまり深く考えるのはやめておこう。 「ともあれ、これからも宜しくね。冴月ちゃん」 杏子さんはそう言って、すっと手を差し出した。 「はいッ……宜しくお願いします、杏子さんッ」 あたしも彼女につられるように笑んで、そして杏子さんの手に自分の手を重ねる。 触れる温度は、月見夜さんに似てるんじゃない。この温度は、杏子さんだけのもの。 ―――これは杏子さんの温度。 いつかは忘れられるかな。月見夜さんのこと、忘れられるのかな。 そしてあたしは、もっともっと素敵な人に、恋をすることが出来るのかな。 うん。きっと大丈夫だよ。 今はもう、月見夜さんじゃなくって。 杏子さんに笑みを見せることが、出来るから。 大丈夫。 足元に気をつけながら、二人で歩く夜の道。 本当は同僚さんや店長さんを連れて行く予定だったのに、結局二人っきりになった帰り道。 “お仕事”の後に、火照った身体が冷たい空気に晒される。 「すっかり日が暮れちゃいましたね」 そう切り出すと、隣を歩く長身の人物は、ちらりとこちらに目を向ける。 都さん、少しだけ口数が減ったけれど、いつものように振舞って「そうね」と頷いた。 私―――五十嵐和葉―――は、なんだか彼女の顔を見るのが照れくさくて、つい目を逸らす。 お仕事の相手、それはお仕事の時だけ顔を合わせて、その時だけ触れ合って。 そういう関係が当然だったから、お仕事の後も普通に付き合って行くってのはやっぱり照れくさい。 それは、都さんも同じなのかなぁ。 会話も上手く続かずに、少しの距離を置いて並んで歩く私達。 気まずいわけでもないけれど、なんだかちょっと寂しいなぁ。 今はとても特別な時間、そんな気がする。 施設に戻れば婦警さんたちに叱られちゃうかもしれないなぁ。でもMinaさんにも会えるし、美味しいご飯も食べられるし、あの施設の中は暖かいし。なのに、なんでだろう、早く帰りたいって思えない。 今、この時間を終わりたくないって、そんなふうに思ってしまう。 「ねぇ、都さん……」 「ん。なぁに?」 「私のこと……幻滅しましたか?」 「どうして?」 「だって……あんなこと……軽い女みたいに思われちゃうかなって」 会話の切り口も見つからなくて、結局はそんな話題しか浮かばなかった。 都さんはふっと足を止めると、私のことを少しの間見つめてから、微笑みを零す。 「可愛かったわよ。それに、嬉しかった。……幻滅どころか――」 「……」 どんな言葉が続くのかなって、ドキドキしながら都さんを見つめ返す。 都さんは少しの沈黙の後、そっと私に手を伸ばし、頬に指先を滑らせる。 冷たい指先が、少し火照った頬にじんわりと滲むようだった。 「……和葉ちゃんのこと、恋人にしたいぐらい。」 「都さん……すごい口説き文句ですよ、それ」 「ふふ、だって口説いてるもん。」 悪戯っぽい笑みに、思わずつられて吹き出した。 都さんってば上手だなぁ。こんな人が最後のお客様で――最後のご主人様で、本当に良かった。 「ありがとうございます……都さん」 「んーん。こっちこそごちそうさま。」 軽い調子で返されて、「もぅ」と頬を膨らませながら、また二人で歩き出す。 さっきよりも縮まった距離。ちらりと隣にいる都さんを見れば、目が合って。 都さんは柔らかく笑んでから、私をそっと引き寄せた。 「寒いでしょ?」 「……はい。寒いです」 「うん。」 それは寄り添う理由なんだって、お互いに言い訳してるみたいでおかしかった。 都さんに肩を抱かれて、彼女に寄り添って歩く。 温かくて、なんだか嬉しくて、この時間がずっと続けばいいと、そんなことを思った。 恋人でもないのに、今はお客様でもないのに、それなのにこんなにも相手のことが愛しくて。 きゅっと、都さんに抱きつくようにして――その体温に縋った。 「まだ寒い?……そうよね、ほら、雪降ってきたもん」 「あ……」 気付けば、空から雪がはらはらと舞い落ちていた。 暗闇の中、微かな光に照らされて、白く輝く雪の姿に見惚れた。 私達は足を止めて、空を見上げ、暫し言葉をなくしていた。 「……和葉ちゃん」 ふと名前を呼ばれて都さんに目を移すと、都さんは小さく笑んで私の顔に指を伸ばし、 「睫毛に雪がついてる。……目、瞑って」 と、囁いた。 私は彼女の言葉のままに目を瞑って、――待つのは彼女の、体温か。 期待通りに、ふわりと唇に触れた温度。その温もりに心まで溶かされてしまいそうだった。 やがて私は目を開けて、都さんと視線を交わす。 今のキスに、理由などあるのだろうか。 互いに言い訳も見つからずに、少しだけ笑った。 彼女がもしも恋人だったら、幸せに、なれるのかな。 さっきの言葉、やっぱり冗談なのかな。本気だったら、私は嬉しい? 恋人に、なれたら…… 「カット!」 ……は!? 突然の声は、都さんのものでもないし、当然私でもない。 私と都さんは顔を見合わせ、それからきょろきょろと辺りを見回した。 「ドラマのワンシーンのような美しい情景でしたよ。しかし、ドラマの裏には現実が存在する」 声の主の姿はない。ただその声は冷たい空気の中、凛として響き渡る。 女性の声とも男性の声ともつかない――まるで少年のような、中性的な声だった。 「夢物語はいつまでも続くものではないのです。それが現実というもの」 私と都さんは辺りを見回して人物の姿を探す。 その時不意に、カッ!と背後から光が差した。 振り向けばそこには―― 「私は現実に生きるもの。私の名は、怪盗エ」 「出たな白い人ッッ!」 ……。 私達の背後の二階建てほどの建物。その屋根の上に、人物はいた。 きっとその人物が用意しているのであろうライトに照らされ、しなやかな姿が見える。 白いシルクハットに、白いスーツ。 そう、つまり都さんの言う通り、「白い人」ではあるんだけど…… 都さん、今のタイミングはどうかと。 あの人まだ、名乗ってる途中だったような気が……。 「ドラマには必ずNGというものが存在する。それは人間の常なのです。ともすれば、次に行なうのはリテイクです。宜しいですねお嬢さん方。」 人物はそう言って、ふっと姿を消し、ランプも消えた。 再び訪れた暗闇の中、私と都さんは黙り込む。 そして少ししてからまた、カッ!と光が差した。 「私は現実に生きるもの。私の名は、怪盗FB!」 ……あ、リテイクってそういう意味なんだ。 やり直したんだ。……うーん、あんまり格好良くはないかなぁ。 怪盗、エフビー。……怪盗?都さんのお仲間さん? 「何がFBよ。あんたね?私の後をちょこまか付け回してたのは」 「ストーカー呼ばわりとは失敬な。私は敬愛するHAPPYの姿を背後から眺め、見習っていただけですよ」 それも立派なストーカー行為だと思う。 口ぶりは格好良いけど、どこかズレた人なんだな、と思いつつ、建物の上に浮かび上がった人物を見上げる。その格好も確かに怪盗さんっぽくて、顔はシルクハットの影に見えないところなんかもう、まさに怪盗さん、っていう感じがする。 怪盗FB。聞いたことのない名前だけど……。 「見習うのはいいけどさ。……こう、出てくるタイミング悪いんじゃない?怪盗たるもの、絶妙のタイミングで姿を現すべきよ。あんたは怪盗としてはまだまだね、FB。」 都さん、すごく不機嫌だ。腕を組んでジトーっとした目を建物の上のFBに向けながら、呆れたような口調で言い付ける。しかしFBも怯まない。 「私はHAPPYの出現タイミングを見習っただけですよ。ある時は米軍幹部の逢瀬現場、ある時は米軍兵士の陵辱現場。HAPPYは“ここから!”というタイミングで出現したではないですか。」 「…………そ、それはッ、た、タイミング的に面白いかな、と」 「都さん、言い訳になってないです」 思わず小声でつっこんで、FBと都さんを交互に見る。FBのどこかズレてる部分っていうのは、もしかして都さんを見習った部分なのだろうか。うん、なんだかそんな気がする。 都さんもFBの言葉にたじたじだったものの、気を取り直すようにダンッと一歩踏み出した。 「とにかく!あんたがどんな目的を持ってるのかは知らないけど、この子には手を出さないで」 庇うように、私の前に翳された都さんの手に、少しだけきょとん。 ……あ、私?私が狙われてるの? 「残念ながらHAPPY、私の狙いはその若い女性ではありません」 ……あ。違うんだ。私じゃないんだ。嬉しいような、残念なような。別に攫われてみたいとかじゃなくて、都さんに守って貰えるのかなぁって思うと少し楽しみだったわけで。 「じゃあ何よ。金?」 「それも違います。」 他に何を狙うのかと、私も都さんも小さく首を傾げてFBを見上げる。 刹那、ふっとライトが消えたかと思えば、この辺りをぼんやりと照らしていた街灯までも一斉に消えて、薄闇に包まれた。空にぼんやりと浮かんでいる月光など頼りにならない。 隣にいる都さんすら微かなシルエットにしか見えなくて、私は不安になって都さんに手を伸ばす。 「私の狙いは一つだけ――貴女ですよ、HAPPY」 「……え、私?!」 闇の中でそんなやりとりが、っていうか都さん狙い、ですか!? わけもわからず、ただ都さんを渡したくない、そんな一心で都さんを手探りで探す。 しかし、トンッと微かな音がして――おそらく今の音は、都さんがどこかへ跳んだ音、だった。 「冗談もほどほどにしておきなさいFB!私を奪うなんてバカげてるわよ!」 「それはどうか。実践してみましょう?」 FBは笑み交じりの口調で言い、刹那、ひゅんっと風を切る音がした。 都さんに対して――怪盗HAPPYに対して、あんなにも自信満々に言い放つなんて。 私には何も見えない。二人の姿も、気配っていうものも。 ただ、時折どこかで地を蹴る音や、風を切る音が聞こえてくる。 「なッ?!……なんつースピードなのよっ」 「貴女が教えてくれたんですよ。狙い方も、――奪い方も」 「バカな!」 そんな会話の一端から知ることが出来るのは、……。 FBの声に滲む余裕と、都さんの声に滲む焦り。 あ、あぁッ……どうしよう、もしもこのまま、都さんが奪われてしまった、ら。 私は、都さんのことを手放したく、ないのに――! 「都さん、お願い、負けないでッ……」 闇の奥へと呼びかける。その声が届いているのか否かすらもわからない、返答のない一方的な言葉。 それでもどうか届くことを、そして言葉が事実になることを祈って、私はきゅっと手を組んだ。 不意に、――ドンッ、と。 人間がぶつかるような微かな音が聞こえた。 どこから聞こえたのかもわからず、私は暗闇の中で必死に目を凝らす。 今の物音の後、ふっと音が消えてしまったように、何も聞こえなくなってしまう。 「……都さ……都さん!!」 襲い来る恐怖に抗うように、声を上げて名を呼んだ。 返事なかったらどうしよう。もう都さんがこの場にいなかったらどうしよう。 そんな不安に負けじと、声を上げて何度も彼女の名を呼んだ。 「――ッ、生きてるわ、よ……」 どこかで聞こえた微かな声、間違いなく都さんのものだった。 だけどその声は掠れていて――もしかしたら身体に傷を負ったのかもしれないと、不安は消えない。 都さんの返答から十秒も経たぬうちに、チカチカと視界の隅で瞬く光。 そしてふっと、今まで消えていた街灯に光が点り、辺りをぼんやりと照らす。 私から十五メートルほど離れたところに都さんの姿はあった。地面に尻餅をつくように崩れ落ち、片手で口元を覆っていた。 「都さん!」 私は都さんに駆け寄り、泣きそうになりながら彼女のそばに跪く。 どうしよう、もし命に関わるような怪我だったら……! 「……あ」 都さんはようやく私のことに気付いたような素振りで顔を上げ、それから弱い笑みを浮かべて言った。 「怪我とかはしてないし……大丈夫よ。……大丈夫」 そう言いながらも微かに震える声。 やっぱり無理をしているのではないかと、そう思って彼女の身体を見回すけれど―― 確かに。怪我は見当たらない。 なのに、都さんは微かに身体を震わせて宙を見上げ、その後でガッ、と、握りしめた拳で地面を叩く。 「……み、都さん?……何があったんです?」 明らかに尋常ではない様子に、私は恐る恐る問いかけた。 都さんは「ふっ」とそんなニヒルな笑みを漏らした後、 「あいつ……絶対許さない!!!」 と、溢れんばかりの怒りを露わにする。 「何か大事な物とか、奪われたんですか……?」 「そうよ。大事なものを」 こっくりと頷いて、都さんは大きく息を漏らした。 その後でまた手を口元に当てながら、ほんの微かな声で、呟いた。 「唇、奪われた。」 「…………は?」 「あいつ!!私にキス、した、のッ!」 「ええ!?」 わなわなと打ち震えながら、既に姿を消したFBを探すように空を見渡す都さん。怒り心頭といった様子だけど、確かに見ず知らずの人にいきなりキスされれば怒るかもしれないけど、でも、なんていうか。 …………き、キスぅ? 呆気に取られている私のことなど構わずに、都さんは立ち上がって空を仰ぐ。 都さんは強い怒りを露わにして、もう姿もないFBに向け、闇夜に吠えた。 「怪盗FB、覚えてなさいーッッ!!」 《HAPPY》 VS 《FB》 怪盗同士の因縁の対決になるかに思われた。 私もこの時には知る由もない。 FBの本当のライバルは都さんではなく――もう一人の怪盗だということを。 |