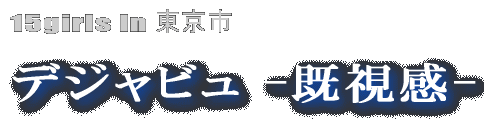
|
息を切らせながら廊下をダッシュしていた。 食堂にいるのは悪魔三匹だ。その名はハルカ・ミコト・イズミ。 あたし―――蓬莱冴月―――の過去を掘り出すなんて、マジで勘弁して下さいッ! あたしが、年齢に拘る理由。あたしの昔の恋に関係している。 そこまで突き止めるなんて大したものだよ、三人とも。 だけど。これ以上、昔のことを突っ込まないで。 あたしはもう、あの時のことなんか――忘れてしまいたいんだから。 「――ッ!」 今日、見た夢は何だろう。 それはもう過去であるはずなのに。 あんなにも鮮明にあたしに呼びかけた。『セナちゃん』と。 忘れたいのに出て行ってくれない。 過去の人が。 「わ!!」 走りながら考え事なんかするものじゃない。 結構なスピードなのに、前方に全然注意を払っていなかった。 目の前のお姉さんが振り向いたその瞬間には――ドンッ!と。 思い切り、あたしはお姉さんに体当たりを掛けていたのだった。 「ビックリ……した。」 お姉さんはその場で膝をつき、あたしは尻餅をついていた。お姉さん、ぱちぱちと瞬きながらあたしを見る。 「ご、ごめんなさい!全然前見てなかったッ……」 ペコペコと頭を下げて謝ると、お姉さんはのほほんとした笑みを浮かべてこう言った。 「いいのいいの。私もよく、ぼーっとしてて人にぶつかっちゃうから。」 怒りもせずに柔らかい笑みを見せてくれるお姉さんに安堵しながら、このお姉さんの名前を思い出す。 事情聴取の時と同じく後ろに結った長い黒髪に、優しげな笑顔。ハイネックにロングスカート、そんなお姉さんっぽい格好をしている――彼女の、名前。なんか妙に可愛い名前だった。 あ……あんこ、さん。そうだ、杏子さんだ。 「冴月ちゃん、だったね?はい、落し物。」 杏子お姉さんは、その場に転がっていた細身の何かを拾い上げてあたしに差し出す。 って、うわ。あんま人には見られたくなかったような気がする――ポケットに入れていた剃刀だ。 「あ、えと、本当にすみませんでした」 杏子お姉さんが差し出してくれた剃刀を受け取り、慌ててポケットに押し込んだ。 そして立ち上がり、その場を後にしようとした。けれど不意に杏子お姉さんが呼び止める、「冴月ちゃん」と。 「……は、はい?」 「あー。えっとね」 杏子お姉さんはのんびりとした口調で笑んで、「よいしょ」と言いながら立ち上がる。その途中で「おっとっと」とか言ってバランス崩してる辺りが妙に可愛い。 「あのね、冴月ちゃんね……パソコンしてるよね?」 「え?あ、はい!」 「うん。お仲間さんだなぁって思ってたの。私もパソコンしてるから。置いてきちゃって手元にないんだけどね」 あぁ、そう言えばこのお姉さん、小説家さんとか言ってたっけ。パソコンってやつも実は貴重なものだったりして、世の中でパソコン扱える人って早々いない。二十年前は誰でもパソコン使ってたらしい――って 「ああああああああぁぁぁぁぁぁっっっ!!!!」 あ、あ、あ、あ、あ!!! あたしは今頃になって、超ハイパー物凄く大事なことを思い出していた。 突然上げた大声にきょとんとしている杏子お姉さんは「どしたの?」と首を傾げる。 「ぱ、パソコン!あたし、昨日のどさくさで隣のビルに置いて来てたんだ!なんか忘れてると思ったら!」 そう、昨日の――Happyに連れてこられた時のことだ。あたしと遼はHappyに抱えられ、隣のビルからマジックのように飛行してこの施設の上の建物、つまり09跡地にやってきた。その時、あたしは見事に忘れてしまったのである。隣の廃ビルに、命と同じぐらい大事なパソコンを。 その命より大事なパソコンをすっかり忘れてた辺りがちょっと痛いけど、展開が速すぎて本当に忘れていた。あぁ、もうすぐあそこにパソコン放置してから二十時間ぐらい経っちゃうけど……誰かに盗まれてないかなぁ。うぅ、超不安。 「ありゃりゃ、忘れちゃったのかぁ。それじゃ取りに行こうか。私、付き合ってあげるよ」 杏子お姉さんはにっこりと笑んで言ってくれた。うわ助かる。一刻も早い方が良い。 「じゃあお願いします!い、今からいいです?あーんもう、めっちゃ心配……」 「はいはい。でも婦警さんの承諾を得ないとね」 と、そんなわけであたしたちは婦警二人組のお部屋を訪ね、出てきた千景ちゃんに事情を説明した。 時刻は既に夜中の零時を回っていた。「明日にしない?」という千景ちゃんの言葉に、あたしと杏子お姉さんは揃って首を横に振り、あたしは熱烈に説得したのだった。「一刻を争うのです!」 そして渋々といった様子ながら、千景ちゃんがついてくるという条件を飲み、あたしたち三人は施設の重厚な扉を開けて外に出た。空調の効いた施設内から出てきたばかりだからだろうか、痛烈に寒い。あたしってばこんな環境で生きてたのかと、少し感動。たった一日弱、施設の中にいただけでも身体ってやつは鈍ってしまうものなのだ。 「うぅ、さっむぅ……せめて昼間ならもちょっと暖かいのに……」 などという千景ちゃんのぼやきは無視して、早足に建物を出る。 荒れ果てたアスファルトを踏んで、ゆるりと左右を見渡した。誰もいない真夜中の道、光源となるのは千景ちゃんが手にしているランプと、どこか遠くでチカチカと点滅する街灯くらいのもの。今でも公共電力が生きていること自体、奇跡に近いような気もする。 「この廃ビルの二階に置いといたんだよ、あたしのパソコン。」 そう言いつつビルへと足を速め、パソコンが心配で仕方が無いあたしは二人を急かすように振り向いた。後ろの二人はのんびりと歩いてくる……いや、杏子お姉さんはぼんやりと上を見上げて立ち止まってすらいる。 「早く早くーっ」 「あ、ごめんね」 あたしが急かせば、杏子お姉さんはふと我に返ったように笑んで、あたしの後を追った。 二人を案内しながら、道を挟んですぐのビルの中に入っていく。ビルの出入り口、昔にはきっとガラスの自動ドアがあったのだろう。今やそのガラスの欠片すらも残っておらず、ぽっかりと口を空けているだけだ。建物の奥には闇が蠢いているように見え、思わず足を止めていた。 「不気味だねぇ……」 後ろから掛けられるのほほんとした声は杏子お姉さんのもの。杏子お姉さんと千景ちゃんとはあたしのそばまで歩いて来ると、二人も闇を目の当たりにしてか、足を止めてビルの中を見回していた。 ビルの内部、所々が朽ち果てて既に崩れ落ちている箇所もある。幸い階段は無事で、昨日はあたしは勿論のこと、遼やHappyこと都さんもその階段を通って二階に足を運んだのだろう。……都さんの場合、なんか妙な通路とか知ってそうな気もするけれど。 光のない廃ビルの中では二人より先に進むことも出来ず、ランプを手にした千景ちゃんについて歩く。ランプはぼんやりとビルの中を照らしているのだが、隅っこの方までは光が届かない。カサカサと小さな音がするのは、この建物の中に巣食っているネズミかなんかだろうか。正体が明らかじゃない以上、それは不気味なことこの上ないのだった。 「このビルにはね……噂があるの」 静まり返った空気の中、ぽつりと切り出したのはあたしの隣を歩く杏子お姉さん。 「噂?」 「昔ね、このビルはオフィスビルだったの。それはそれは和やかな職場だったらしいわ。……だけど」 淡々とした口調で紡ぐ杏子お姉さんに、一歩前を歩く千景ちゃんもチラリと振り向いた。 お姉さんは真っ直ぐに前を見つめながら言葉を続ける。 「突然、職員の一人がこの建物の中で謎の変死を遂げた。出社した別の職員がその遺体を発見したそうよ」 「……」 「誰が殺したのかはわからず……会社の職員達は皆、容疑者になった。彼らは互いを疑いの眼差しで見るようになり、和やかな雰囲気は消えてしまったの……」 「……そ、それで?」 「職場には喧嘩が絶えなくなり……職員達は皆、いがみ合った。憎しみは絶望を生み、そして――」 「そして……?」 「集団自殺。」 ぽそっ、と杏子お姉さんが口にした、その時だった。 ガシャアアアアアン!!と、何かが割れるような音が響き渡る。 「うわぁぁぁぁ!?」 「な、なによこれッ」 あたしと千景ちゃんは顔を見合わせ、階段の直前で足を止める。 多分今の音、この上の階から聞こえたと、思う……。 杏子お姉さんだけは無表情に階段の上を見上げ、 「今でも怨霊がたくさん、いるのかもしれないわね……」 と、めちゃめちゃ怖いことを言う。 ちょ、ちょっと待って、マジっすかッ!?あたし、昨日何時間もこのビルにいたよぉぉ……。 足が竦んで、階段の下で立ち止まる。千景ちゃんも不安げな顔であたしと杏子お姉さんを見遣っては「どうすんの?」と小声で問うた。杏子さんだけは怯えた様子を見せるでもなく、じっと階段の上を見つめている。 その時、カツン、カツン、カツン……と、どこからか足音のような音が聞こえた。 あぁ、これも階段の上からだ。カツン、カツン、カツン。音は徐々に、近づいてきていた。 あたしは思わず隣にいる杏子お姉さんの腕にしがみ付いて、恐る恐る階段の上を見つめる。 「幽霊なんかいるはずないわよ!」 恐怖を振り切るように千景ちゃんは強く言って、ランプを手にダッと階段を登っていった。 「ち、千景ちゃん……!!」 声が上擦って引き止めることも侭ならない。 やがて千景ちゃんは階段の踊り場まで到達し、そして――ピタリと動きを止めた。 「だから言ったのに。怨霊がいるかもしれない、って」 杏子お姉さんは小さく溜息を零し、諦めたような眼差しで千景ちゃんを見上げる。 って、え?ええ!?嘘でしょ、嘘でしょー!!? 暫しの沈黙の後、千景ちゃんはバッと身を翻し、あたしたちの方にダッシュで駆け下りた。 「や、ヤバい。ここはマジでヤバイッ!」 焦ったような声を上げながら「戻るわよ!」と怒鳴りつける。ち、千景ちゃん、顔面蒼白だよ…… な、何?今、千景ちゃんは何を見たのッ!? 「逃げちゃだめ……」 杏子お姉さんは囁くような声で言って、千景ちゃんの腕をガシッと掴んでいた。 って、杏子お姉さんも幽霊みたいな顔になってるよ、まじで、うわーーん!! 「だだだだ、だってこの上には……!!!」 千景ちゃんは階段の上を指差し、顔を上げ、……そして声を飲んだ。 震える指先。見開いた瞳。千景ちゃんの視線の先に、何かがあるのは、間違いない。 その様子に、あたしはゆっくりと振り向き……階段の上を、見上げ―― 「きゃわぁぁああああああッッッッッッ!!!」 思わずあたしもその場から逃げ出そうとしていた、のに、杏子お姉さんがもう一方の手であたしの腕を掴んで離さない。身体の力が抜けるようにぺたんとその場にへたり込んで、恐る恐る階段の上を見上げる。 カツン、カツン、カツン。 足音を響かせて、降りて、来る。 幽 霊 が !!!!! 黒くぼんやりと揺れる姿。 顔も頭も髪もなく、 胴体もぼんやりと澱んだ黒で、 そして幽霊なんだから当然足もな…… 足も、ない? 足? ―――足音、するのに? 「プッ」 不意に、あたしの腕を掴んでいた杏子お姉さんが小さく吹き出した。 「二人とも……引っかかりすぎ」 という楽しげな声を上げたのは杏子お姉さんではなく―――幽霊だった。 あたしは腰抜けてるし、千景ちゃんも「は……?」と呆気に取られているし。 わけもわからず、クスクスと笑みを漏らす幽霊を見つめるだけだ。 「いやぁ驚かせてごめんねー」 幽霊は突如、ガバッと何かを脱ぎ捨てた。黒いのは幽霊の身体じゃなくて、何かの、布? そしてその中から現れたのは…… 「は、Happy……」 「都ぉ……」 千景ちゃんと一緒に、へにゃっとその場で脱力してしまう。 あ、あああぁぁぁ…… 「実はさ、退屈だったからこのビルに遊びに来てたわけ。そしたら、上の階から三人がこのビルに入ってくるのが見えてね?」 「それでね、私はビルの上にいた都さんを見かけてね。」 都さんとお姉さんは、楽しげな口調でネタばらしをしてくれた。それはもう楽しげに。 「見事なアイトークだったわね!杏子ちゃんならやってくれると思ったわ」 「うん、都さんもなんか企んでそうだったからねぇ。怖い話なんかしちゃったー」 二人は顔を見合わせて、ブイサインなんかし合いっこして笑っていた。 「じゃ、じゃあ……さっきの怖い話は」 「うん、嘘。」 「嘘……」 ガックシ。 「このパソコン、確か冴月ちゃんのでしょ?昨日忘れてたような気がしたからね、それも兼ねて来てたのよ」 都さんは階段を降りながら背中のリュックからパソコンを取り出し、あたしに差し出した。 「あ……うん……そう……あたしの……」 お礼を言う気にもなれずに、脱力したままでパソコンを受け取る。 はぁ。 都さんも、杏子お姉さんも……ひどい……あたし、本気で怖かったのに……。 千景ちゃんも同じだ。その場に膝をついて、打ち震…… ん? 「千景ちゃん?大丈夫?」 千景ちゃんは未だに驚いたような表情で、先ほど都さんがいた階段の上を見上げていた。 もうネタばらしも終わったんだから、ガックリするなり怒るなりしていいのに。 なのに千景ちゃんは尚も、微かに唇を震わせて階段の上を指差す。 「ん?」 「どしたの?」 あたしたち三人は首を傾げつつ、千景ちゃんの指差す先、階段の踊り場に目を遣った。 そこには何もなく、闇がぼんやりと蟠っているだけである。 「何もないよ?」 千景ちゃんに目を戻してそう言っても、千景ちゃんはふるふると首を小さく横に振った。 「い、今、確かに……白っぽい人、が……」 「え?」 「いたの!!本当に!!お願い信じて!!」 「え。」 千景ちゃん、嘘をついているようにも見えない。千景ちゃんは心底焦った様子でそばに置いていたランプを手に取り立ち上がり、「戻るわよ!」と怒鳴りつける。 ちょ、ちょっと待って……何……本当に今、何か、いたの……? 「こ、怖いこと言わないでよ、私のさっきのお話は冗談なんだし」 杏子お姉さんも少し表情を強張らせて、慌てて千景ちゃんの後を追いかける。 あたしも置いていかれるわけには行かないと二人を追った。 「……」 ただ、都さんだけは。 いつもの明るい調子とは全く違う、真剣な表情で階段の踊り場を見上げていた。何かを感じているように、目を細め、闇の蟠る踊り場を見つめた。やがてふっと踵を返し、あたしたちの後を追いかける。 「――白い、人」 ぽつりと背後で呟かれた言葉に、一瞬背筋が凍るようだった。 廃ビルを出てから、そびえ立つビルを見上げようとしたけど、やっぱり止めた。 ……こ、怖いんだもんッ。 『Happy……後ろに、白い人が……』 あれは、いつのことだったか。確か、三ヶ月ほど前だったと思う。 米軍に攫われた人質を助け出す途中のことだった。 私―――伴都―――は米軍基地の地下倉庫に、人質として攫われていた少年を助けるために乗り込んだ。そこは非常に入り組んでいて薄暗く、視界も悪い。かといって、こっそり忍び込んでいるわけだから明りを灯すわけにもいかず、気配と微かな物音を頼りにして、人質の少年を探した。 少年は倉庫の片隅に、両手の自由を奪われ、口を塞がれて囚われていた。私は少年の拘束を外し、「これで大丈夫よ」と声を掛けて少年を連れて戻ろうとした。少年も最初は「怪盗Happyだ!」と喜んでくれていた。しかし不意に、不思議そうな表情を浮かべて呟いたのだった。 「白い、人……?」 先ほど千景ちゃんに同じこと言われて、振り向けどそこには誰もいなかった。 二度目だ。私以外の人が、私の背後に潜む「白い人」という存在に気付いた。 しかし私は、その白い人に気付いたことが一度もないのだ。――気配すらも。 少年に言われた時は、きっと少年の見間違いだろうと思った。しかし、千景ちゃんにも同じことを言われたとなると……その「白い人」の存在は、確かなものになってくる。 私の背後に潜む、白い人。一体、何者なの……? 「…………」 地下施設の廊下に一人。考え込みながら歩いては、ふっと足を止める。 ゆっくりと振り向いて、そこに誰もいないことを確認した。 ――突如、ふっと襲う既視感。 誰もいない廊下。誰かがいるような気がするのに、誰もいない空間。 白い人、という存在が、私を蝕んでいるようだ。 「ったく、気味悪いわね……」 肩を竦めながら再び歩き出し、ふっと小さく溜息を吐いた。 もしも白い人とやらが実在するならば、正々堂々私の前に姿を現したらどうなの? こそこそと後をつけて回るなんて、そんなやり方は私の好みではない。 一体何者か知らないけど…… 「あの、都さん」 「出たな白い人!!」 不意に傍から掛けられた声、反射的にそんなことを言いながら振り向いて――あれ? そこにはきょとんとした表情を浮かべる和葉ちゃんの姿があった。個室の扉がパタンと閉まったところを見ると、和葉ちゃんは丁度部屋から出てきたんだろう。 うーん。和葉ちゃんの洋服って薄い緑だし、どこからどう見ても白くはないなぁ。 「あ、ごめんごめん、なんでもない。どした?」 繕うように笑みながら返すと、和葉ちゃんは尚も不思議そうにしつつも、ふんわりと微笑んだ。 「あのですね、……実は、またお願い事があるんです」 「うん、言ってみ?可愛い子のお願いならお姉さん何でも聞いてあげちゃう」 「あはは、私はそんなに可愛くないですよぉ。……えっと、ですね」 和葉ちゃんは、どこか切り出しにくいように目を逸らす。まぁ、何事かしら。 「……実は、前に勤めていた職場に戻りたいなぁって思うんです、けど……戻りたいっていうかですね、一緒に仕事してた女の子とか、店長さん達のことが心配で……。でも、千景さん達には言えなくて」 「ふむ?……千景ちゃん達には言えないの?」 どして?と首を傾げると、和葉ちゃんは辺りを気にするようにきょろきょろと廊下を見回した後、私に少し身を近づけて小声で続けた。 「私の勤めていたお店……少し、違法なところ、なんです。だから」 「あぁなるほどね。」 和葉ちゃんは確か、風俗店に勤めてたって言ってたっけ。こんな可愛い顔して風俗なんて驚きだわ。 それはともかく、お店が違法なところという話。これは別段驚くことでもない。このご時世、真っ当な商売をして儲けている人間なんて極僅か。私だって怪盗Happyなんて格好良く言ってるけど、実際のところは窃盗罪なんかに引っかかっちゃうわけだしね。 「千景ちゃん達には内緒で、こっそりお店の様子を見に行きたいってことね」 「は、はいッ!それで、もし辺りが危険なようだったら、店長さんや皆もこの施設に保護して頂けたら、と」 「うんうん。それじゃあ……まずは内緒で出かけましょ?それで和葉ちゃんの同僚さん達が保護を望んだら、一緒に連れてくれば良い話だからね」 私がそう提案すると、和葉ちゃんは嬉しそうに笑んで「はいっ!」と元気に頷いた。 まぁ可愛い。この子が風俗嬢なんかやってるんだったら私通ってたのになぁ……なーんて。 「あぁ、でも私……都さんにお願い事してばっかりですね。何か恩返しが出来たらいいのに……」 和葉ちゃんはしょんぼりとして目を伏せる。 そんな様子に少し笑って、ぽむぽむっと和葉ちゃんの頭を撫ぜた。 「じゃあさ、お仕事の腕前を生かして私のこと接待して?」 「はぇ……?接待、ですか?」 「うん。お酒とか注いでくれると嬉し。」 そう言うと、和葉ちゃんは弱く笑んで、「そんなことぐらいなら」と小声で零す。 ……お酒注ぐことが、“そんなことぐらい”か。 彼女の言葉の端に滲んだ、お仕事の実体に苦笑して、 「恩返しなんてそのうちでいいからね。」 と明るく努めれば、和葉ちゃんもまたいつもの明るい笑みを見せて「はい」と頷いた。 「明日のお昼にでも、和葉ちゃんの部屋に迎えに行くから。OK?」 「わかりました。お世話になります」 「いーえ。それじゃ、おやすみぃ」 「はいっ、おやすみなさい!」 深く頭を下げてくれる和葉ちゃん、全くもって可愛らしい。 礼儀正しく見送られ、私はご機嫌で自室へ続く廊下を歩み出したのだった。 ――明日ぐらいは、白い人もお休みしてくれると嬉しいかな。 可愛い子とのデート、邪魔されたくないもんね。 「……あれ?」 少女の姿を見かけ、私―――高村杏子―――は足を止めた。つい先ほどまで一緒にいた少女、冴月ちゃんだ。冴月ちゃんのパソコンを回収して、この地下施設に戻って来たのは零時半ぐらいだったか。それから私達は「おやすみなさい」と挨拶を交わして解散した。 その後一旦部屋に帰ったは良いものの、どうにもこうにも退屈で私は再び部屋を出た。同室の未姫さんも眠っていたし、ね。そして偶々通りかかった薄暗い食堂で、ぼんやりと浮かぶ光を目にしていた。 光源は、冴月ちゃんが向かっているパソコンが放つものだ。冴月ちゃんは私には気づかずに、じっとパソコンの画面を見つめていた。薄暗い場所、パソコンと、パソコンのそばに置いてあるコーヒーと、そして幼い少女――手首に幾つもの傷がある、少女。 この光景。……どこかで、見たような気がする。いわゆるデジャビュ。既視感というものだ。 だけど私はこんな光景を見たことはない。ただ、知っているだけで。 足音を忍ばせて、冴月ちゃんの背後に近づいていく。食い入るように画面を見つめている冴月ちゃんは、やはり私のことには気付かない。 驚かせちゃおうかな、とそんな企みを胸に秘め、息を吸い込んだ、――けれど。 冴月ちゃんのパソコンの画面に表示された文字。それを目にして、思わず動きを止めていた。 私にも見覚えがある。それは「メッセンジャー」と言われるネット上でのコミュニケーションツールの、ログ画面だった。メッセンジャーとは、チャットを手軽に行なうことの出来るツール。アドレスを登録し合い、互いにメッセンジャーを起動していれば相手のオンライン状況なんかも把握することが出来る。ログっていうのは、要するにチャットでの会話を保存したもの。メッセンジャーでの会話は逐一、ログとして保存されているのだ。 そのログには二つのハンドルネーム。 『セナ』と『月見夜』。 少しだけ息を飲んで、それから、声にして吐き出した。 「……わっっ!!!」 「うわぁぁ!?」 目論み通りに冴月ちゃんを驚かすと、冴月ちゃんは見事にビクッと身を竦ませ、目を丸めて振り向いた。 「びび、びっくりしたぁ。杏子お姉さん……?」 「えへへ、驚かせちゃった。何してるの?」 「え?え、えっと……」 冴月ちゃんはどこか慌てた様子でパソコンから伸びたマウスを動かし、メッセンジャーのログ画面を消した。それから再度私に目を向け、困ったように笑んでみせる。 「な、なんでもないよ。その……パソコン、ちゃんと動くかなって、テスト、みたいな」 繕うようにそんなことを言ったけれど、動作テストのためにメッセンジャーのログを開くことはしないだろう。 セナと月見夜の会話は、隠したいものなのだろうか。 ……ま、それもそっか。普通、プライベートの会話を人に見せる気にはなれないもんね。 「隣、座ってもいい?……眠れないの」 「うん、いいよ。杏子さんも眠れないの?あ、あたしは夕方に起きたから当然か」 「ふふ、私も今日は寝坊しちゃった。元々夜型だからねぇ」 冴月ちゃんの隣の席に腰を下ろして、冴月ちゃんの横顔、思わず見つめていた。 冴月ちゃんは私の視線に気付くと不思議そうな顔をする。「なんでもない」とごまかして、冴月ちゃんのパソコンに視線を移した。 なんだか、話題が浮かばない。なんでもないことを話して、なんでもなく、笑って。 そんなコミュニケーションが、上手く取れなくなってしまって。 「……杏子、さん?」 「う、うん?」 ぽつりと名前を呼ばれ、笑みを繕いながら応える。私の様子……おかしいだろうか。 冴月ちゃんはやはりどこか不思議そうにしながらも、パソコンをいじりながら言葉を続けた。 「杏子さんも、パソコンしてたって……言ってた、よね?」 「あ、……うん。してたよ。」 「じゃあ、さ……チャットとかメールとかそういうので、知らない人と話したこと、ある?」 「ネット上だけの関係、っていうこと?」 「……うん。」 内心、少しだけドキドキしながら、冴月ちゃんの言葉を耳にして。 どう応えて良いか迷ったけれど――嘘をついてどうなるものでも、ないし。 「……あるよ。何人か。……チャット、とか」 「あるんだ?へぇ……」 私の答えに、冴月ちゃんは感心したように私を見上げ、「そっか……」と呟きながらパソコンに目を戻す。 それからまた少しの沈黙が流れ、やがて次の言葉を切り出したのもまた、冴月ちゃんからだった。 「会ってみたい、とか。思った?……その、ネットの向こう側の人に」 「……」 言葉を、失ってしまう。 私。何て答えたらいいんだろう。 会っ…… 「あ、ご、ごめん、なんか変なこと聞いちゃった。……あたし、部屋、戻ります」 冴月ちゃんは慌てたように言って、パソコンの電源を落とした。 黙りこんでしまった私に気を使ってくれたのだろうか。 「こっちこそ……ごめんね」 小さく謝ると、冴月ちゃんは不思議そうな顔をして「い、いえ」と首を横に振った。 それから電源の落ちたパソコンを抱え、 「おやすみなさいっ!」 と頭を下げて、慌しく食堂を後にしてしまう。 私はその背中を見送って、それからふっと溜息を零した。 しん、と静まり返った食堂。……あ、冴月ちゃん、マグカップ片付けるの忘れてる。 マグカップを手に取ると、中にはまだ温かいコーヒーが残っていた。 私、追い出しちゃったかな。……そんなつもりじゃなかったのに。 「冴月ちゃん……かぁ」 温かいマグカップを両手で包んで、少し迷ったけれど、残ったコーヒーを口にする。 口の中に広がるコーヒーは甘くて、薄くて、子どもっぽい味だった。 私、知ってたんだよ。 マグカップの中身がコーヒーだっていうことも、そしてそのコーヒーが甘いことも。 前に話してくれたもの。ここで出会うより、前に。 冴月ちゃん。……ううん、セナちゃん。 あの子の姿を見た時から、薄々気付いてた。 『セナ : あたしはねぇ、コーヒー飲みつつ暗ーい部屋でパソコするの好きなのですー』 『月見夜 : いかにも不健康って感じね。コーヒー飲みすぎたらアレだよ、胃が悪くなるよ?』 『セナ : 大丈夫!あたしが飲んでるコーヒーってめっちゃ薄いし、甘いし』 『月見夜 : ありゃ、お子様だなぁ。ブラックとか言って欲しかったよvv』 『セナ : ぷー、ほっといてくださいー』 『セナ : 多分、月見夜さんがあたしのこと見かけたらすぐにわかると思います』 『月見夜 : なんでなんで?セナちゃんって目立つの?』 『セナ : 目立つっていうか……微妙(笑)』 『月見夜 : 微妙ってなにー。知りたいよー』 『セナ : えっとね。手首にいっぱい傷がある子、って覚えれば良いのです。』 『月見夜 : あ、そっかぁ。だめだぞ、セナちゃん。痛いことしちゃめっ☆』 遼ちゃんが、冴月ちゃんのことをセナって呼んでいた。 それを聞いて、あぁそっか、って。なんだか自然に納得してた。 だってセナちゃんは……私の思っていた通りの子だったもの。 まだ幼げな顔立ちも、中身はしっかりしてるところも、でもどこか自虐的なところも? 手首の傷って本当だったんだなぁって、複雑な気持ちを抱いたりしながらも、 やっぱり、嬉しかったよ私。 セナちゃんは本当のセナちゃんを、私に―――月見夜に見せてくれてたんだね。 でも、私は。 「言えないよ……」 セナちゃんが、月見夜と高村杏子が同一人物だって知ったら、きっと幻滅する。 月見夜がこんな人間だったなんて、ってね、きっと…… 私のこと、嫌いになるよ。 だから言えない。 だから言わなかった。 だからあの時、私は―― 『セナ : あたし、月見夜さんと会ってみたい』 『月見夜 : セナちゃんとは会えないよ。ごめんね』 あ、あぅ……。 あたし―――蓬莱冴月―――ってば、なんか、もう……どうかしちゃってるよ!! 杏子さん変に思っただろうなぁ。いきなりあんな質問したりして、わけわかんないよね。 困らせちゃったみたいだし、折角隣に座ってくれたのに、あたし逃げちゃったみたいだよ。 失礼なこと、しちゃった、よね……。 「はぁ……」 遼と相部屋の部屋で、ベッドに寝転がって溜息一つ。あたしが溜息なんかついてれば、遼が突っ込んできそうなもんだけど、今は遼はぐっすりお休み中。あぁあれだなぁ、年寄りは早寝早起きっていうか。 そんなことはどうでもいいんだけど、杏子さんのこと、あぁーもう、頭ぐちゃぐちゃしちゃってるよぅ。 「……なんで、あたし」 目ぇ、おかしいの、かな。 目とかそんな問題じゃないかも。頭?頭おかしい?うわ、それは重症だぁ。 ……なんで、こう、逃げたりしちゃったか、っていうと。 さっきあたしが杏子さんに投げ掛けた問い。 『会ってみたい、とか。思った?……その、ネットの向こう側の人に』 そう、問いかけた時に、ふっと見せた杏子さんの困ったような表情。 それを、どこかで見たことがあるような、気がして。 実際に見たことなんてあるはずはないんだ。だけど、知ってるような気がして。 『セナ : あたし、月見夜さんと会ってみたい』 それはもう半年ぐらい前のことだ。メッセンジャーで、月見夜さんに投げ掛けた言葉。 それに対して彼女は――三分間ぐらい、返事をくれなかった。 あぁ困ってる、困らせてるって、凄く自責したのをよく覚えてる。 そしてあたしがその発言、前言撤回しようと思ってキーボードに手を置いた時だった。 彼女は言った。 『月見夜 : セナちゃんとは会えないよ。ごめんね』 ネット越しの人、あたしは彼女の顔なんて見えるわけもないし、声も聞こえないし。 だけど、そのネット特有の“間”というものに現れてた。月見夜さんの戸惑いが。 その時の、表情。――さっきの杏子さんみたいな顔だったんじゃないかなって、そんなこと、思った。 違う。杏子さんと月見夜さんは全然関係のない存在だ。 なのに、あたし。 一瞬、杏子さんが月見夜さんに見えて、ドキッとした。 あ、ありえないよね。こんなこと考えるなんて、あたし、本当にどうかしてる。 ただちょっと前に、偶然月見夜さんのメール拾っちゃっただとか。偶然夢に出てきたとか。そんなので敏感になってるだけなんだ。でも全ては偶然でしかないんだ。月見夜さんのメールだって、ランダムなアドレス指定して送るような広告メールだったのは確認したし、それにあんな夢だって、ただ、偶然ッ……。 わかってる。わかってるよ、月見夜さんはもう、あたしのそばにはいないんだから。 今更、思い出したりしないでよ、あたしのバカ。月見夜さんは過去の人なんだから! 「ッ……」 悔しくて、なんだか馬鹿馬鹿しくて、キュッと唇を噛んだ。 好きだったよ、好きだったのは認めるよ。あたしは、ネットの向こう側の女性に恋をしていた。 だけど――あたしは、振られたのと、同じだもん。 月見夜さんはあたしなんか、大した存在でもなかったんだよ。わざわざ会ってくれるわけなんかない。 ただ、ネット上だけで他愛もないことを話して、そんな関係で良かったんだ。 なのに、あたしが会いたいなんて言ったから……愛想、尽かされちゃったんだよ。 忘れよう。忘れてしまおう。もう月見夜さんとは関係無い。 あたしは、過去の恋愛なんて、どうでもいいよ。 だからお願いだよ月見夜さん―――あたしを、放して。 カチャリ。水散さんとあたし―――真田命―――が過ごしている部屋の扉を片手で開けて、「よっと」、軽く声を上げながら肩を使って上手く部屋の中に滑り込む。片手が塞がっているのは、温かいミルクと食事を乗せたお盆を持っているからだ。遼や伊純嬢と別れてから遅い晩御飯を食べた後、この食事を調達して部屋に戻って来たのである。 食堂を出てからすぐに冴月と出くわしたんだけど、冴月ってばあたしを見た途端敵を見るような目ぇするんだもん。「今は訊かないよ」って一言告げて、「そっか」と呟く冴月とすれ違った。 あの子の隠し事が気にならないわけじゃないけれど。あたしには冴月よりももっと、気になる人がいた。 「水散さーん」 室内にいる相部屋の人物に声を掛け、もう起きてるかな?と小首を傾げた。 しかし、ベッドに眠っている水散さんは、今も安らかな寝息を立てている。 「……早かったかな」 そろそろ起きるだろうと予測して、こうして簡単な食事を持ってきたのだけれど、今も尚水散さんは深い眠りの中にいるようだ。もう、かれこれ十八時間ぐらい眠っていることになる。 あたしは食事の乗ったお盆を部屋の隅のテーブルに置くと、すやすやと寝息を零す水散さんに近づいた。彼女が身を横たえるベッドに腰を掛け、寝顔にそっと手を伸ばす。微かに朱の差した頬を撫ぜ、柔らかな茶色の髪を指先で梳いてみる。そんなあたしのちょっかいにも反応はなく、水散さんは眠り続けていた。 水散さんが眠りに落ちる前―――昨日、一体何があったのか、あたしにはまだ把握できていない。 この部屋で眠ろうとした時、突然佳乃さんの切羽詰った声が聞こえてきて。部屋を飛び出してホールに向かうと、千景さんの攻撃によって倒れたのであろう米軍の兵士と、銃を手にしたままで一息つく千景さんの姿があった。その時あたしは――もう、騒動は片付いているのだと、そう思った。実際、米軍兵士が崩れ落ちている箇所には血液も落ちていたし、もしかして死んでる?と。 だけど。その油断こそが間違いだった。気を抜いたその時、突如、腕に鋭い痛みが走った。 バランスを崩し、ドンッ、と背を壁に叩きつけられて――そしてあたし、間抜なことにそのまま気を失った。 あの時、あたしは確かに腕を撃たれたはずだったし、その証拠にベッドサイドに畳まれていたあたしの服には銃弾が通って破れた部分がくっきりと残っている。 それなのに。あたしの腕には、何の痕も残っていなかった。治療をしたとかそんなんじゃない、何もなかったように肉があり、血が通い、皮膚が覆う。 あたしが目を覚ましたのは、昼下がりの頃だったか。隣のベッドには眠っている水散さんの姿があった。 状況が掴めず、水散さんを起こそうかとも考えたけれど、それも野暮なことだと思い留まり、あたしは部屋を出た。そして訪ねたのは婦警達の部屋。 出てきたのは佳乃さんだった。あたしが昨日のことを問い掛けても、佳乃さんはどこか不思議そうな様子で首を捻り『私にもよくわからないんです』と曖昧なことを言う。そして彼女はこう続けた。 『水散さんに聞くのが一番早いと思いますよぉ。多分、私が話しても納得出来ないんじゃないかな』 更に追求したい気もしたが、やめておいた。佳乃さんに聞くと話が迂曲してしまいそうだということと、もう一つは出かけていたのであろう千景さんが戻って来たということ。千景さんとはどうも話が合いそうにない。だからあたしは婦警から話を聞くことは諦めて、部屋に戻った。 水散さんはずっと目を覚まさない。寝坊しそうなタイプには思えないんだけど、何かに取り付かれているように彼女はずっと眠り続ける。だから仕方なく、あたしは水散さんが目を覚ますまで待っていることにした。 午前一時。 先ほど持ってきた食事もすっかり冷めてしまっただろう。それはまた後で作り直せば良い話だけど。 それよりもあたしの危惧は水散さん自身に向けられる。こんなに長々と眠っているなんて、身体のどこかが悪いのだろうか。もしかしたら、眠り姫のようにずっと目を覚まさないのではないか。 不安になって、そっと水散さんの手に触れた。平熱の低いあたしが触れると、心地良い温度が感じられる。 柔らかい感触。気持ちよくて、彼女の手を緩く握っていた、 その時、「ふぁ」と微かに漏れた吐息に気づき、あたしは水散さんの顔を見つめる。 規則的な寝息が止んでから、少し。やがて水散さんは、長いこと閉ざされていた瞳を静かに開いた。 「……やっと、起きた?」 少し笑って、薄っすらと目を開ける水散さんに声を掛ける。 水散さんはゆっくりと目を動かし、やがてあたしの姿を捉えた。 「おはようございま……ふぁ」 気の抜けた挨拶に、思わず笑みが漏れていた。 彼女が目を覚ました、たったそれだけのことに心底安堵している自分に気付く。 昨日会ったばかりの女性なのに、そこまで多くの言葉を交わしたわけでもないのに。 それなのに不思議と、知っているような気がするの。 この安堵感だとか、彼女の見せる笑みを目にした時に感じる気持ちだとか。 なんだかとても柔らかで、懐かしい感情。 「命さん……」 と、水散さんはあたしの名前を呼んで身じろいだ。身体を起こそうとしたようだけれど、すぐに力を抜いてベッドに身を委ねる。まだ頭がはっきりしないと、そんな様子で瞬きを繰り返す。 「おはよう。……よく眠れた?」 「……ふぁい」 水散さんはベッドに腰掛けたあたしの方に寝返りを打ち、距離を縮める。そうして真下から見上げるような視線をあたしに向けては、少し照れくさそうに微笑んで。あたしはそんな水散さんの髪に手を伸ばし、くすぐるように指先で梳いた。水散さんはくすぐったいような、それでいて心地良いような仕草をして、目を細める。 そんな時間をどれぐらい過ごしたか。 まるで恋人のようなじゃれあい、あたしはそういうこと、慣れているわけでもないのに。 冷たい、と――何人の人に言われただろう。あたしの気持ちはいつも冷めていた。 だけど今は違う。こんな気持ち知らないはずなのに、すごく懐かしくて愛しい気持ち。 どうしてあたし、水散さんにこんな感情を抱いてるんだろうって不思議に思いながら、彼女の微睡に心を委ねていた。 「命さん……傷、もう痛みませんか?」 水散さんはあたしを見上げてぽつりと問いかけ、それからゆっくりと上体を起こす。 頭が重いと、そんな様子で額に手を当てながら、彼女が視線を向ける先はあたしの右腕。 そこには彼女が言う通り、傷があるべきなのだ。だけど―― 「傷、って。……これのこと?」 あたしは服の袖を捲くり、傷痕も何も残っていない腕を示して見せた。 水散さんはパチパチと瞬きながらあたしの腕を見つめた後、ふっと安堵するように微笑んで見せる。 「良かった。痕、残らなかったですね。」 「残らなかった……?」 やはり話が見えずに問い返すと、水散さんはきょとんとした表情を浮かべた後、「あ」と何か気づいたように声を上げた。 「まだ聞いてないんですね。千景さんとか佳乃さんに」 「聞いたけど教えてくれなかったの。水散さんに聞けばわかる、って」 「……なるほど」 ようやく合点といった様子で水散さんは小さく頷くと、ぺたんとベッドに座りなおしながら、「えっとですね」と切り出した。 「まだ聞いていないならば驚かれたと思います。昨日命さんは確かに、銃で腕を撃たれました。」 「うん……」 「その、傷を。……私が治癒させて頂きました。」 「……、……治癒?」 あまり聞きなれない言葉に、眉を顰めて問い返す。 水散さんはこくんと頷いて、それから何かを探すようにあたしの手をじっと見つめる。 「お話だけじゃわかりにくいと思うので……、ちょっと失礼しますね」 水散さんは両手であたしの手を取って、手の甲に微かに残っている小さな切り傷に親指で触れた。 「この傷は?」 「えっと……こないだ鎌で切ったんだと思うけど」 「なるほど」 それは、あと一週間もすれば跡形もなく消えてしまうであろう、ほんの微かな傷。 水散さんはそんなあたしの手の甲の傷に――手を翳した。 「見てて下さいね」 と、ぽつりと呟いてから、水散さんは静かに目を閉じる。 その時――ふっと。彼女の手の中に、ぼんやりと光が生まれた。 信じられない光景だった。人が何の道具も使わずに光を生み出すなんてこと、出来るわけがない。 だけど、驚くのはこれからだった。 水散さんの手の平から生まれた光があたしの手を包み込んだかと思うと みるみるうちに、あたしの手の甲の微かな傷が―――消えていく。 「う、そ……」 「……驚きました?」 水散さんが手を離せば、彼女の生んだ光もふっと消えていった。 まるで手品のようだ。その裏にタネがあって当然だった。しかし、手の甲にあったあたしの傷は、確かに跡形もなく消えていた。指先で触れても、そこに傷があったなどと思えない感触だ。 「これが私の……治癒能力なんです」 水散さんは微笑んでそう告げてから、ふっと小さく息をついた。 治癒能力。――普通ならば、ありえない、その能力。 だけど彼女は証明した。それをあたしの目の前で実践して見せた。 信じられない、けれど、信じざるを得ないことだ。 実際、こんな力でもなければ一晩で銃で撃たれた傷が消えるはずもない。 「どうしてこんなことが……」 「私にもよくわからないんですけど……おそらく、命さんの持つ治癒力を引き出すと共に、私自身の治癒力で補いながら治癒を行なうのだと思います。だからちょっと……いえ、すごく。寝坊しちゃったみたい、です」 水散さんはちらりと時計に目を向けて、照れくさそうに苦笑して見せた。 つまり、水散さんは……その身を削って、あたしの傷を癒してくれたってこと、よね。 大きな疲弊を伴っても、尚。 「そんなわけで、」 「水散さん」 あたしは彼女の言葉を遮って、ぽつりとその名前を呼んでいた。 水散さんは言葉を切り、不思議そうにあたしを見つめる。 ―――この人。 あたしの運命と関係している。そんな気がしてならない。 実際、彼女の手当てがなければ、命を脅かす傷だったのかもしれない。 彼女が心優しい女性だっていうのはわかるけど、こうまでしてあたしに尽くしてくれるなんて。 何とも言えない、けど、なんだか―― あたしはこの人、離しちゃいけないような、気がする。 「あ、ありがとう……」 少し慣れないお礼の言葉、ぽつりと告げながら彼女の肩に手を伸ばす。 「いえ、当然のことをしたまでです」 微笑みながらも、あたしの手に不思議そうにする水散さん。 少し躊躇ったけど、あたしは――彼女の身体、そっと抱き寄せていた。 「み、命さん……?」 驚いたような声を上げながらも、抵抗はせずにあたしに身を委ねる水散さん。 懐に彼女の身体を抱きこんで、緩く、包んだ。 この温度。あたし、知ってる。 この匂いも、彼女の大きさも、彼女の吐息も。 何もかも、初めてじゃない。あたしはこうして彼女を、抱きしめたことがある。 ―――そんなはず、ないのに。あたしと水散さんは昨日会ったばかりなのに。 「水散さんとは……初めて会った気がしない。」 「あ……」 「あたしのこと、知ってる?」 囁くように問うと、水散さんは小さく身じろいで顔だけを上げた。 不思議そうにあたしを見上げ、それからふっと目を伏せて。 「……初対面です。でも」 水散さんは一旦言葉を切ると、その頬をあたしの胸元に寄せた。 今度はされるがままではなく、彼女から身を寄せてくれた。 「―――私も、命さんにどこかで会ったことがあるような、気がします」 あぁ、やっぱり。 あたしだけじゃないんだ。水散さんも同じ気持ちを感じてくれている。 悠祈、水散さん―― 昔どこかで出会ったような、 昔どこかで、愛したような……。 |